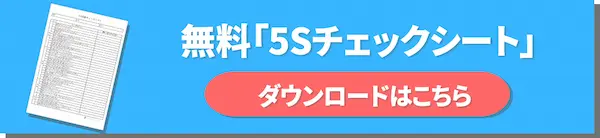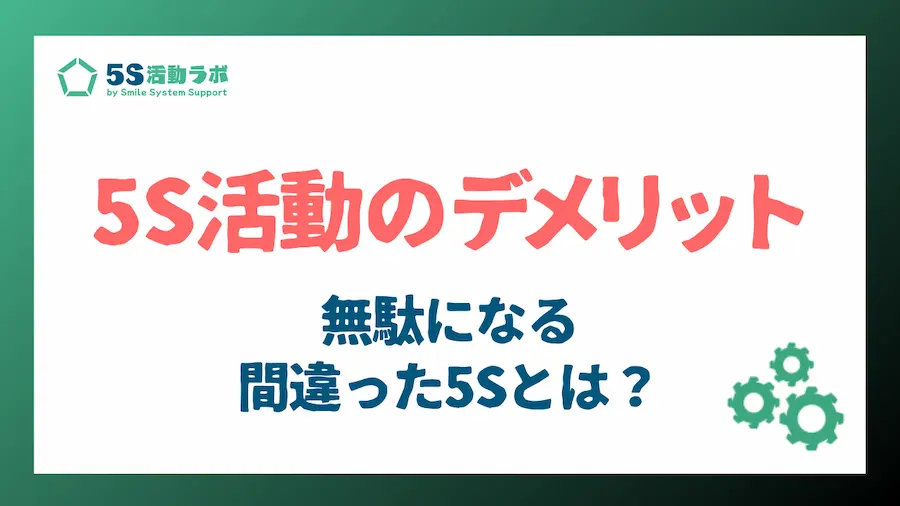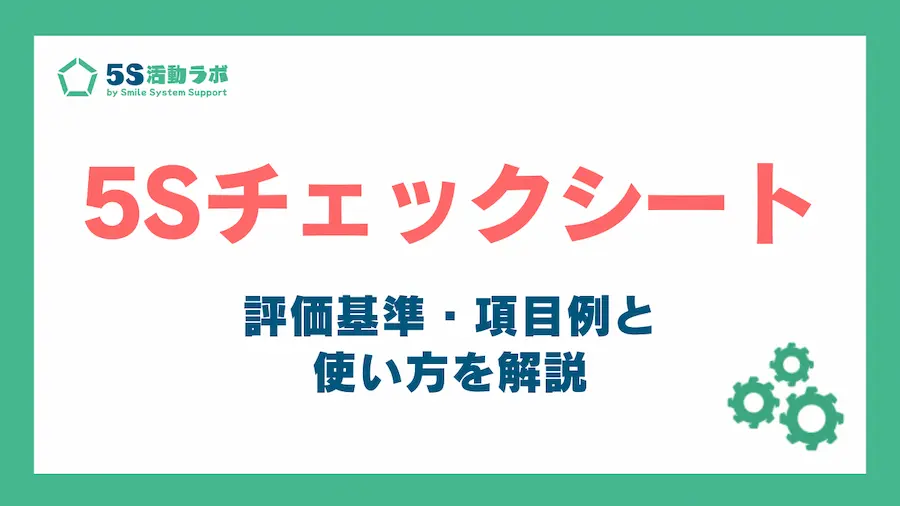
5S活動を定着させるには、「いま職場がどうなっているか」を客観的に確認できる仕組みが欠かせません。
そんなときに役立つのが 5Sチェックシートです。
この記事では、まず 5Sの基本ができているかを診断できる11項目のチェックリスト表 をご紹介します。
さらに、改善活動に直結させるための 詳細なチェックシート(Excel/PDF)も無料ダウンロードできるようご用意しました。
「評価基準や項目例を知りたい」「どんな頻度で実施すればいい?」といった疑問にもお答えしていますので、ぜひ最後までご覧ください。
👉5Sとは?職場改善の基本を徹底解説!目的・進め方・成功事例をわかりやすく紹介
もくじ
5Sチェックシートとは?
5Sチェックシートとは、職場における 整理・整頓・清掃・清潔・躾 の取り組み状況を確認するための点検シートです。
日常業務の中では「慣れ」によって乱れを見過ごしてしまいがちですが、あらかじめ定められた項目に沿って確認することで、現状の良い点や改善が必要な点を客観的に把握できます。
チェックリストは、5Sを継続的に推進していくうえで「現在地」を知るツールでもあります。
一度だけ実施して終わりにするのではなく、定期的に点検を繰り返すことで改善のサイクルを回すことができます。
5Sチェックリストを使うメリット
現状把握がしやすい
個人の感覚ではなく、シートを通じて「できている/できていない」が一目でわかる。
改善の優先順位が立てやすい
チェック結果を一覧化することで、どこから着手すべきかを整理しやすい。
チームで意識を合わせられる
同じシートを共有することで、改善点の認識をメンバー全員で統一できる。
継続改善の仕組みになる
定期的に点検を繰り返すことで、改善が習慣として根付いていく。
簡易版チェックリスト表(5S現状チェック11問)
以下の11項目は、5Sの基本が現場で守られているかを一目で確認できる内容です。
まずは「いくつ当てはまるか」をチェックするだけで、職場の現状を簡易的にジャッジできます。
| No. | チェック項目 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 床に直置きしている | 転倒や掃除不良の原因。基本は直置き禁止。 |
| 2 | 壁に立てかけ置きをしている | 地震時に倒れて危険。安全対策が必須。 |
| 3 | 棚の天板の上にモノを置いている | 落下リスク大。重い物は下段へ。 |
| 4 | コードが床に這っている | つまずきの危険。カバーなどで対策。 |
| 5 | 棚や掲示物で窓を塞いでいる | 採光・換気・避難経路の妨げになる。 |
| 6 | 掲示物を壁に直貼りしている | 情報が埋もれやすく見栄えも悪化。掲示板で管理。 |
| 7 | 全てのモノの定位置が決まっていない | 探し物・紛失の原因。定位置を設定する。 |
| 8 | 全てのモノの適正量が決まっていない | 在庫の過不足を生みムダが発生する。 |
| 9 | 全てのモノ・場所に標示がされていない | 誰にでも分かる表示で迷いを防ぐ。 |
| 10 | 区画線が引かれていない | 通路・作業場を区切らず事故リスク増。 |
| 11 | 紙媒体が多い(データ化できていない) | 保管・検索が非効率。可能なものはデータ化。 |
この11問でまずは現状を把握できます。
さらに一歩踏み込んで改善を進めたい場合は、より詳細な項目までカバーした正規版シートをご活用ください。
ぜひ無料でダウンロードして、現場での改善活動にご活用ください。
このオリジナルチェックリストの特徴
一般的な5Sチェックリストには、点数をつけて合計点で良否を判断するタイプもあります。
一方で、今回ご提供するオリジナル版は、点数化ではなく “気づきを残す”ことを重視した設計 になっています。
点数式ではなく「気づき記録型」
本シートは、Yes/Noでチェックするだけでなく、気づいたことを自由に書き込める欄を用意しています。
数字を追いかけるのではなく、改善のタネを見つけることを目的としています。
「気づき」が記録されることで、次回の点検や会議の際に具体的な改善アクションに直結します。
さらに、点検を繰り返すことで自然と「改善の視点」が鍛えられ、現場の小さな異常や変化にも気づきやすくなるという効果があります。
どの現場にも使える普遍設計
製造業や工場・物流倉庫・事務所・病院・介護など、業種を問わず利用できます。
特定の業種専用のリストではなく、「5Sの基本原則」だけを切り出した普遍的なチェックリストなので、誰でも導入しやすいのが特徴です。
短時間・低負荷で運用できる
A4サイズでまとまっているため、短時間で現状確認が可能です。
日常業務の合間に取り入れやすく、無理なく継続できる形にしています。
「チェックすること自体が負担になって続かない」という悩みを解消する設計です。
評価基準はどう考えるべき?
5Sチェックリストを探している方の多くは、「合格ライン」や「点数での判断基準」を求めています。
実際、一般的なシートには以下のような例が見られます。
- 80点以上 … 良好
- 60〜79点 … 要改善
- 59点以下 … 重点的な改善が必要
しかし、今回ご紹介しているオリジナルチェックリストは 数値での評価を目的としていません。
「何点だったか」よりも、現場で気づいたことを具体的に書き出すことを重視しているからです。
数値化してしまうと「点数を上げること」が目的化しやすく、本来の改善行動がおざなりになる危険があります。
そこでこのシートでは、Yes/Noチェックに加えて「改善すべき点」や「感じたこと」を記録することで、次の行動に直結する評価の仕方を採用しています。
なお、もし「数値化したい」という場合は、Yes=1点、No=0点と換算すれば、合計点を出すことも可能です。
ただし、あくまでも参考値と考え、本来の目的は“改善につなげること” である点を忘れないようにしましょう。
5Sチェックシートの活用方法(4ステップ)
このチェックシートは、日常の自己点検だけでなく、全員参加型の5Sパトロールで活用すると大きな効果を発揮します。
以下の流れで取り組むことで、改善が組織全体に広がっていきます。
ステップ1:全員で全部署をパトロールする
チームごとに分かれて、社内の全部署や共有スペースを回ります。
その際に5Sチェックリストを使い、気づいたことを記録していきます。
「他部署の視点」で見てもらうことで、自分の部署だけでは気づきにくい改善点が明らかになります。
ステップ2:チームで気づきを共有する
パトロールを終えたら、チームに戻って気づきを持ち寄ります。
リーダー主導で一人ひとりから意見を出し合い、リーダーが意見をまとめます。
この過程で、メンバー同士の意識も揃っていきます。
ステップ3:気づきを発表する
各チームから、見つけた気づきを全体に向けて発表します。
自部署に関する指摘が出た場合は必ず記録しておき、改善の材料にします。
他チームからの客観的な意見が、改善のヒントになります。
ステップ4:改善策を考え、計画を立てる
発表後は、チームに持ち帰り、改善策を検討します。
「どの改善を優先するか」「いつまでに実行するか」を具体的に計画し、実行に移します。
計画と実行を繰り返すことで、改善が積み重なりやすくなります。
💡 運用のポイント
このサイクルを 月に一度 全員で行うと、改善が加速します。
繰り返すことで、自然と「気づきの視点」が鍛えられ、現場の小さな異常にも敏感になっていきます。
こちらの当社オリジナルのチェックシートには記入欄もあるので、この運用にそのままご利用いただけます。
よくある失敗と防ぎ方
5Sチェックリストは、形だけ実施してしまうと効果が半減してしまいます。
ここでは、よくあるつまずきとその防ぎ方を整理しておきましょう。
チェックして終わりにしてしまう
失敗例:シートに記録しただけで、その後チーム内や全体での共有がされていない。
防ぎ方:必ずチームで「気づきの共有 → 発表 → 改善策検討」という流れを踏む。
気づきが出てこない
失敗例:パトロールをしても「特に問題なし」で終わってしまい、形だけの活動になってしまう。
防ぎ方:最初は気づきが少なくても問題なし。繰り返すうちに自然と視点が鍛えられ、だんだんと小さな改善点にも気づけるようになる。
改善策を立てない/実行に移さない
失敗例:チェックはしても「誰が・いつまでにやる」が決まらず、改善が進まない。
防ぎ方:必ず担当者と期限を設定し、次回の点検でフォローする仕組みをつくる。
やりっぱなしで習慣化されない
失敗例:一度やって終わり、継続されない。
防ぎ方:月1回など定期的にパトロールを仕組み化し、必ず改善策と実行計画までをセットにする。
こちらもCHECK
-

5S活動のデメリット~無駄になる間違った5Sとは~
日本の製造業では「5Sは当たり前」と言われるほど重視されており、取引先の評価基準になることもあります。 実際に「5Sができていない会社とは取引しない」と公言する企業もあるほどです。 その ...
続きを見る
よくある質問(FAQ)
Q1. チェックはどのくらいの頻度で実施するのが効果的ですか?
おすすめは月に1回の全員パトロールです。
定期的に振り返ることで改善サイクルが回りやすくなり、習慣として根付いていきます。
大きなレイアウト変更や繁忙期の後に臨時で行うのも効果的です。
Q2. チェックは一人でやってもいいですか?
はい、一人でも実施可能です。大切なのは「全員が自分の目で職場を見ること」。
一斉に回る必要はありませんが、全員がチェックに参加することが重要です。
そのうえで、チェック後には必ず意見を持ち寄り、共有する場を設けることが改善につながります。
Q3. チェックした内容はどのように活用すればいいですか?
シートに書いた気づきは、チームで共有し、改善策につなげることが大切です。
単なる記録で終わらせず、「誰が・いつまでに改善するか」を決めて計画に落とし込みましょう。
その上で次回のパトロール時に再確認すれば、改善の進歩がわかります。
Q4. チェック後に改善が進まない場合はどうすればいいですか?
改善が進まない原因の多くは、担当者や期限が決まっていないことです。
必ず実行計画を立て、期限を設定し、次回のパトロールで確認する仕組みをつくりましょう。
小さな改善からでも積み上げることで、継続的な改善が進みやすくなります。
Q5. 初めて導入する場合、まずどこから始めればいいですか?
まずは小さく始めることがおすすめです。
全社一斉にやろうとすると準備が大変なので、最初は1部署や1エリアで試してみましょう。
その後、効果や手応えを感じられたら範囲を広げていくと、スムーズに定着します。
Q6. 評価基準や評価方法はどうすればいいですか?
一般的なチェックリストでは点数を合計して「80点以上で良好」といった基準を設ける場合があります。
ただし、このオリジナルシートは点数化よりも気づきを重視する設計です。
繰り返し行うことで気づきの質が高まり、改善が積み重なっていくこと自体が評価の代わりになります。
どうしても数値で比較したい場合は、Yes=1点、No=0点で合計すれば簡易的な評価方法として使えます。
5Sチェックシートを無料でダウンロード
今回ご紹介したオリジナルの5Sチェックシートは、Excel版・PDF版を無料でダウンロードいただけます。
点数式ではなく「気づき記録型」の設計で、誰でもすぐに実践に活かせるシンプルな内容になっています。
まとめ
5Sチェックリストは、職場の現状を客観的に振り返り、改善のきっかけをつくるためのシンプルなツールです。
一般的には点数で評価する形式もありますが、今回ご紹介したオリジナル版は “気づきを残すこと”に重点を置いたチェックシート。
繰り返し使うことで視点が鍛えられ、小さな変化にも気づきやすくなります。
さらに、全員で共有し改善策を立てることで、形だけで終わらない「改善のサイクル」を職場に根づかせることができます。
ぜひ、この記事で紹介したオリジナルチェックリストを活用し、日々の業務改善の一歩に役立ててください。