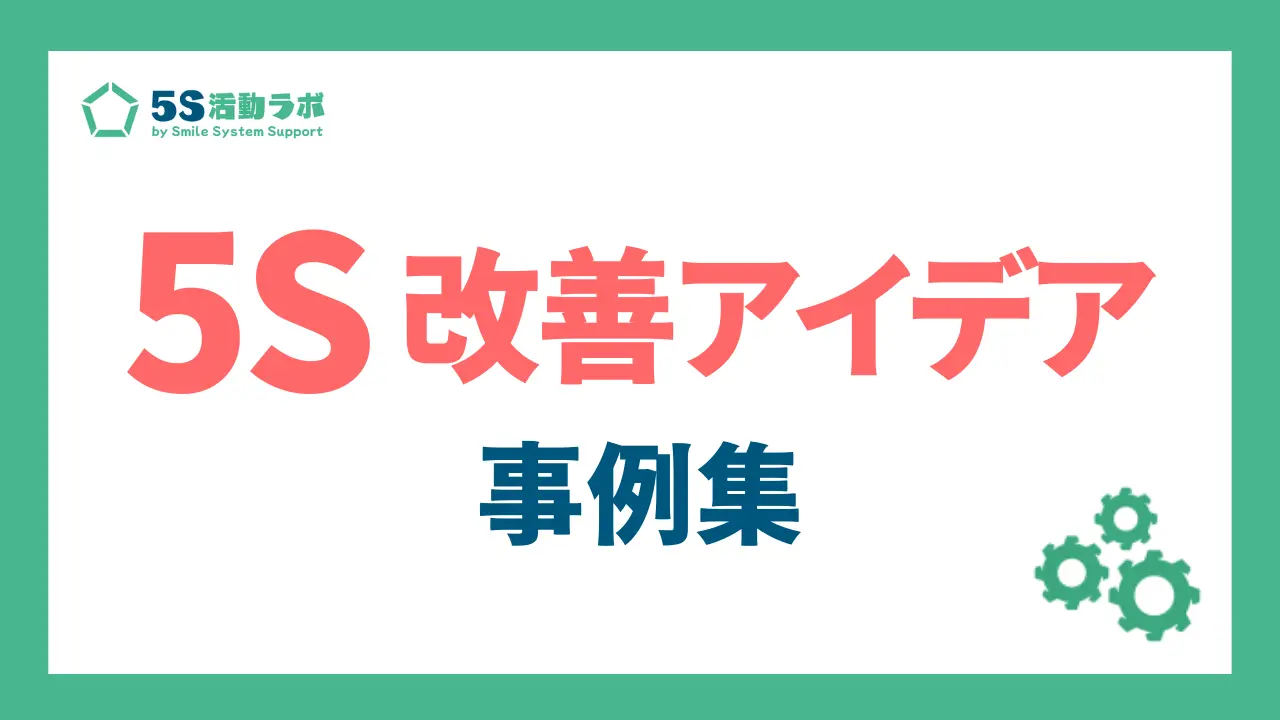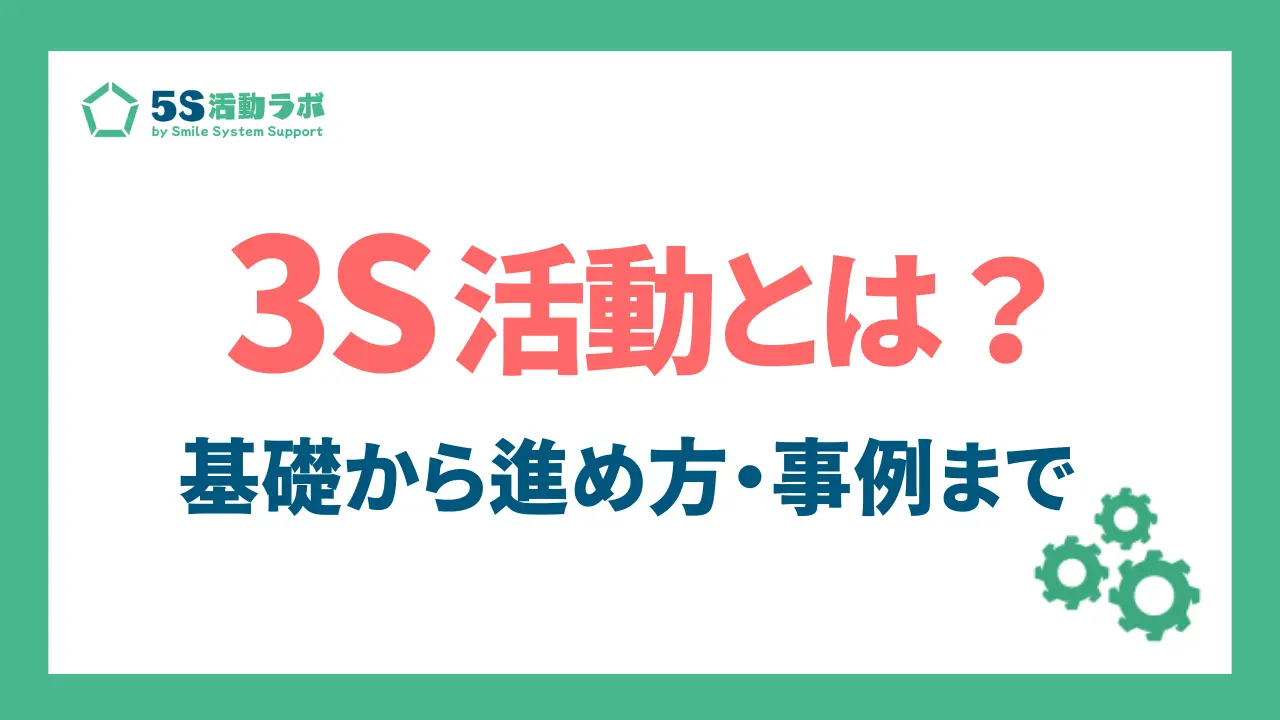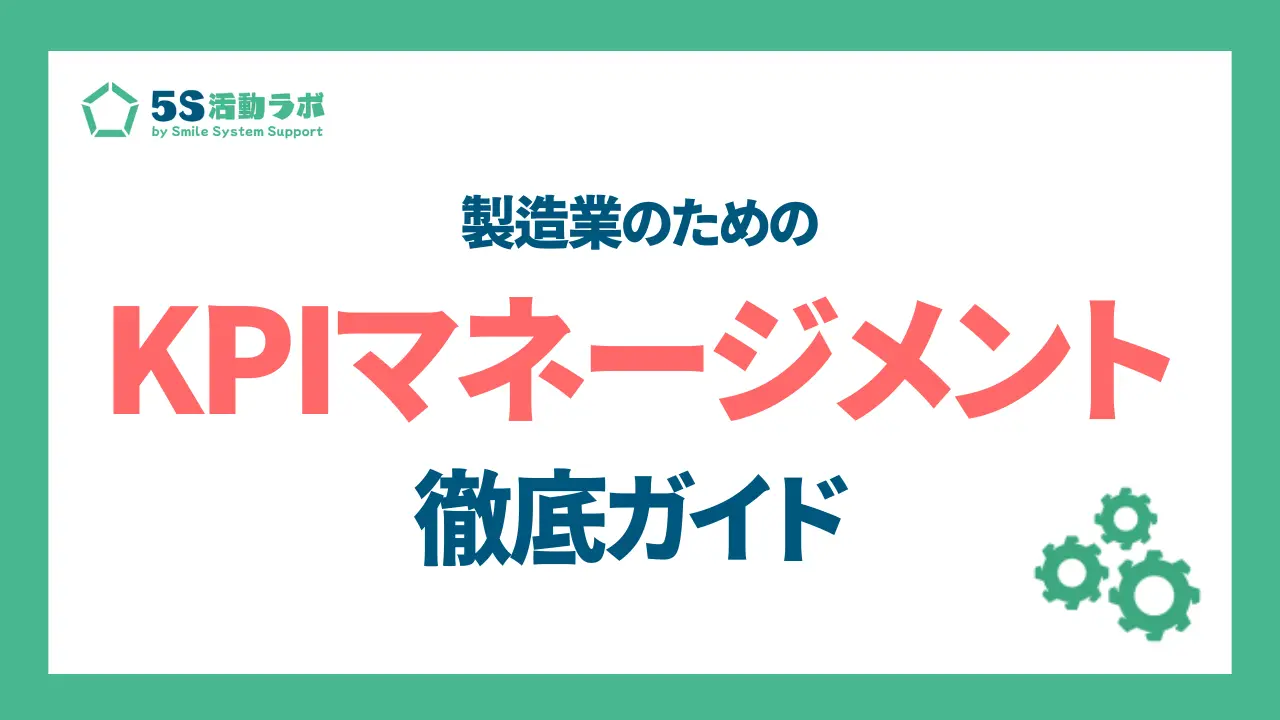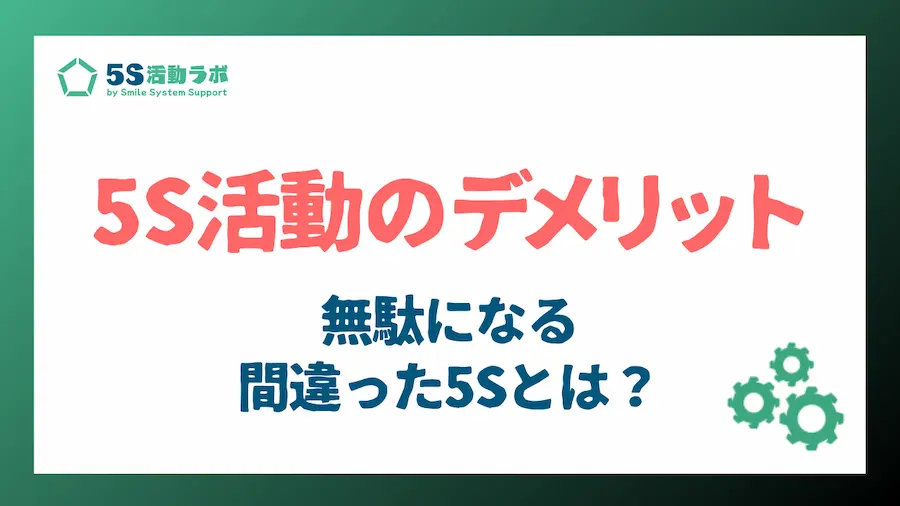
日本の製造業では「5Sは当たり前」と言われるほど重視されており、取引先の評価基準になることもあります。
実際に「5Sができていない会社とは取引しない」と公言する企業もあるほどです。
そのため、多くの会社が5Sに取り組んでいますが、正しく理解せずに表面的に進めてしまうと、かえって非効率化や不満を招くなどのデメリットにつながる場合があります。
「5Sは本当に効果があるの?」「逆効果になることもあるの?」と疑問を持つ方も少なくありません。
この記事では、5Sの代表的なデメリットと、それを避けるためのポイントを整理します。
正しく理解して取り組めば、5Sは企業に大きなメリットをもたらす活動となります。
間違った5Sが引き起こすデメリット
5Sは「整理・整頓・清掃・清潔・躾」の取り組みであり、本来は効率化・安全・快適な職場づくりを目的としています。
しかし、意味や目的を正しく理解せずに取り組むと、かえって以下のようなデメリットにつながることがあります。
1. 非効率化
表面的に「きれいに並べる」ことばかりに囚われると、本来の目的である効率が失われてしまいます。
例えば、全部をしまい込んだ結果、必要なものを取り出せず探す時間が増えるなど、仕事がしづらくなるケースです。
また、一部の人だけに都合の良いルールを押し付けると、別の人にとっては逆に効率を下げることにもなります。
2. やらされ感による形骸化
「躾」を「部下をしつける」と誤解し、強制的にやらせると、社員は納得感を持てず「なぜやるのか分からない」と不満が募ります。
その結果、5Sは自主性を育む活動ではなく、嫌々続ける形式的な活動になりがちです。
3. 時間とコストがかかる
活動の初期には教育や会議に時間を割き、整理や整頓のために収納什器やラベルなどの備品費用も発生します。
短期的には「余計な手間やコストが増えた」と感じる場面もあります。
4. 効果が出るまで時間がかかる
5Sは「漢方薬」とも例えられるように、即効性はなく、習慣化して初めて効果が現れます。
半年から数年単位での継続が必要なため、途中で「意味がない」と感じて挫折してしまうケースもあります。
5. 現場の反発や負担感
忙しい日常業務に加えて「掃除の時間を必ず取れ」と言われると、社員にとっては負担増に感じられやすくなります。
特にトップダウンで一方的に進めると、現場からの反発を招き、活動が長続きしません。
6. 形式化・形骸化のリスク
見た目を整える「整列」で止まってしまい、本来の「整頓=誰でもすぐ取り出せる状態」には至らないことがあります。
また「やっている感」だけが残り、成果につながらない形骸化した活動になってしまう危険もあります。
デメリットを防ぐためのポイント
ここまで挙げたように、5Sは誤解ややり方の間違いで大きなデメリットを招くことがあります。
しかし、正しい進め方を理解すれば、それらを防ぎメリットへと変えていくことが可能です。以下に代表的なポイントを整理します。
目的を明確にする
「なぜ5Sをやるのか」を経営層と現場が共有することが第一歩です。
単なる片付けではなく、安全・効率・快適な職場づくりが目的であることを繰り返し伝えましょう。
ボトムアップで進める
トップダウンの強制では「やらされ感」が残ります。
小集団活動や現場の意見を取り入れてルールを作り、社員が自分たちで考えて動ける仕組みにすることが継続の鍵です。
仕組み化と見える化を徹底する
「人を責めるな、仕組みを責めろ」という考え方が重要です。
チェックリスト、発注カード、標示や色分けなど、誰でも守れる仕組みを整えることで形骸化を防ぎます。
小さな成功体験を積み重ねる
いきなり大きな変化を目指すのではなく、身近な改善で成果を実感できるようにすることが大切です。
社員が「やってよかった」と思える経験を重ねることで前向きな活動に育ちます。
継続と習慣化を意識する
5Sは即効性のある活動ではなく、漢方薬のように続けてこそ効果が出ます。
毎日の短い清掃や定期的な振り返りを組み込み、活動を自然に定着させましょう。
まとめ
5Sは本来、安全で効率的な職場をつくり、社員の自主性やチームワークを育てる強力な活動です。しかし、目的を理解しないまま表面的に取り組むと、非効率化や反発、形骸化といったデメリットにつながりかねません。そのような5Sなら、最初からやらない方がいいとすら言えるでしょう。
だからこそ大切なのは、デメリットを正しく理解し、避ける工夫をすることです。目的を明確にし、現場の声を反映させ、仕組みとして定着させれば、5Sは必ず大きな成果をもたらします。
もしこれから5Sに取り組むなら、単なる整理整頓ではなく「企業文化を変える活動」として位置づけてください。正しい進め方で継続すれば、5Sは安全・効率・快適な職場、そして強い組織風土をもたらしてくれるはずです。