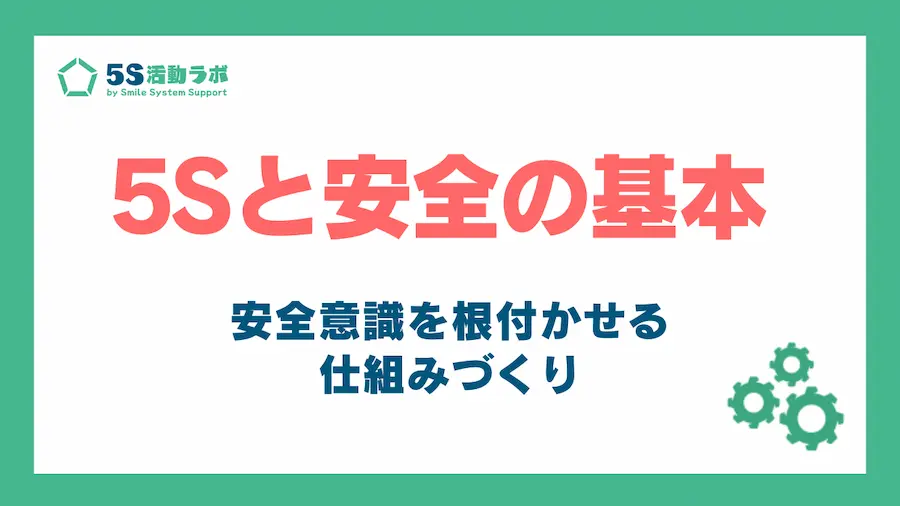
製造業の現場では「安全第一」と言われながらも、転倒や挟まれといった労災は繰り返されています。なぜ安全意識は根づかないのでしょうか。
答えのひとつは5S(整理・整頓・清掃・清潔・しつけ)にあります。5S活動は単なる片づけ活動ではなく、労働安全を守るための安全対策の基本です。
本記事では「5Sと安全の関係」「労災がなくならない本質的な理由」「安全文化を根づかせるための仕組みづくり」について解説します。
管理職や現場リーダーの方が、安全性を高めながら事故ゼロを目指すための実践ポイントをまとめました。
もくじ
5Sと安全の関係とは?
なぜ5Sは「安全の基本」と言われるのか
5S(整理・整頓・清掃・清潔・しつけ)は、安全対策の基本対策です。
通路に物がなければ転倒は防げ、工具や部品が整頓されていれば誤操作や取り違えも防げます。清掃を徹底すれば油漏れや異常の早期発見につながり、重大事故を未然に防ぐことができます。
労災の多くは整理・整頓・清掃不足が直接原因
厚生労働省の統計によると、製造業で多い労働災害は「転倒」「無理な動作」「墜落・転落」「はさまれ・巻き込まれ」です。
その多くは通路をふさぐ直置き、整理不足、清掃不徹底といった5Sの欠如が直接原因です。
つまり、5Sは見た目を整える活動ではなく、労災リスクを減らす労働安全の実践策であり、現場の安全性を維持する基本対策なのです。
製造業で労災が繰り返されるのはなぜか?
しかし、5S活動が重要だと分かっていても、現場ではなかなか徹底できていないのが実情です。
その本質的な原因は、整理整頓や清掃そのものが足りないことではなく、「ルールを守らなくても許される風土」にあります。
例えば、通路に材料を直置きする、工具を定位置に戻さないといった行為は、単なるミスではなく「少しくらい大丈夫」という風土の表れです。さらに、ベテラン社員ほどルールを省略しがちで、その姿を新人が見習い、現場全体が「形だけのルール」に陥ってしまいます。
だからこそ事故は繰り返され、注意や掛け声では改善しません。
労災を減らすために本当に必要なのは、環境整備だけでなく「ルールを守ることが当たり前になる風土づくり」です。
なぜ安全意識が根付かないのか?
トップダウン指示では安全意識は根付かない
「安全第一!」「気をつけろ!」といった掛け声や、一方的な安全教育だけでは現場は変わりません。社員は受け身になり、やらされ感が残り、最初は従っても次第に形骸化してしまいます。
また、「なぜ危険なのか」「何が起こるのか」という理由が共有されなければ、ルールはただの禁止事項になり納得感がありません。人は長時間の作業や慣れの中で必ず気を抜く瞬間があるため、掛け声や注意だけでは不十分です。
だからこそ、安全意識を根づかせるには、指示や注意ではなく仕組みで支えることが欠かせないのです。
小さなヒヤリハットを放置する“運が良かった”文化
「さっき危なかったけど大丈夫だった」というヒヤリハットは、報告されずに流されることが多いのが現実です。
小さな怪我や違反を「運が良かった」で済ませる空気が広がると、改善の機会が失われ、やがて重大事故につながります。
つまり、安全意識が根付かない背景には、見て見ぬふり・言えない空気・仕組みの欠如があるのです。
5S活動で安全意識はどう育つのか?
整理・整頓は安全で快適な職場をつくる基本
整理と整頓は、製造業における労災防止の基本です。
整理はいらないものを処分し、必要なものだけを残すことです。不用品を放置すると通路をふさぎ、つまずきや転倒の原因になります。直置きをなくすことが、安全の第一歩です。
整頓は必要なものを誰でもすぐ取り出せる状態に整えることです。工具や部品を定位置に置くことで、探す手間がなくなり、作業がスムーズになります。それにより余計な負担が減り、集中力が途切れにくくなるため、誤操作や不注意を防ぐ効果があります。
整理整頓は単に片づけではなく、安全で快適に働ける空間をつくる活動です。これが転倒や誤操作を未然に防ぎ、事故ゼロにつながります。
清掃は異常を発見する点検活動
清掃は、衛生的な清潔さを保つことだけでなく、異常を発見するための点検活動でもあります。
油漏れや摩耗、ネジの緩みといった危険の兆候は清掃の中で見つかります。清掃を徹底することで、機械の故障や重大事故を未然に防ぎ、現場の安全性を大きく高めることができます。
5Sが“違和感に気づく力”を育てる
整理・整頓・清掃を習慣化すると、社員はいつもと違う状態に敏感になります。
私たちはこれを「気づく力がついた状態」と言っています。
「通路が狭くて危ないかも知れない」「音が変わった」「油染みが広がっている」など、わずかな異変に気づけるようになるのです。
この違和感に気づく力こそが、安全意識の土台となり、5Sが単なる片付けではなく安全文化をつくる活動である理由です。
なぜボトムアップ型の5S活動が安全風土を変えるのか?
指示よりも“自分ごと”で動ける仕組みが必要
結論から言えば、安全意識を根づかせるにはトップダウンの指示では不十分です。
現場の社員が自分で気づき、改善を考え、実行するボトムアップ型の5S活動こそが、継続的に安全風土をつくる仕組みになります。
小集団活動で気づきを共有する
ボトムアップ型5Sの基本は、4〜6人の小さなチーム活動です。
小集団だと全員が関われ、話しやすい空気が生まれます。
これを継続することで、「言ってもいい」「直してもいい」という空気と「守り合う関係」が育っていきます。
月1回の振り返りが風土を定着させる
改善は一度で終わらせず、月1回の振り返りを習慣化することが重要です。
「何に気づいたか」「どんな改善を実行したか」を確認することで、学びが積み重なり、現場は少しずつ変化します。
このPDCAサイクルの繰り返しにより、安全を“考える習慣”が職場に根づいていきます。
👉 5S振り返りのやり方|毎月の報告書とKPTで改善を定着させる方法
ボトムアップ導入のBefore→After
実際にボトムアップ型5Sを導入した現場では、次のような変化が起きます。
Before
- 整理整頓はしているが、安全意識は低い
- ヒヤリハットが日常的に発生する
- 報告や相談が少なく、改善は一時的
After
- 自分たちで危険箇所を点検するようになる
- 小さな違和感でもすぐに共有・改善される
- 改善提案が自然に出てくる
- 「安全は大事」が共通認識として定着する
このように、ボトムアップ型5Sは仕組みと空気を変えることで、自然に人が動き出す現場を実現します。
安全意識を定着させるには何をすべきか?
5S視点でのパトロールが労災を防ぐ
安全パトロールは5Sの視点で行うことが効果的です。
「通路はふさがれていないか」「工具は定位置に戻っているか」「床は清掃されているか」を点検し、話し合って、改善策を考えることで、安全対策が日常業務に組み込まれます。
重要なのは、社員全員が参加することです。管理職だけが点検するのではなく、全員が点検の視点を持つことで「危険に気づく力」が育ちます。全員で見て、全員で直す。その繰り返しが、安全文化の定着につながります。
標語やスローガンは目的意識を持って
安全意識を浸透させるには、まず全員で「なぜ安全が必要なのか」という目的意識を共有することが出発点です。
そのうえで、自分たちで考えた標語やスローガンを掲げると、社員にとっての安全の合言葉になります。
例えば「整理は安全の第一歩」「通路は命の道」といった短い言葉も、外から与えられたものではなく、自分たちで話し合って決めたものであれば、現場の納得感と主体性が生まれます。
このプロセスこそが、やらされ感ではなく主体的な安全文化を育てるのです。
現場事例を共有して実感を高める
安全意識は知識ではなく実感から育つものです。
例えば「通路に置かれていた部材を定位置化した結果、転倒リスクがゼロになった」といったBefore→Afterの事例を、活動報告書として共有すると、「自分たちの行動で安全が変わる」という実感が広がります。
小さな改善事例を積み重ねることで、現場全体の安全意識が確実に高まります。
5Sと安全に関するよくある誤解とは?
「5Sはもうやっている=安全対策は不要」という誤解
結論から言えば、整理整頓だけでは労災は防げません。
多くの現場が「5S活動はやっている」と言いますが、その実態は見た目を整えるレベルで止まっています。
本来の5Sは違和感に気づく力を育て、安全文化をつくる仕組みであり、片付けや清掃だけでは安全対策にならないのです。
「うちの現場にはムリ」という思い込み
「人が多すぎて徹底できない」「少人数で忙しい」という理由で5Sを諦める現場もあります。
しかし、5S活動は小さく始めるほど効果が出やすい活動です。4〜6人の小集団で気づきを共有するだけでも改善は回り始め、安全意識は自然に浸透します。
「忙しくて時間がない」→実は時間を生み出す投資
5Sは時間を奪う活動ではなく、むしろ時間を生み出す投資です。
整理整頓が徹底されれば探す時間ややり直しの時間が減り、清掃で異常を早期に発見すれば事故対応のロスもなくなります。
結果的に、生産性を高めつつ労災リスクを下げることができるのです。
FAQ|5Sと安全に関するよくある質問
Q. 5Sと安全にはどんな関係がありますか?
5S(整理・整頓・清掃・清潔・しつけ)は、労災を防ぐための土台です。通路の確保や定位置管理、清掃による異常発見が、転倒・挟まれ・墜落といった事故を未然に防ぎます。
Q. なぜ「5Sは安全の基本」と言われるのですか?
5S活動を徹底することで「危険要因をつくらない環境」が整います。安全靴や保護具だけでは防げない事故も、5Sで環境を整えることで予防できます。
Q. 労災の多くは5Sで防げるのですか?
はい。厚生労働省の統計でも、転倒・墜落・はさまれ事故の多くは整理・整頓・清掃の不足が原因とされています。5Sは労災対策の第一歩です。
Q. 5Sで地震対策もできるのですか?
はい、できます。5Sは単なる片付け活動ではなく、安全・効率・快適な職場をつくるための仕組みです。例えば「棚の天板に物を置かない」「直置きをしない」「避難経路を常に開けておく」といったルールは、普段の5Sと同時に災害時の安全確保に直結します。つまり、5Sを徹底すること自体が地震対策の一部になるのです。
👉 5Sでできる地震対策|地震に強い職場をつくる7つのチェック項目
Q. 5S活動をしていても事故が減らないのはなぜですか?
多くの場合、5Sが「片づけ指示」で終わっており、仕組み化や習慣化がされていません。やらされ感の活動では、安全意識が根づかず事故は減りません。
Q. 注意喚起しても社員がルールを守らないのはなぜですか?
「なぜ守る必要があるのか」が伝わっていないことが多いです。理由を共有せず「気をつけろ」と言うだけでは、ルールは形骸化しやすくなります。
Q. 社員が安全ルールを守らない場合、どうすればいいですか?
個人を叱責するのではなく、仕組みで支えることが大切です。定位置管理やチェックリストなどの仕掛けを作り、誰でも守れる環境を整えることが効果的です。
Q. 「ヒヤリハット」を報告させる仕組みはどう作ればよいですか?
仕組みと風土の両方が必要です。カードやボードで簡単に書ける仕掛けを整えると同時に、「指摘しても責められない」空気を育てることが大切です。小さな気づきを歓迎する文化があってこそ、報告は続きます。
参考資料
5Sと安全の関係まとめ
5Sは安全を当たり前にする文化を育てる仕組みです。整理・整頓・清掃を徹底することで転倒・挟まれ・墜落といった労災を防ぎ、現場に「違和感に気づく力」を根づかせます。
管理職は「人を責めるな、仕組みを責めろ」の姿勢で仕組みづくりをリードすることが重要です。その積み重ねが労災ゼロを目指す安全文化につながります。

