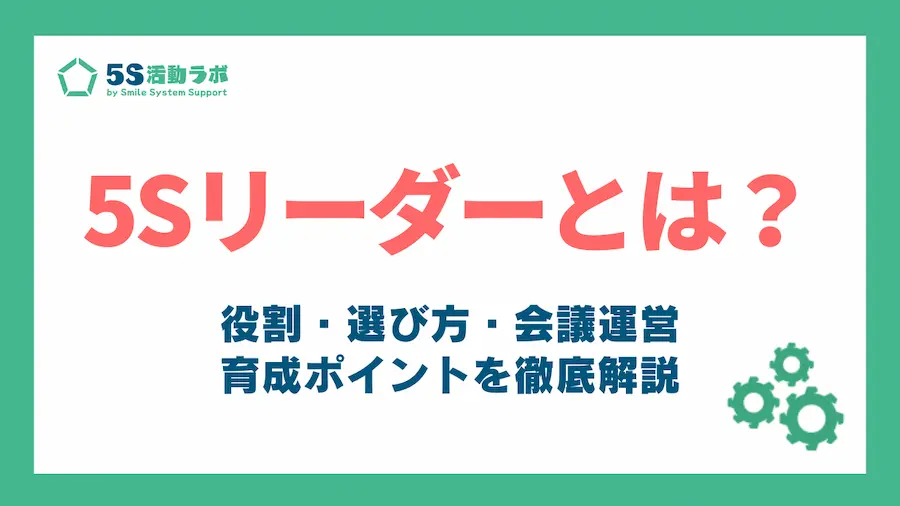
5S活動を進めるうえで欠かせないのが「5Sリーダー」の存在です。現場にルールを押し付ける役ではなく、仲間の意見を引き出し、改善の輪を広げる促進者としての役割が求められます。
しかし実際には「誰に任せればよいのか」「リーダーは何をすればよいのか」が曖昧なまま任命され、活動が形骸化してしまうケースも少なくありません。
この記事では、5Sリーダーの役割や選び方、会議の進め方、現場を巻き込む方法までを整理し、リーダーが活動を成功に導くための実践ポイントを解説します。
これからリーダーに任命された方はもちろん、支える立場にある上司や経営者にとっても役立つ内容です。
もくじ
5Sリーダーの役割
5Sリーダーとは?定義と役割の本質
5Sリーダーは、現場の改善を「指示する人」ではなく、仲間の自主性を引き出し活動を進める促進者(ファシリテーター)です。整理・整頓・清掃の状態を自分で点検する役目よりも、メンバー全員で「どうすればもっと働きやすくなるか」を話し合える場をつくり、意見を引き出し、次の一歩を決める役割に重きがあります。
トップダウン型との違い|ボトムアップ型が成果を生む理由
トップダウン型では「上からの指示だから仕方なくやる」という“やらされ感”が強くなり、活動が形骸化しがちです。一方で、リーダーがファシリテートするボトムアップ型は、社員が自分たちで問題を発見し、解決策を考えて実行する流れをつくります。これにより主体性や考える力が育ち、活動が長続きし、組織全体の風土改革につながります。
👉 なぜボトムアップ式5Sが組織を変える?成功のポイントと継続の仕組みを解説
5Sリーダーが育てるリーダーシップと人材育成効果
5Sリーダーは、特に若手に任命することで「小さなリーダーシップ経験の場」となります。会議で意見をまとめる力、チームを動かす力、改善を進める推進力を実地で学ぶことができ、将来の管理職候補を育てる絶好の機会になります。5Sを通じて現場のリーダーシップが層として厚みを増すことは、企業全体の強みとなります。
5Sリーダーの選び方(誰に任せるべきか)
なぜ役職者より若手が適任なのか|登用のメリット
5Sリーダーは「部長や課長」といった役職者が務める必要はありません。むしろ管理職が前に立つと「上からの押し付け」と受け取られ、現場の自主性が損なわれやすくなります。
そこで有効なのが、将来を期待する若手社員をリーダーに任命することです。5S活動は失敗しても大きなリスクが少なく、チャレンジの場として最適。若手にとっては人前で意見をまとめ、周囲を巻き込む経験ができる育成の機会となります。
小集団(4〜6名)ごとの任命と責任範囲の明確化
5S活動は全員参加が理想ですが、大人数では意見が出にくく「ひとごと感」が強くなります。そこで、4〜6名の小集団に分けてリーダーを置くのが効果的です。小人数なら一人ひとりが発言しやすくなり、当事者意識も高まります。
さらに、各グループごとに担当エリアを割り振ることで責任範囲が明確になり、「誰かがやってくれるだろう」という曖昧さをなくせます。廊下や食堂など共有スペースも、必ず担当部署を決めて管理する仕組みが必要です。
上司・管理職の正しい関わり方|後方支援と例外禁止
管理職や経営層の役割は、リーダーに権限を与え、背中を押し、例外を作らないことです。例えば「社長だけは直置きしてよい」という例外を認めてしまえば、一気に活動が崩れます。
上司は口を出しすぎず、リーダーが進めやすい環境を整える「後方支援者」として関わります。社員が出したアイデアを否定せず、まずは「やってみよう」と応援する姿勢が、活動を広げる大きな力となります。
👉 5S活動が失敗する原因は経営者にあった|やらされ感をなくす支援者の役割とは
5Sリーダーに求められる会議運営スキル
全員の意見を引き出すファシリテーション
5S会議の目的は「現場の課題を共有し、次の改善を決めること」です。そのためリーダーには、全員が発言できる場をつくるファシリテーション力が求められます。
「意見はありませんか?」と投げかけても沈黙しがちなので、「〇〇さんはどう思いますか?」と一人ずつ指名するのが効果的です。これにより当事者意識が生まれ、会議が活性化します。
否定せずに聴く|信頼を生む傾聴と受け止め
出てきた意見をすぐに評価・否定するのはNGです。リーダーは否定せずに聴く姿勢を徹底することで、メンバーは安心して意見を出せます。「なるほど、そういう考えもありますね」と受け止め、必要に応じて深掘りの質問を投げかけることで、メンバーの思考を引き出せます。
意見を整理し合意形成につなげるまとめ力
会議では意見が散らばりやすいため、共通点や方向性を整理して合意形成につなげる力が必要です。ホワイトボードや付箋を活用し、「課題」「対策」「担当者」「期限」といった形で見える化するのが有効です。最後に「誰が・いつまでに・何をするか」を必ず決め、会議が次の行動につながるようにします。
👉 5S活動で重要なコミュニケーション|活動継続ための実践ポイント
成功する5Sリーダーの心得と行動指針
心得①:活動は「みんなで」行うこと
5Sは一人で頑張っても続きません。「全員で取り組む」ことを前提にするのがリーダーの最初の心得です。例えば「自分が片づけるから大丈夫」と抱え込んでしまうと、他の人は当事者意識を持たなくなり、結局リーダーが疲弊します。リーダーはあくまで促進役であり、「全員が動く仕組み」を作ることが大切です。
心得②:計画は「みんなで」決めること
5Sの計画はトップやリーダーが一方的に決めるのではなく、現場のメンバーと一緒に作ることが定着の鍵です。自分たちで考え、合意した計画だからこそ実行力が生まれます。たとえば会議で「どの棚から整理を始めるか」「いつまでにどこまで進めるか」を話し合い、納得して決めることで活動が動き出します。
心得③:リーダーが率先して行動する姿勢を示すこと
リーダー自身が整理整頓や清掃に率先して取り組む姿勢を見せることも欠かせません。机の上が散らかったままのリーダーが「片づけよう」と言っても説得力はありません。小さな行動でも「まず自分がやる」姿を示すことで、周囲も自然とついてきます。これは上司・経営者にも共通する原則で、例外を作らない一貫性が現場の信頼につながります。
全員が関わる5S活動にするための仕組みづくり
一人ひとりに役割を与える
5S活動は一部の人任せでは続きません。一人ひとりに必ず役割を分担することが重要です。例えば小集団ごとに担当エリアや当番を決め、「1カ月間まったく関わらなかった人」が出ない仕組みを作ります。これにより全員が主体的に活動に加わる土台ができます。
反対派や消極層への対応
どの職場にも消極的な人はいますが、まずは中立層を巻き込むことが効果的です。小さな改善で探し物が減ったり掃除が楽になった成果を共有し、成果を写真や数字で“見える化”することで自然に流れが生まれます。反対派は無理に説得せず、雰囲気に引き込むのが現実的な方法です。
人を責めるな、仕組みを責めろ
5S活動でよく起こるのが「ルールを守らない人がいる」という悩みです。しかし大切なのは、個人の怠慢を責めるのではなく、守れる仕組みが整っていないことに目を向けることです。
ルールを守りやすい仕組みを整えることで、反対派や消極的な人も自然に参加できるようになり、活動が無理なく定着します。
FAQ: 5Sリーダーに関するよくある質問
Q. 5Sリーダーとは具体的にどんな役割を担う人ですか?
現場の改善を「指示する人」ではなく、仲間の自主性を引き出し活動を促進するファシリテーターです。点検や指示が中心ではなく、みんなで課題を話し合う場をつくり、意見をまとめ、次の一歩を決める役割を担います。
Q. 5Sリーダーは誰に任せればいいですか?
役職者よりも、将来を期待する若手社員に任せるのが理想です。5S活動は失敗しても大きなリスクが少なく、リーダーシップを学ぶ場として最適です。小さな成功体験を積むことで、自信と成長につながります。
Q. 上司や管理職は5Sリーダーとどう関わればよいですか?
口を出しすぎず、背中を押し、例外を作らない立場で支えることが大切です。社員の意見を否定せず「やってみよう」と応援する姿勢を見せることで、リーダーは安心して活動を進められます。
Q. 会議で意見が出ないとき、リーダーはどう進行すればよいですか?
「意見はありませんか?」と聞くのではなく「〇〇さんはどう思いますか?」と一人ずつ指名することで発言が生まれます。否定せず受け止め、ホワイトボードや付箋で意見を整理し、行動につなげるのが効果的です。
Q. メンバーが5Sに無関心な場合、リーダーはどう巻き込めばよいですか?
まずは小さな改善で成果を実感させることがポイントです。探し物が減った、掃除が楽になったといった即効の変化を共有し、写真や数値で“見える化”すれば、自然と関心が高まります。
Q. 反対する社員やベテランを動かすコツはありますか?
無理に説得するより、雰囲気に巻き込むのが効果的です。中立層を動かして活動の流れをつくることが先決です。改善の成果が見えれば、反対派も少しずつ関わらざるを得なくなります。
Q. リーダーが抱え込みすぎて疲弊しないための工夫は?
「自分がやらなければ」と思わず、一人ひとりに役割を分担し、必ず全員が活動に関わる仕組みをつくることです。リーダーは進行役に徹し、実務を抱え込まないことが継続の鍵となります。
まとめ
5Sリーダーは、現場を仕切るのではなく自主性を引き出す促進者です。若手に任せて育成の場とし、一人ひとりに役割を分担して全員参加を徹底することが成功の鍵となります。
リーダーは抱え込まず、会議で意見を引き出し、成果を見える化して共有する役目に集中しましょう。小さな改善を積み重ねることで雰囲気が変わり、やらされ感がなくなり、自発的に動く風土が育ちます。
まずは「小集団リーダーの任命」「全員への役割分担」「成果の共有」の3つから始めてみてください。

