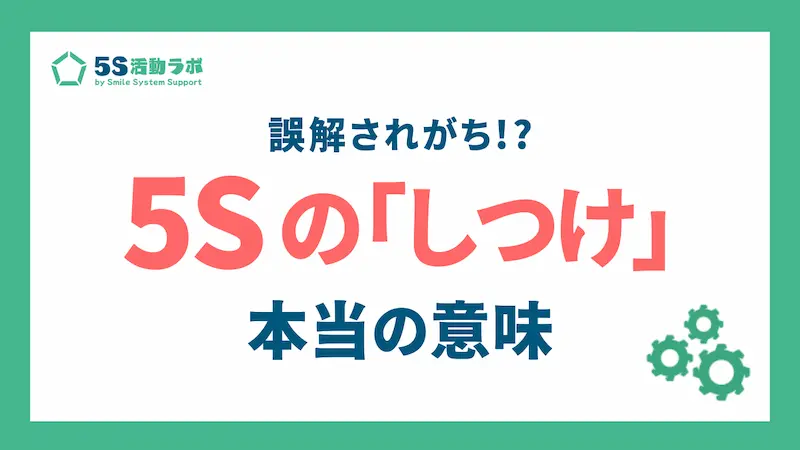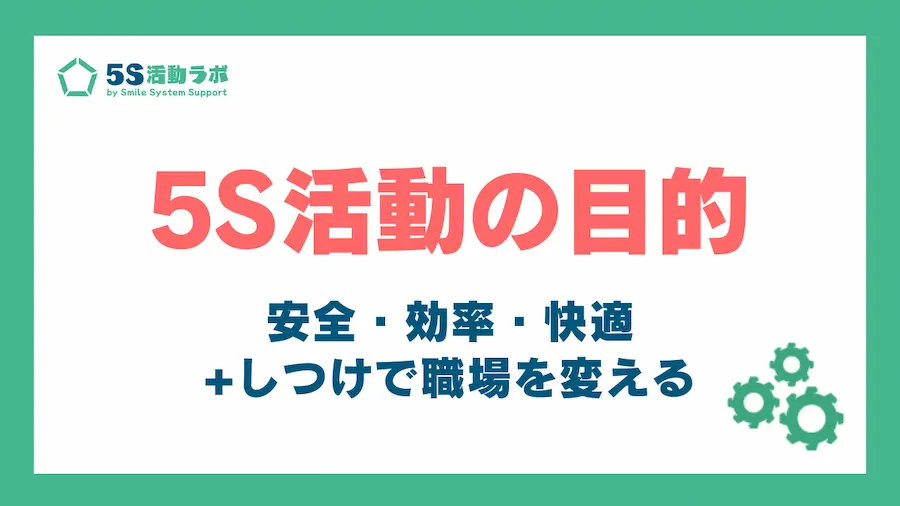
5Sとは、整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字を取った、職場改善の基本活動です。5Sとは何か?はこちらの記事で解説しています。
本記事では、その中でも多くの企業が最初に直面する疑問である「5S活動の目的」について解説します。
5S活動の目的は、単なる整理整頓や清掃ではありません。第一に安全を守り、次に効率を高め、そして快適な職場をつくること。
さらに最終的にはルールを自然に守れる風土(躾)を育てることにあります。
もくじ
5Sの目的は「安全・効率・快適」
5S活動の基本的な目的は、次の三つに集約されます。
- 安全: 事故やヒヤリハットを防ぎ、安心して働ける職場をつくる
- 効率: 探すムダや在庫のムダをなくし、生産性を高める
- 快適: 身体的・心理的ストレスを減らし、働きやすい環境を整える
この三つはどれか一つが欠けても成り立たず、互いに補い合って初めて健全な職場環境が実現します。
以下では、それぞれの目的を具体的に解説していきます。
動画でも「5Sの目的」をわかりやすく解説しています。ぜひご覧ください。
安全の確保と安全意識の定着
5S活動の第一の目的は安全性の向上です。事故や怪我を防ぎ、誰もが安心して働ける職場をつくることが基本になります。
現場で最も多い労災事故は「つまずき」だと言われています。
工具や部品の直置きが原因となることが多く、「これくらい大丈夫」という気の緩みから事故は起こります。
整理で不要なものを徹底的に処分し、整頓でモノの定位置を決めることによって、想定外の場所にモノがある状況をなくすことができます。
また、清掃を徹底して床や機械をピカピカに保つことで、油汚れによる転倒を防ぐだけでなく、設備の異常や不具合を早期に発見することができます。
そして忘れてはならないのが、5S活動の本質は「ルールを決めて守ること」にあるという点です。
区画線を越えない、軍手を外して操作しない、ヘルメットのあごひもを締める――
こうした細かなルールを全員で守ることが、ヒヤリハットを減らし、事故を未然に防ぐ最大の仕組みになります。
業務効率化
5S活動の二つ目の目的は業務の効率化です。
整理・整頓・清掃を徹底することで、探すムダ・待つムダ・やり直しのムダなど、7つのムダをなくし、生産性を高めます。
たとえば「整理」で不要な物を処分すると、倉庫や作業場には「本当に使うもの」だけが残ります。
必要なものだけに絞り込むことで、探す時間が大幅に減り、動作がスムーズになります。
さらに「整頓」では、必要な物を誰でもすぐに取り出せる状態に整えます。
- 定位置:誰が見てもわかる置き場所を決める
- 定量:必要な量だけを置き、過不足を防ぐ
- 標示:見える化によって在庫やツールの状態を一目で把握
この3つを徹底するだけで、在庫の過不足や道具の行方不明といった非効率は一掃されます。
そして、「清掃」を通じて設備や職場をきれいに保てば、異常の早期発見や故障の防止にもつながります。
これにより設備トラブルで作業が止まるリスクも軽減されます。
快適性の向上
5S活動の三つ目の目的は快適な職場環境をつくることです。
安全で効率的であるだけでなく、働く人が気持ちよく業務に取り組める環境を整えることが欠かせません。
たとえば、机や作業台の上に不要な物が散乱していると、それだけで視覚的なストレスが生まれます。
整理整頓でスッキリとした環境を保てば、心理的な負担が減り、集中力も高まります。
また、無理な姿勢で作業を続けていると、腰痛や肩こりなど身体的な不調につながります。
工具や部品を取りやすい位置に整頓することで、自然と作業姿勢が改善され、身体への負担も軽減されます。
さらに、清掃を通じて温度・湿度や照明といった職場環境を整えることも大切です。
空調や換気を点検する、照明の明るさを適正にする、といった小さな工夫が快適さを大きく左右します。
5S活動から得られるその他の効果
5Sの核となる目的は「安全・効率・快適」ですが、実際に活動を進めることで、それ以外にも多くの効果が表れます。
これらは副次的な成果ですが、企業の成長にとって大きな意味を持ちます。
品質向上
整理整頓によって不要なモノや不適切な在庫を排除すると、作業環境が安定します。さらに清掃を徹底することで設備の異常を早期に発見でき、不良品の発生を抑えられます。その結果、製品やサービスの品質が向上します。
コスト削減
探すムダや過剰在庫、やり直しといった非効率を排除することで、無駄な作業時間や材料費が減少します。これにより、コスト削減や利益率の改善につながります。
従業員の意識改革
5Sを通じて小さなルールを守る習慣が根づくと、従業員は自律的に行動できるようになります。責任感や規律性が高まり、主体的に改善に取り組む文化が育ちます。
企業イメージの向上
整理整頓された職場は、従業員だけでなく、取引先や顧客に対しても好印象を与えます。清潔で秩序ある環境は信頼感を高め、企業イメージの向上につながります。
5S活動の本当の目的は「躾=風土づくり」
安全・効率・快適という三つの目的を達成することは重要ですが、5S活動の最終的なゴールはそこにとどまりません。
根底にある本当の目的は、決めたルールを全員が当たり前に守れる風土をつくることにあります。
5Sのステップは、整理・整頓・清掃を徹底する3Sから始まり、標準化によって「清潔」を保つ仕組みへと発展します。
そして最終段階が「躾」です。
これは、誰かが監視しているから守るのではなく、自然にルールが守られる状態を指します。
たとえば、安全のために設けられた区画線や保護具の着用ルールも、単に事故防止にとどまりません。
日々こうした細かなルールを自然に守れるようになることが、職場全体に「約束を守る文化」を育てます。
小さなルールの積み重ねが、やがて大きな信頼と安心を生む風土に変わっていくのです。
また、エラーやミスが起きたときに「人を責める」のではなく「仕組みを改善する」という姿勢を持つことも重要です。
システムに手を入れることで同じミスを防ぐことができ、現場はより働きやすく進化していきます。
こちらもCHECK
-

5Sの「躾」に違和感?誤解されがちな「躾」の本当の意味とは
5S活動は「整理・整頓・清掃・清潔・躾」の5つのステップで構成されます。 その中で最後の「躾(しつけ)」は、言葉の響きから誤解されやすい要素です。 「しつけ」と聞くと、子どもや部下に厳し ...
続きを見る
あなたの職場に合った5Sの目的を明確にしよう
5S活動の目的は「安全・効率・快適」そして「躾=風土づくり」にありますが、どのポイントを優先するかは職場ごとに異なります。
だからこそ、自分たちの職場では何を大切にするのかを明確にすることが大切です。
たとえば「不良率を下げたい」「残業を減らしたい」「離職率を改善したい」といったように、自社の課題をもとに目的を定めましょう。
その上で「不良率を30%減らす」「残業時間を月10時間以内にする」など、数値化した目標に落とし込むと実現度が高まります。
目的と目標が決まったら、社内で共有しスローガンとして掲げることも効果的です。
「私たちは〇〇を実現するために5Sを進める」と明文化することで、活動に一体感が生まれ、継続しやすくなります。
まとめ:5Sの目的を明確にして、職場を変えていこう
5S活動の目的は単なる片づけや清掃ではありません。第一に安全を守り、次に効率を高め、そして快適な職場をつくること。
さらに最終的にはルールを当たり前に守れる風土(躾)を育てることにあります。
そのうえで、5Sに取り組む際には自分たちの職場に合った目的を明確にし、全員で共有することが大切です。
目的がはっきりすれば、5S活動は単なる作業ではなく、未来の職場をつくるための力強い取り組みに変わります。