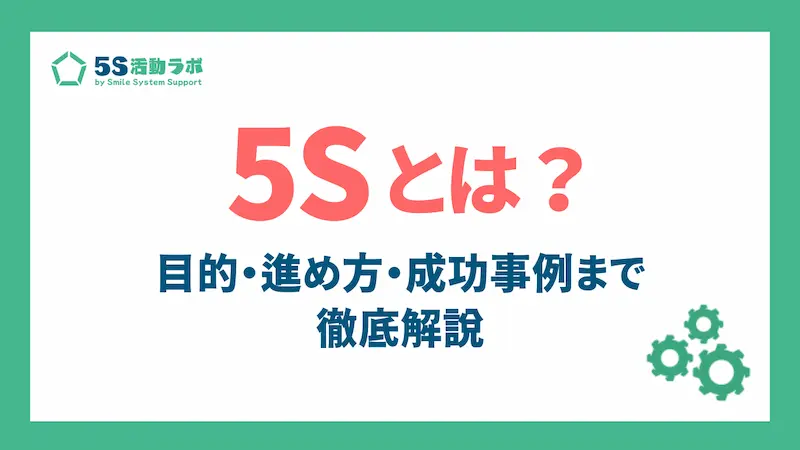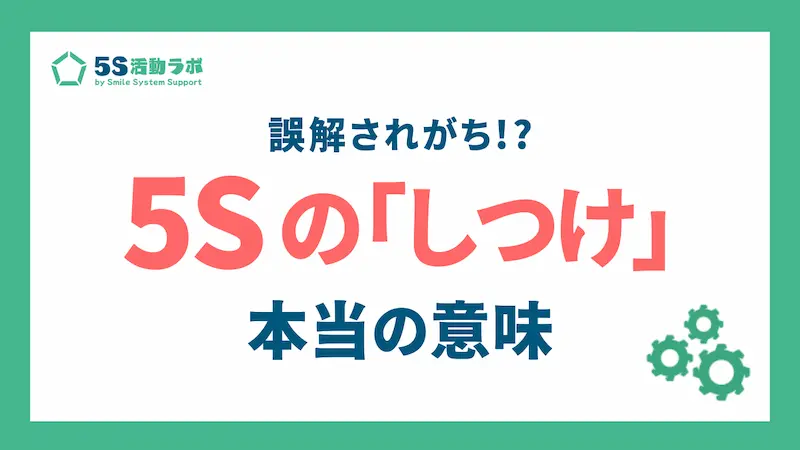
5S活動は「整理・整頓・清掃・清潔・躾」の5つのステップで構成されます。
その中で最後の「躾(しつけ)」は、言葉の響きから誤解されやすい要素です。
「しつけ」と聞くと、子どもや部下に厳しくルールを守らせるようなニュアンスを思い浮かべる人も多いでしょう。
そのため「5Sの躾」という言葉に、少し違和感を覚える方も少なくありません。
本記事では、その誤解を解き、「躾」が本来意味するものを整理しながら解説していきます。
5S活動全体について知りたい方はこちら
5S活動における「躾(しつけ)」の本当の意味とは
5S各要素の意味
まずは5Sそれぞれの意味を簡単に振り返っておきましょう。
- 整理(seiri)
要るモノと、要らないモノを分類し、要らないものを捨てること - 整頓(seiton)
要るモノを、誰にでも、すぐに取り出せるようにすること - 清掃(seisou)
ゴミや汚れがない綺麗な状態を維持すること - 清潔(seiketsu)
3S(整理・整頓・整頓)が維持されている状態 - 躾(shitsuke)
3Sが定着し、決められたことを守れる風土になっている状態
5Sは順序を追って進めるだけでなく、それぞれが連動して効果を発揮します。
特に最後の「躾」は、3Sと清潔がきちんと定着してこそ意味を持つ段階です。
こちらもCHECK
-

5Sとは?職場改善の基本を徹底解説!目的・進め方・成功事例をわかりやすく紹介
はじめに:トヨタ発祥の「5S活動」で職場を変える 現代の企業や組織が抱える課題には、業務効率の低下や安全性の欠如、社員育成や社内コミュニケーションの問題など様々です。これらを解決するための強力なアプロ ...
続きを見る
5Sの「しつけ」に対する誤解
「躾(しつけ)」と聞くと、多くの人がまず思い浮かべるのは“厳しくルールを守らせる”というイメージではないでしょうか。
子どもやペットに対する「しつけ」と同じ言葉であるため、5Sの躾にも同じ感覚を重ねてしまい、違和感を覚える方も少なくありません。
その結果、「上司が部下に独自ルールを押し付ける」「サービス残業を強いる」など、本来とはかけ離れた形で“躾”が使われてしまうケースも見受けられます。
しかし、5S活動における「躾」とはそうした上下関係でルールを守らせることではありません。
本来は、整理・整頓・清掃がきちんと徹底され、社員一人ひとりが自主的に取り組み、それが職場全体の風土として根づいている状態を指します。
つまり「行動を強制すること」ではなく、「当たり前にできている状態」を表す言葉なのです。
英語で言い換えると分かりやすい「躾」
もともと5Sは、5つの言葉をすべて“S”で始める標語として整理された経緯があります。
その中で「躾(しつけ)」という日本語が選ばれたことで、“厳しく守らせる”といったニュアンスが強調され、違和感につながってしまいました。
しかし、英語表記を見ると本来の意味が分かりやすくなります。
- 整理 ⇒ Sort(分類する)
- 整頓 ⇒ Set in order(正しい位置に置く)
- 清掃 ⇒ Shine(輝く)
- 清潔 ⇒ Standardize(標準化)
- 躾 ⇒ Sustain(維持する)
ここで「躾」にあたるのは Sustain(持続する/維持する) です。
つまり、3Sと清潔を一時的に取り組むのではなく、続けて習慣にすることこそが「躾」の本質なのです。
日本語の「しつけ」では誤解されやすい部分も、英語で「Sustain」と言い換えると「続ける・習慣化する」という意味が直感的に理解できます。
この違いを知るだけで、「躾」に対する違和感も解消されるでしょう。
躾の効果:気づく力が育つ
5Sの最後のステップである「躾」が定着すると、職場で大きな変化が生まれます。
それは、社員一人ひとりに “気づく力” が備わることです。
整理・整頓・清掃が当たり前になると、
- 「ここに不要なものが置かれている」
- 「棚の並べ方が使いにくい」
- 「壁が汚れている」
といった 小さな違和感に敏感に気づけるようになります。
この力は、単にモノや環境に対する感覚だけではありません。
問題や異常の兆し、作業のムダ、さらには同僚の表情や気持ちの変化にも気づけるようになり、仕事全体のパフォーマンスが高まります。
実際に、以前はゴミを見ても素通りしていた人が、自然と拾って片付けるようになる。
そんな小さな行動の積み重ねが、「見て見ぬふりをしない」風土をつくり、ミスや事故を未然に防ぐ 安全文化 へとつながっていきます。
FAQ:躾に関するよくある質問
Q1. 5Sの「躾」とは何ですか?
整理・整頓・清掃が習慣化し、社員全員が自然にできている状態を指します。
日本語の「しつけ」と違って、厳しくルールを守らせることではなく、当たり前の習慣として続いている状態です。
Q2. 清潔と躾の違いは?
清潔は「3Sのルールを標準化して維持すること」。
躾は「その状態がさらに習慣として根づき、風土化していること」です。
Q3. 躾の言い換えはありますか?
英語では「Sustain(持続する/習慣化する)」と表されます。
日本語では「習慣化」「風土化」と言い換えると分かりやすいでしょう。
Q4. 躾の目的は何ですか?
正確には「目的」というより「結果」に近い言葉です。
ただし5Sの本来の目的である「安全・品質・効率・人材育成」を実現するために、躾の段階は欠かせません。
Q5. 躾はどうやって進めれば良いですか?
特別な活動をする必要はありません。
整理・整頓・清掃を徹底し、清潔として標準化・維持することを繰り返すことで、自然と習慣化=躾の状態に近づきます。
Q. 5Sが「宗教っぽい」「気持ち悪い」と言われるのはなぜですか?
そう感じられる背景には、5Sが本来の業務目的とは切り離され、形式やスローガンだけが強調されてしまうことがあります。たとえば「5Sさえやっていれば大丈夫」といった言い方や、強制的に従わせるような進め方は、外から見ると信仰的で不自然に映りがちです。
しかし、正しい5Sの目的は「職場を安全、効率的、快適にすること」です。理想的な取り組み方は、押し付けや形式ではなく、現場の人が「自分たちのためにやる」と納得し、自然に続けられる習慣として根付かせることです。
まとめ
5Sの「躾」は、厳しく守らせることではなく、整理・整頓・清掃が自然に習慣化された状態を指します。
英語で言う「Sustain(持続する)」が本来の意味であり、職場に根づけば「気づく力」が育ち、安全・品質を守る風土につながります。
躾は特別な活動ではなく、3Sと清潔を繰り返し続けた結果として訪れるゴールです。