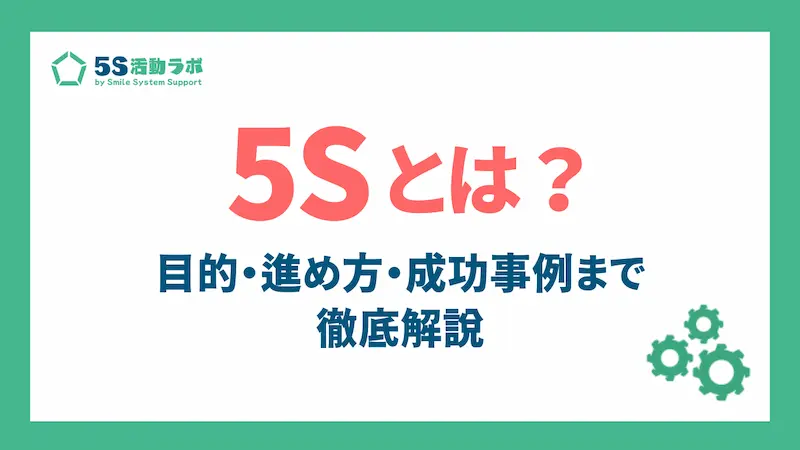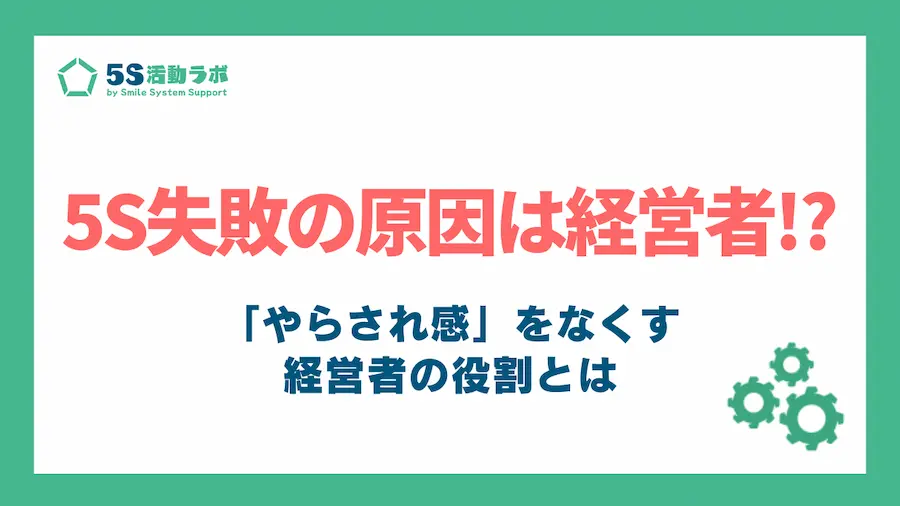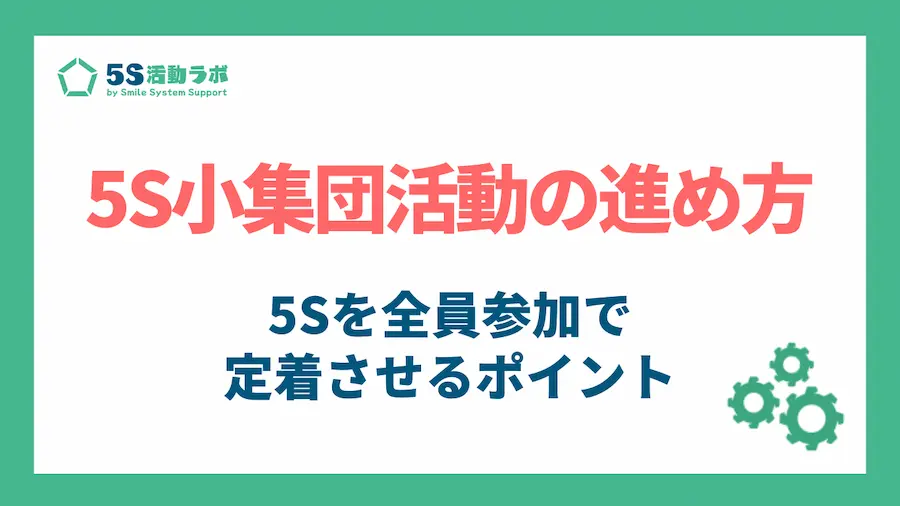
5S活動を導入したものの、実際に取り組んでいるのはリーダーや委員会の一部だけ――そんな状況に心当たりはありませんか。
多くの現場で聞かれる声が「また余計な仕事が増えた」という社員の反発や、当事者意識のない「他人事」スタンスです。その結果、活動は一部の人に負担が集中し、長続きせず、会社全体の文化として定着しないのです。
そこで注目したいのが、全社員を巻き込み、当事者意識を育む方法「小集団活動」です。
この記事では、5S活動を会社全体に広げるための具体的な仕組みとして、小集団活動のメリットと進め方をご紹介します。
もくじ
そもそも5S活動とは?– 目的の再確認
5S活動は「整理・整頓・清掃・清潔・しつけ」の5つを、この順番で進めることが基本です。
目的は掃除や見た目の美化ではなく、「安全」「効率」「快適」な職場を社員自身の手でつくること。その過程で残業削減やコスト削減といった成果が生まれます。
さらに大きな効果は、社員が主体的に意見を出し、改善に動く組織へ変わっていくこと。
5Sは片付けの活動にとどまらず、会社の文化を変える取り組みなのです。だからこそ、一部の人だけではなく、全員で取り組む仕組みづくりが重要です。
5Sとは何か?目的や効果はこちら
-

5Sとは?職場改善の基本を徹底解説!目的・進め方・成功事例をわかりやすく紹介
はじめに:トヨタ発祥の「5S活動」で職場を変える 現代の企業や組織が抱える課題には、業務効率の低下や安全性の欠如、社員育成や社内コミュニケーションの問題など様々です。これらを解決するための強力なアプロ ...
続きを見る
3. なぜ「小集団活動」が5S成功につながる?3つのメリット
5S活動は、リーダーや委員会の一部だけが頑張っても、負担が偏り長続きしません。会社全体に根付かせるには全員参加が不可欠ですが、単に呼びかけるだけでは「誰かがやってくれるだろう」という他人任せの意識が生まれやすくなります。
そこで効果を発揮するのが、4〜6名程度の小集団活動です。少人数だからこそ、一人ひとりが関わりやすく、5Sを文化として定着させる力になります。その理由は次の3つです。
メリット1:当事者意識が芽生える
大人数の会議では「誰かが言ってくれるだろう」と黙ってしまいがちですが、少人数なら意見が出しやすく、自分の声が反映されやすい環境になります。結果として「やらされ感」から解放され、活動を「自分ごと」として捉えるようになります。これは5Sを続ける上で欠かせない参画意識の醸成につながります。
メリット2:コミュニケーションとチームワークが強化される
共通の目標に向かって話し合い、協力して行動する中で、職場の会話が活性化します。他部署と混成チームを組めば、お互いの仕事への理解が深まり、部署を超えた相談や協力もスムーズに。5Sを通じたチーム経験は、日常業務でも成果を出せる強い組織づくりの基盤となります。
メリット3:改善アイデアが生まれやすい
小集団活動では定期的に社内を点検し、自分の部署だけでなく他部署を客観的に観察することで、これまで見過ごしていた課題に気づきやすくなります。こうして鍛えられるのが「気づく力」。この力が育つと、社員一人ひとりから自主的な改善提案が生まれ、活動がどんどん前向きに回り始めます。実際に多くの企業で「社員から自然に意見が出るようになった」という成果が報告されています。
メリット4:チーム同士で切磋琢磨できる
グループごとに特色や進み具合の差が出ると、それが互いの刺激となって活動が活性化します。他チームの成功事例や工夫を取り入れることで、自分たちのアイデアも広がり、改善の質が一段と高まります。
【実践編】5S小集団活動の進め方 4ステップ
ここからは、5Sの小集団活動をスムーズに始めるための4つのステップを紹介します。
ステップ1:グループ分けをする
まずは全社員が必ずいずれかのグループに所属するようにします。バラバラに活動すると「誰かがやるだろう」という他人任せの空気が生まれがちですが、グループに属することで当事者意識が高まります。
- 理想の人数:1グループ4〜6名程度。発言しやすく、意見が活動に反映されやすい規模です。
- メンバー構成の工夫:部署をミックスすると普段関わりの少ない社員同士が協力するきっかけになり、部署間の理解や連携が深まります。
ステップ2:リーダーを選出する
次に各グループのリーダーを決めます。小集団であれば負荷が軽く、リーダー経験の第一歩としても適しています。
- 役職者は避ける:役職者がリーダーだとトップダウンになりやすく、指示待ちの雰囲気が生まれます。
- 若手に任せる:将来を担う若手に任せることで、意見を聞きまとめる経験を積むことができ、次世代リーダーの育成にもつながります。上司は口を出しすぎず、サポート役に徹するのが理想です。
👉 5Sリーダーとは?役割・選び方・会議運営と育成のポイントを徹底解説
ステップ3:目標と計画を立てる
各グループで会議を開き、活動の目標や年間計画を立てます。自分たちで決めた目標だからこそ主体性が生まれます。
- 担当範囲を明確化:どのグループがどの場所を担当するかを決め、責任の所在を明確にします。放置エリアをなくすことがポイントです。
- 具体的な計画に落とし込む:いつ、誰が、どこを、どう改善するかを明確に。曖昧な計画では実行に移されにくくなります。
👉 5S計画表の作り方|目標設定から記録・発表・プレゼン資料まで徹底解説
ステップ4:定期的な会議でPDCAを回す
計画して実行するだけでは継続しません。活動を止めずに成果を出し続けるには、定期的な振り返りが不可欠です。
月1回のグループ会議:活動を振り返り、改善策を話し合います。特に「Check(振り返り)」が重要です。
リーダー会議で共有:グループリーダー同士も月1回集まり、進捗や成功事例を共有します。他のグループの工夫が刺激となり、切磋琢磨する文化が生まれます。
👉 5S振り返りのやり方|毎月の報告書とKPTで改善を定着させる方法
成功の秘訣は「上司の関わり方」!ボトムアップで進める3つの心得
5Sを根付かせるには、上からの指示だけではなく、社員が主体的に動くボトムアップの進め方が欠かせません。そのために重要になるのが、上司の関わり方です。ここではポイントを3つにまとめます。
心得1:「聴く耳」を持つ
現場を一番知っているのは社員です。まずは部下の意見を否定せずに受け止めましょう。「どうせ聞いてもらえない」と感じさせないことが、信頼と前向きな雰囲気をつくります。
心得2:「率先垂範」で行動する
社員が決めたルールは、上司も率先して守ることが大切です。例外を作ると活動は一気に形骸化してしまいます。逆に上司が一緒に行動すれば、部下のモチベーションは自然と高まります。
心得3:「任せる勇気」を持つ
社員に権限を移し、まずはやらせてみること。たとえ失敗しても大きなリスクはなく、そこから学ぶ経験が社員を大きく成長させます。「任されている」という責任感が、自主性を育む原動力になります。
※上司・経営者の関わり方はこちら
-

5S活動が失敗する原因は経営者にあった|やらされ感をなくす支援者の役割とは
あなたの会社の5S活動は、本当に成果につながっていますか? 「社員にやらせているけれど定着しない」「片付けや掃除の一環にしか見えない」――そんな悩みを抱える経営者は少なくありません。実は、5S活動が失 ...
続きを見る
FAQ: 小集団活動に関するよくある質問
Q. 小集団活動の目的は何ですか?
全員参加で5Sを定着させることです。少人数で話し合いながら取り組むことで、当事者意識を持ち、現場の課題に気づき、自主的に改善を進められるようになります。その結果、単なる環境改善にとどまらず、組織文化そのものが前向きに変わっていきます。
Q. 小集団活動の5Sには理想的な人数は?
理想は4〜6名程度です。この規模であれば全員が発言しやすく、意見が反映されやすいのでやりがいを感じやすくなります。人数が多すぎると発言機会が減り、少なすぎると負担が偏るため、適度な人数設定がポイントです。
Q. 活動テーマはどのように選べば良いのでしょうか?
最初は難しいテーマを設定する必要はありません。まずは自分たちでパトロールを行い、「ここが不便」「ここが危ない」といった現場の課題を見つけることから始めましょう。現場に即したテーマの方が成果が出やすく、活動が長続きします。
Q. 小集団活動は意味がないという意見もありますが、本当に効果はある?
単に形だけで進めると効果は出にくいですが、正しく運営すれば大きな効果があります。社員の当事者意識が高まり、チームワークが向上し、改善アイデアが自然に出てくるようになります。実際に導入した企業では「社員が自発的に動くようになった」という声が多く報告されています。
Q. デメリットや注意点はありますか?
活動が形骸化すると「時間のムダ」と捉えられやすい点には注意が必要です。また、テーマが曖昧だったり、上司が口を出しすぎたりすると自主性が失われます。小さな成功体験を積み重ねることと、現場主体で進める姿勢を守ることが大切です。
Q. トヨタ生産方式における小集団活動との関係はありますか?
トヨタではQCサークル活動をはじめ、小集団による改善が生産方式の基盤を支えています。5Sの小集団活動も同じ考え方で、現場の社員が小さな改善を積み重ねることで大きな成果を生み出すという点で共通しています。
Q. 「課題達成型」の小集団活動とはどういうものですか?
課題達成型とは、グループごとにテーマや目標を明確に設定し、期限を決めて解決に取り組む活動スタイルです。「倉庫の整理を1ヶ月で完了させる」など具体的な課題に取り組むことで達成感が得られ、次の活動にもつながります。
Q. QCサークルと5Sの小集団活動はどう違うのですか?
QCサークルは品質管理をテーマに、データ分析や統計手法を用いて不良削減や品質向上を目指す活動です。一方、5Sの小集団活動は、安全で、効率的で、快適な職場づくり を目的としています。整理・整頓・清掃を通じて事故を防ぎ、ムダを減らし、働きやすい環境を整えることに重点を置いています。どちらも小集団で改善を進める点は共通していますが、対象とするテーマや目的が異なります。
まとめ:小集団活動で「やらされ5S」から卒業しよう
5S活動を全社で成功させるには、全員参加を促す仕組みが欠かせません。その有効な方法が小集団活動です。
少人数のグループで進めることで、社員一人ひとりの当事者意識が育ち、チームワークが強化され、現場から改善のアイデアが生まれるようになります。これは単なる環境改善にとどまらず、社員が成長し、組織が強くなるプロセスそのものです。
「また余計な仕事が増える」と感じていた5Sも、小集団活動を通じて「自分たちの会社をより良くする活動」へと変わります。まずは小さなグループをつくり、身近な問題をみんなで話し合うことから始めてみませんか。