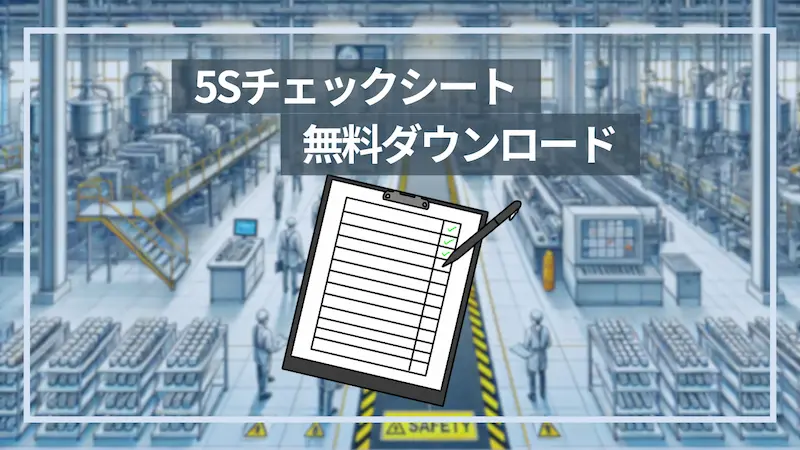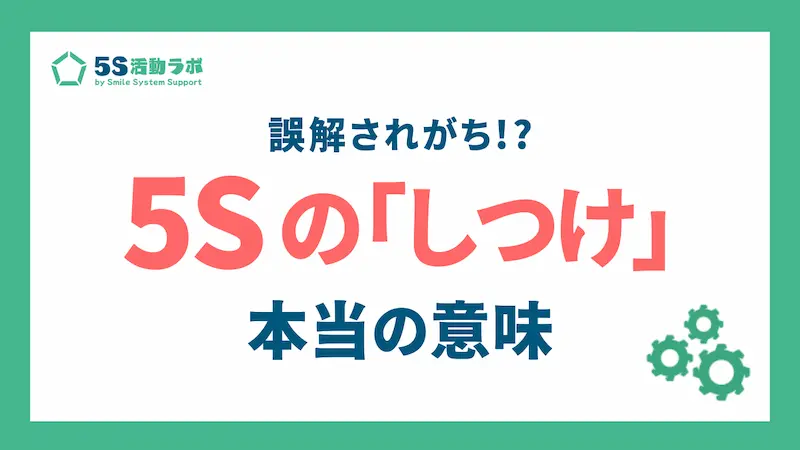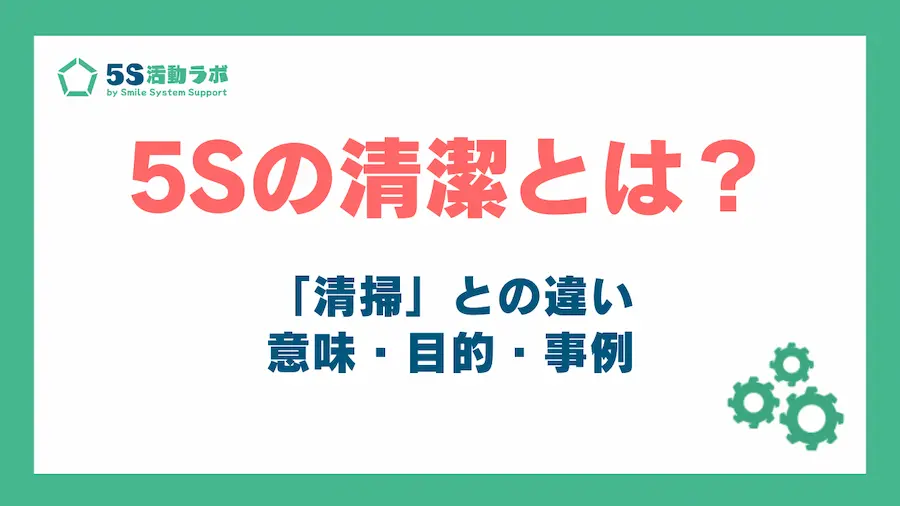
5S活動の中で「清掃」と「清潔」はよく混同されがちです。
しかし、この二つの違いを正しく理解しなければ、せっかくの5Sも形だけで終わってしまい、本来の効果を得ることはできません。
清潔とは、新しい取り組みを増やすことではなく、整理・整頓・清掃で決めたことを標準化・ルール化・仕組み化して、誰がやっても同じ状態を維持できるようにする段階です。
この記事では「清潔とは何か」「清掃や躾との違い」「実際の事例や仕組み」「チェックリストとの関係」まで分かりやすく解説していきます。
👉 5S活動全体について知りたい方はこちら
もくじ
清潔の定義と意味
5S活動は「整理・整頓・清掃・清潔・躾」の5つのステップで構成されています。
その4番目にあたる「清潔」とは、最初の3S(整理・整頓・清掃)をルール化し、標準として維持している状態を指します。
まずは前提となる3Sの意味を簡単に整理しておきましょう。
- 整理(Seiri):要るものと要らないものを区別し、不要なものを徹底的に処分すること
👉 整理とは? - 整頓(Seiton):必要なものを、誰でもすぐに取り出せるようにすること
👉 整頓とは? - 清掃(Seisou):ゴミや汚れがない綺麗な状態を維持すること
👉 清掃とは?
「清潔」の段階では、3Sを単に行うだけでなく、ルール化・標準化を徹底し、継続できる仕組みを作ることが目的になります。
清潔の目的
清潔の目的は、整理・整頓・清掃(3S)を標準化し、誰がやっても同じ水準で維持できる仕組みを作ることにあります。
清潔そのものが新しい活動を意味するのではなく、3Sを「やりっぱなし」で終わらせず、継続できる形に整えることが本質です。
◆ 標準化
整理・整頓・清掃で決めた基準を全員で共有し、誰がやっても同じ結果になる状態にします。
例:赤札の処理基準、整頓の定位置・定量ルール、清掃の基準レベル。
◆ ルールの見える化
標準を日常で守れるよう、運用方法を明文化し、全員に分かりやすく提示する。
例:基準を掲示物・マニュアル・チェック表に落とし込む、清掃担当を見える化する。
◆ 維持の仕組み化
ルールを守ろうと意識しなくても、自然に守れる環境をつくる。
例:
- 工具の形跡管理(戻さないと違和感が出る)
- 掃除道具を汚れやすい場所のすぐ近くに設置(面倒さをゼロにする)
- 消耗品の発注カード方式(なくなった時点で自動的に発注に繋がる)
清潔とは、3Sを“標準化→ルール化→仕組み化”の流れで徹底し、誰がやっても同じ状態を自然に維持できる段階です。
この徹底があって初めて、次のステップ「躾=無意識の習慣化」へ進むことが可能になります。
清潔と「清掃」との違い
清掃と清潔は似ているようで、その役割と目的は異なります。
清掃(Seisou)
職場の汚れや乱れを取り除き、異常を発見しやすい状態に整えること。
→ 事故や品質不良を防ぎ、綺麗で働きやすい環境を維持するのが目的。
清潔(Seiketsu)
整理・整頓・清掃でつくった環境を、標準化・ルール化・仕組み化によって継続的に維持すること。
→ 常に安全・効率・快適な環境を保ち、ムラや後戻りをなくすのが目的。
この違いを理解することが、5Sを単なる美化運動で終わらせず、本来の効果である「働きやすい環境づくり」に結びつけるカギとなります。
清潔と「躾」の違い
清潔と躾はどちらも「継続」に関わる段階ですが、その性質は異なります。
清潔(Seiketsu)
整理・整頓・清掃で整えた環境を、標準化・ルール化・仕組み化によって誰がやっても同じ状態に維持すること。
躾(Shitsuke)
清潔でつくったルールや仕組みが社員の中に浸透し、意識しなくても当たり前に、自然にできるようになった状態。
たとえば、工具の形跡管理によって、誰もが同じ場所に戻せるようにするのが清潔の取り組みです。
それを繰り返すうちに、社員が誰に言われなくても自然に戻すようになったら、それは躾の領域に入ります。
清潔がしっかり徹底されてこそ、自然に躾へとつながっていきます。
清潔の事例
事例①消耗品管理の仕組み化
この事例は、消耗品(除菌ティッシュやハンドソープ)の管理を整頓と標準化によって清潔レベルまで高めた例です。

棚の定位置には「品名」「発注点」「発注個数」「発注先」に加えて「商品の画像」が標示されています。
これにより、どの商品を・いくつになったら・いくつ注文するかが誰にでも一目で分かります。
さらに、置き場所には残数を示す数字が標示されており、数えなくても在庫数が瞬時に把握できます。
発注点には「発注してください」という標示が出る仕掛けもあり、発注忘れを防ぐ仕組みになっています。
事例②廃液缶処理の仕組み
この事例は、廃液缶の保管ルールを明確にして、誰が見ても同じ管理ができるようにした例です。

保管場所には「廃液缶」「3段以上積まない」「黄色枠内」「いっぱいになったら処理に行く」といったルールが掲示されています。
さらに、3段目の高さに合わせて壁に緑のラインが引かれ、(写真には写っていませんが)床には黄色い区画線も設けられています。
これにより、どれくらい溜まったら処理に行くべきかが一目で分かる仕組みになっています。
この仕組みがあることで、担当者が変わっても迷うことなく同じ基準で管理でき、廃液缶の放置や積みすぎによる危険を防ぐことができます。
これらの事例は、清潔が単なる「きれいにする活動」ではなく、3Sを仕組みとして継続させる段階であることを示しています。
清潔とは、新しい取り組みを増やすことではなく、整理・整頓・清掃で決めたことを漏れなく徹底できる仕掛けを整えることなのです。
清潔のチェックリスト
当社では、現場で使える 5Sチェックリスト をご用意しています。
ダウンロードはこちら
-

5Sチェックシート無料ダウンロード
いつもご覧いただきありがとうございます。 たくさんのご要望にお答えしてSmile System Support監修により「5Sチェックリスト」を無料ダウンロードできるようにしました。 こ ...
続きを見る
清潔には独立したチェックリストを設けていませんが、実際には 整理・整頓・清掃のチェックリストをきちんと運用することが清潔の維持につながります。
つまり、清潔とは「3Sのルールを標準化し、チェックリストを仕組みとして回せている状態」と言えます。
FAQ:清潔のよくある質問
Q. 清掃と清潔の違いは何ですか?
A. 清掃は汚れや乱れを取り除いて「働きやすい環境を整える」活動です。
一方で清潔は、その状態を標準化・ルール化・仕組み化して「誰がやっても同じ環境を維持できるようにする」段階です。
Q. 清潔のチェックリストはありますか?
A. 当社では清潔の専用チェックリストは設けていません。
実際には、整理・整頓・清掃それぞれのチェックリストを運用することが清潔の維持につながります。
👉 [5Sチェックリストのダウンロードはこちら]
Q. 清潔と躾の違いは何ですか?
A. 清潔は「ルールや仕組みで環境を維持する段階」です。
躾はそのルールが自然に守られ、意識せずとも習慣化されている段階です。
Q. 清潔を定着させるコツはありますか?
A. ポイントは「考えなくても自然にできる仕組み」を取り入れることです。
例:工具の形跡管理で戻さざるを得ない状態にする、清掃道具を汚れやすい場所の近くに置く、発注カードで自動的に補充につながる仕組みをつくる、などです。
Q5. 清潔は5Sの中でなぜ重要なのですか?
3Sを続けられる仕組みがなければ、環境はすぐに元に戻ってしまうから。
清潔があることで5Sが一時的で終わらず、継続的に効果を発揮します。
Q. 清潔と衛生管理は違うのですか?
清潔は「3Sの標準化と維持」であり、必ずしも衛生(衛生的にきれいかどうか)に限定されるものではありません。
ただし食品や医療の分野では「衛生」と直結する効果もあります。
次は「躾」へ――習慣化で根づかせる最終ステップ
「清潔」は、整理・整頓・清掃を仕組みで維持する段階でした。
次の「躾」は、それらが自然に習慣化し、誰もが当たり前に実行できるようになった状態を指します。
厳しく守らせるのではなく、自発的に風土として根づくことが本来の「躾」です。
こちらもCHECK
-

5Sの「躾」に違和感?誤解されがちな「躾」の本当の意味とは
5S活動は「整理・整頓・清掃・清潔・躾」の5つのステップで構成されます。 その中で最後の「躾(しつけ)」は、言葉の響きから誤解されやすい要素です。 「しつけ」と聞くと、子どもや部下に厳し ...
続きを見る
まとめ
清潔とは、新しい活動を加えるのではなく、整理・整頓・清掃を標準化・ルール化・仕組み化して、誰がやっても同じ状態を維持できるようにする段階です。
- 清掃=環境を整える行為
- 清潔=整えた環境を維持する仕組み
- 躾=その仕組みが自然に習慣化された状態
事例(在庫管理の発注カード方式や廃液缶の保管ルール)でも見たように、仕組みとして回る形をつくることが清潔の本質です。
清潔が定着することで、3Sの成果が一時的に終わらず、次の「躾=習慣化」へとつながり、職場全体の風土を変えていく基盤となります。
👉 続けて「躾とは?」をご覧ください。