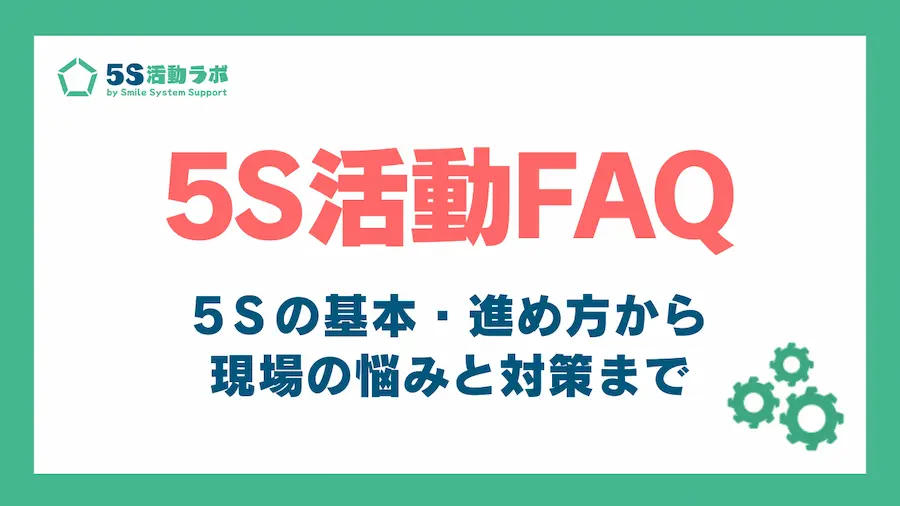
5S活動に取り組むとき、多くの現場から「整理と整頓の違いは?」「赤札や3定のルールはどう決める?」「清掃が形だけにならない工夫は?」といった疑問が寄せられます。
このページでは、整理・整頓・清掃・清潔・しつけの基本定義から、赤札・3定・PDCA・見える化などの実践ツール、さらに工場・病院・介護・事務サービスといった業種別の活用法まで、よくある質問をまとめました。
まず要点を短く理解し、詳しく知りたいテーマはリンク先の記事で深掘りできるようになっています。
よくある質問一覧
■ 5Sの基本(定義・順番・効果)
■ キックオフと方針づくり(経営の関与・方針・期待値)
- 経営者・上司は5Sにどのように関わるべきですか?
- 5Sリーダーに任命されたが、上司をどう巻き込めばいいですか?
- トップダウンとボトムアップ、どちらで進めるのが良いですか?
- スローガンや標語はいつ・どう作るべきですか?
- 5Sをやると利益は上がりますか?
■ 運用の仕組み(ルール・パトロール・全員参加・PDCA)
■ 実践ツールと仕組み化(赤札・3定・発注・見える化)
- 赤札作戦はどのように進めればいいですか?
- 5S計画表とは何ですか?
- 3定(定位・定品・定量)の実践ポイントは?
- 整理整頓して空いた棚スペースにモノが戻されないようにするには?
- 発注ミスや在庫ムダを減らす仕組みは?
- 現場でよく使われる見える化の方法は?
- レイアウトや動線を工夫して効率化するポイントは?
- 整理・整頓を行っても、すぐに元の状態に戻ってしまいます。どのように維持すればよいですか?
■ 現場の悩みと対策(維持・日常運用)
- 自分しか使わない場所まで徹底して5S活動をする必要はあるのか?
- 定位置に戻らないのはなぜ?どう防ぐ?
- 清掃が形だけになってしまうのはなぜ?
- ルールを守らない/守れないときはどうする?
- 仕事が忙しくて5Sに時間が取れません。どうすればいいですか?
■ 業種別(工場・病院・介護・事務)
5Sの基本
Q. 5Sの目的と効果は?
A. 5Sは「整理・整頓・清掃・清潔・しつけ」を通じて、生産性向上・安全確保・品質向上・風土改革を実現する“仕組み化の活動”です。残業削減・離職率低下・コンプライアンス強化・チームワーク向上などの副次効果も確認できます。継続の鍵はPDCAと“月例の振り返り”で、活動の見える化(活動報告書)まで含めて回すと定着が加速します。
👉 詳しくはこちら:「5S活動の目的とは|安全・効率・快適、そして躾で職場を変える」
Q. 5Sの順番はなぜ“整理→整頓→清掃→清潔→しつけ”?
A. この順番は“ムダの排除→取り出しやすさ→異常の早期発見→標準化→習慣化”という論理で積み上がるからです。特に最初の「整理」を徹底しないと、以降の整頓や清掃の効果が出ません。
👉 詳しくはこちら:「5Sとは?職場改善の基本を徹底解説!目的・進め方・成功事例をわかりやすく紹介」
Q. 「整理」とは何をする?
A. 「いる/いらない/急がない」に分け、不要物を“徹底的に処分”する活動です。要不要の基準を明確化し、「赤札作戦」を使って期限内に判断・処分するルールで前に進めます。
👉 詳しくはこちら:「5Sの整理とは?目的・基準・進め方まで失敗しないコツを徹底解説」
Q. 「整頓」と「整列」は何が違う?
A. 整列は“見た目を揃えただけ”で、効率は上がりません。整頓は“誰でもすぐに取り出せるように定位置・適正量を決めて標示する”ことで効率を上げます。現場目線で住所決めや層別配置・形跡管理・ロケーション番号などを設計すると定着します。
👉詳しくはこちら:「5Sの整頓とは?意味・3定から進め方・事例・失敗対策まで徹底解説」
Q. 清掃の目的は?
A. “誰がやっても同じ基準で”きれいを維持し、異常の早期発見・品質向上・安全確保・信頼向上につなげることです。きれいの基準や清掃ルールを決め、習慣化の仕組みを作り、継続を目指します。日々の清掃は“見て見ぬふりをしない風土”を育てます。
👉詳しくはこちら:「5Sの清掃とは?意味・目的・効果・ルール化のポイントを徹底解説」
Q. 清潔とは具体的に何をすればよいですか?
A. 清潔とは「整理・整頓・清掃」で決めたルールが標準化され、維持されている状態を指します。つまり最初の3Sをルール化・改善し続ける仕組みを整えることで、現場が常に「清潔」な状態を保てるようになります。毎月の活動を振り返りながらPDCAで回すことがポイントです。
👉詳しくはこちら:「5Sの「清潔」とは?清掃との違い・目的・事例までわかりやすく解説」
Q. しつけとは?
A. しつけとは、3Sのルールが習慣化され、無意識に行動できる状態を指します(5Sの最終段階)。この段階では「決められたことを自然に守る組織風土」が形成されます。さらに、しつけが進むと社員の「気づく力」が育ち、普段と違う状態を自ら見つけて改善につなげられるようになります。3Sを徹底し、日々コツコツ継続することが達成の秘訣です。
👉詳しくはこちら:「5Sの「躾」に違和感?誤解されがちな「躾」の本当の意味とは」
キックオフと方針づくり
Q. 経営者・上司は5Sにどのように関わるべきですか?
A. 経営者・上司は率先して活動に参加し模範を示すと同時に、現場の意見を尊重して判断を現場に委ねる(権限移譲)ことで主体性と責任感を育てます。また、現場が自律的に判断できるように具体的なルールを整備し、日常の判断を上司に依存させない仕組みを作ることが重要です。
👉 詳しくはこちら:「5S活動が失敗する原因は経営者にあった」
Q. 5Sリーダーに任命されたが、上司をどう巻き込めばいいですか?
A. 上司が非協力的な場合は無理に説得しようとせず、まず協力的なメンバーを増やして成果を見せることが有効です。成果が可視化されると賛同者が自然に広がり、徐々に上司の態度も変わる可能性が高まります。
👉 詳しくはこちら:「5Sリーダーとは?役割・選び方・会議運営と育成のポイント」
Q. トップダウンとボトムアップ、どちらで進めるのが良いですか?
A. 理想はボトムアップです。社員自身が問題を見つけ、試して学ぶことで主体性と成功体験が生まれ、長期的に強い定着と組織風土の変革につながります(トップダウンはスピードがありますが“やらされ感”が残りやすい)。
Q. スローガンや標語はいつ・どう作るべきですか?
A. 活動開始時に「なぜこれをやるのか」という目的を全員で合意し、ビジョン(会社の未来像) → 年度スローガン(部署別数値目標)へ落とすとブレません。スローガンは月例の振り返りで常にチェックし、数値目標と結びつけると効果が高まります。
👉詳しくはこちら:「5S活動のスローガン/標語の例と5Sスローガン・目標の作り方」
Q. 5Sをやると利益は上がりますか?
A. 5Sは短期で即利益に直結するわけではなく、継続して基礎体力が付いた結果として生産性向上 → 短納期・品質向上 → 価格競争力向上につながり、結果的に利益性が高まります。活動は「漢方薬」のように効果が出るまで時間がかかるため、初期〜中期の目安(半年〜1年、1年半〜3年)で変化を捉えるのが現実的です。
運用の仕組み
Q. 5Sのルールはどうやって決めればいいですか?
A. 現場の合意を軸に目的共有し、基準を決めます。(定位置・保管年数・清掃頻度などを数値化)。決めたらルールの掲示や朝礼で周知し、1カ月ごとに見直します。ルールは押し付けるものではなく、誰でも自然に守れる仕組みに育てることが重要です。
👉詳しくはこちら:「5Sルールとは?決め方・事例・守れる仕組み化まで徹底解説」
Q. 5Sパトロールはどのように進めたらいいですか?
A. 月1回程度を基本に、現場メンバーが交代で参加してチェックリストで状態を記録し、その場で気づきを共有して即時対応できる小さな改善を決める運びにします。記録(写真・コメント)を残してリーダー会議で横展開・優先度付けを行い、PDCAで改善を継続すると定着します。
Q. 5Sに全員参加が難しい場合はどうすればいいですか?
A. 班を4〜6人の小グループに分けて月1回の短時間ミーティングで改善を回し、リーダー会議で各グループの成果や共通課題を横展開する仕組みにすると交代制や夜勤でも継続できます。記録や写真で情報を引き継ぎ、PDCAで小さな改善を積み重ねることで「やらされ感」を減らし主体性を育てられます。
Q. PDCA(振り返り)はどう回すのが良いですか?
A. 5Sは継続が肝心なので、Plan→Do→Check→Actを回し、特に「振り返り(Check)」を重視して月に一度は「うまくいった点/原因/次の改善案」を話し合う場を必ず設けます。活動は報告書で見える化し、成果と学びを共有すると次の実行がスムーズになります。
👉詳しくはこちら:「5S振り返りのやり方|毎月の報告書とKPTで改善を定着させる方法」
実践ツールと仕組み化
Q. 赤札作戦はどのように進めればいいですか?
A. まず現場に「赤札」を用意し、不要と思われる物に札を貼って仮置き場へ移すところから始めます。札には品名・数量・処置期限・担当を記入し、期限までに責任者が判断→処分まで進める流れをルール化します。たとえば「工具に1年間赤札が貼られたままなら処分」といった基準を事前に決めると、現場が迷わず進められます。
Q. 5S計画表とは何ですか?
A. 5S活動を継続させるために、誰が・いつ・どこで・何を行うかを明確にするための表です。年間の流れと月ごとの行動を可視化することで、やりっぱなしを防ぎ、成果を確認しやすくなります。
Q. 3定(定位・定品・定量)の実践ポイントは?
A. 3定とは「定位=置き場所を決める」「定品=置く物を決める」「定量=数量を決める」というルールです。誰が使っても迷わず、同じ場所に同じ物が同じ数だけある状態を作ることで、探すムダや欠品・過剰在庫を防げます。
👉詳しくはこちら:「3定管理とは?5S活動で実践する意味・目的・事例を徹底解説」
Q. 整理整頓して空いた棚スペースにモノが戻されないようにするには?
A. 整理の直後に「整頓」で定位置と標示を決め、誰でも分かる表示(写真・ラベル)で置き場を明確にすることが有効です。人数がいれば整頓チームと次の整理チームで分担し、人数が少ない場合は整理→すぐ整頓を実行。また、一時的に置かせないための「ここには置かない」表示を使う運用も実用的です。
Q. 発注ミスや在庫ムダを減らす仕組みは?
A. 最大数・最小数・発注数を決め、誰が・いつ・どう発注するかをルール化します。発注点に発注カード(発注数/発注先/品番など)を置き、担当へつなぐ流れにすると、発注忘れ・重複を防げます。
👉詳しくはこちら:「5Sの整頓とは?意味・3定から進め方・事例・失敗対策まで徹底解説」
Q. 現場でよく使われる見える化の方法は?
A. 現場では「形跡管理(道具の住所をシルエットで示す)」「色分け(置き場と道具を同色にする)」「標示(ラベル・番号・写真表示)」などが基本です。さらに広い倉庫ではロケーション番号やマップを組み合わせることで、誰でも迷わず探せて、置き忘れや誤使用を防げます。
👉詳しくはこちら:「5Sの整頓とは?意味・3定から進め方・事例・失敗対策まで徹底解説」
Q. レイアウトや動線を工夫して効率化するポイントは?
A. 使用頻度の高い物は手前に、工程の流れに沿って配置し、重い物は扱いやすい位置に置くなど動線に合わせた配置が基本です。姿絵(形跡管理)やロケーション番号、ロケーションマップで住所を可視化すると探す時間が激減し、余剰品は別置き場で管理すると現場が散らかりにくくなります。
Q. 整理・整頓を行っても、すぐに元の状態に戻ってしまいます。どのように維持すればよいですか?
A. 元に戻る原因は「忘れる」「面倒に感じる」という自然な行動にあります。まずは個人を責めずに「なぜできなかったか」を掘ることが先決です。忘れるならリマインド(掲示・タイマー・定期点検)を仕掛けたり、面倒なら動線や定位置を見直して手間を減らす仕組みを作る。こうした「守れる仕組み」作りが整頓の本質です。
👉詳しくはこちら:「5Sの整頓とは?意味・3定から進め方・事例・失敗対策まで徹底解説」
現場の悩みと対策
Q. 自分しか使わない場所まで徹底して5S活動をする必要はあるのか?
A. 必要です。5Sの「整頓」は「誰でもすぐに取り出せる状態」を目指しています。あなたが不在でも代わりの人が迷わず作業できるようにすることで、ロスや混乱を防げます。また「自分は分かるから大丈夫」と思っても、5Sで整った状態と比べると効率に差が出ます。わずか数秒の短縮でも積み重ねれば大きな成果につながり、結果として強い組織と効率的な職場をつくることになります。
Q. 定位置に戻らないのはなぜ?どう防ぐ?
A. 戻さない理由の多くは「定位置が使いにくい・遠い・わかりにくい」など仕組みの不備です。人の意識を責めるのではなく、近くて戻しやすい場所・形跡管理・色分けなどで“戻さないと不自然”な仕組みにすると定着します。
👉詳しくはこちら:「5Sの整頓とは?意味・3定から進め方・事例・失敗対策まで徹底解説」
Q. 清掃が形だけになってしまうのはなぜ?
A. 「掃除した風」に終始するのは、清掃の目的や基準が曖昧だからです。異常発見・安全確保・品質保証を目的に掲げ、誰が・どこを・どのレベルで行うかを明確化し、点検表や基準写真で共有すると形骸化を防げます。
👉詳しくはこちら:「5Sの清掃とは?意味・目的・効果・ルール化のポイントを徹底解説」
Q. ルールを守らない/守れないときはどうする?
A. 「なぜ守れないのか」を人に責任転嫁せず、仕組みを改善する視点で解決します。ルールの見直し→みんなで合意形成→守れる工夫(見える化・定位置化)→習慣化→改善、という流れを繰り返すことが効果的です。
Q. 仕事が忙しくて5Sに時間が取れません。どうすればいいですか?
A. 継続が最優先なので、まずは毎日3〜5分でも続ける習慣を作ってください。短時間で回せる「5Sの時間」を定着させると、業務効率が上がりやがてまとまった改善時間も作れるようになります。
業種別FAQ(工場・医療介護・事務サービス)
Q. 工場では5Sはどんな効果がありますか?
A. 工場では、5Sを徹底することで安全性向上・不良率低減・生産効率改善といった直接的な成果が得られます。工具や部材の定位置化で探すムダをなくし、清掃・点検を通じて設備異常を早期に発見できるため、故障や事故を未然に防げます。また、整理・整頓が進むことで動線が短縮され、段取り替えや在庫管理もスムーズになります。
👉詳しくはこちら:「工場の5S活動とは?意義・手順・効果を徹底解説|チェックリストつき」
Q. 病院では5Sはどんな効果がありますか?
A. 病院では、5Sにより薬剤や器具の取り違い防止・感染リスクの低減・患者安全の確保が実現できます。部署間の情報共有や業務標準化が進み、医療事故の未然防止やスタッフの負担軽減にもつながります。
👉詳しくはこちら:「病院での5S活動とは?意味・目的、継続の仕組みと実践5ステップ」
Q. 介護現場は5Sはどんな効果がありますか?
A. 介護の現場では、5Sが転倒防止・誤薬防止・感染予防に直結します。動線や物品配置を整えることで介助がスムーズになり、利用者の安全と職員の働きやすさが両立できます。離職率の低下やサービス品質の安定にも効果があります。
👉詳しくはこちら:「介護施設の5S活動とは|目標や進め方から事例・チェックシートまで」
Q. 事務やサービス業でも5Sは必要ですか?
A. 必要です。書類やデータの整頓・標準化で情報の探し時間を削減し、業務効率と正確性が向上します。また、メール・共有フォルダ・デスク周りを5Sすることで、顧客対応のスピードや信頼感も高められます。

