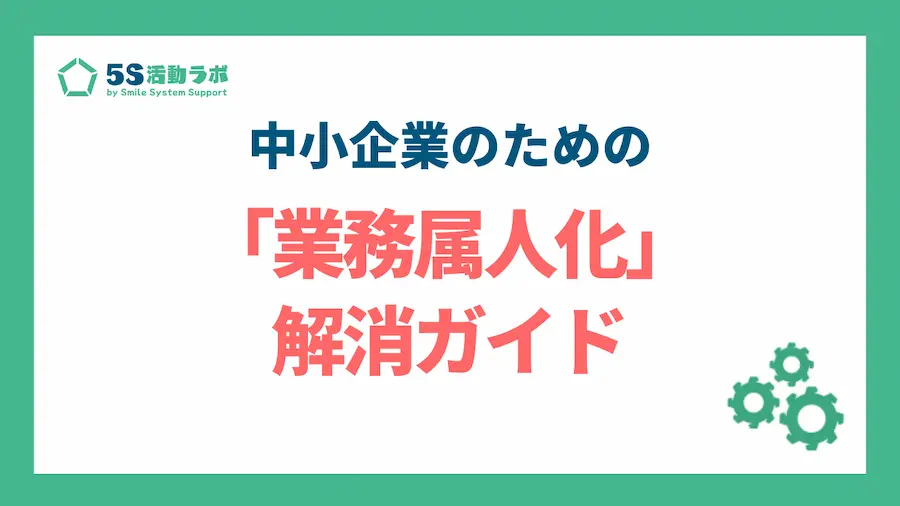
「◯◯さんがインフルエンザで休んだら、誰もあの機械を動かせない」
「経理の担当者が急に辞めてしまい、請求書の締め方が分からずパニックになった」
中小企業の現場では、こうした「特定の人にしかできない仕事(属人化)」が時限爆弾のように潜んでいます。
「ウチは少数精鋭だから仕方ない」と諦めていませんか?
実はその悩み、社員の能力や努力に頼るのではなく、業務を「情報の5S(整理整頓)」で仕組み化することで解決できます。
今回は、中小企業が陥りがちな「属人化リスク」と、それを解消するための具体的な3ステップについて解説します。
もくじ
なぜ「業務の属人化」は経営リスクなのか?
「仕事のやり方が、個人の頭の中だけにある」
この状態を放置すると、会社は以下のような深刻なリスクを抱えることになります。
属人化による3つの経営リスク
- 休職・退職リスク(黒字倒産の危機)
「この仕事はこの人しか分からない」という状態は、担当者に過度なプレッシャーを与えます。結果、過労やストレスでその人が倒れたり退職したりした瞬間、業務が完全にストップし、信用問題や黒字倒産に直結します。 - 品質のバラつき(ミスの温床)
マニュアルがなく「先輩の背中を見て覚える」スタイルだと、教える人によってやり方が変わり、品質が安定しません。お客様からのクレームの原因の多くはここにあります。 - 教育コストの増大(採用しても育たない)
新人に教えるための教科書がないため、ベテラン社員が手取り足取り教える必要があり、通常の業務時間を圧迫します。「教えている間は売上が下がる」という悪循環に陥ります。
なぜマニュアル化が進まない?「3つの言い訳」
仕組み化の重要性は分かっていても、なかなか進まないのが現実です。
現場からよく出てくる「言い訳」にはパターンがあります。
1. 「忙しくて作る時間がない」
これが一番多い理由です。「マニュアルを作っても、今日の売上にはならない」と考え、後回しにされがちです。
しかし、この「面倒な作業」を今やらない限り、3年後も5年後も同じ忙しさから抜け出せません。未来の時間を買う投資だと考える必要があります。
2. 「自分の仕事を取られたくない」
特に営業職や専門職に多いのが、「情報を公開すると自分の価値が下がる」という防衛本能です。
しかし、これは会社全体で見れば「個人商店の集まり」に過ぎず、組織としての力が発揮できていない状態です。
3. 「文字にするのが面倒くさい」
「マニュアル=分厚い説明書」というイメージが、ハードルを上げています。
しかし、現代の仕組み化は、必ずしも立派な文章を書く必要はありません(後述します)。
5S思考で解決!「情報の整理整頓」3ステップ
では、どうすれば属人化を解消できるのでしょうか?
ここで役立つのが、弊社が提唱している「情報の5S」という考え方です。
工場の整理整頓と同じステップで、業務も見直すことができます。
Step 1(整理):業務の棚卸し
まずは、誰がどんな仕事をしているかリストアップ(棚卸し)します。
そして、その仕事を以下の2つに分類します。
- A:自分しかできない仕事(高度な判断が必要)
- B:やり方さえ分かれば誰でもできる仕事(ルーチンワーク)
属人化解消の第一歩は、この「B(誰でもできる仕事)」を徹底的に手放すことから始まります。
また、この段階で「実はやらなくてもいいムダな業務」が見つかれば、思い切って捨てる(やめる)決断も必要です。
Step 2(整頓):暗黙知の可視化
次に、Bの業務を「誰でもできる」状態にするために、頭の中にあるノウハウ(暗黙知)を外に出して形にします。
ここで重要なのは「完璧なマニュアルを目指さないこと」です。
文章を書くのが苦手なら、「スマホで作業風景を動画に撮る」だけでも立派なマニュアルになります。
- 複雑な機械操作 → 動画を撮影して共有フォルダへ
- 検品作業 → OK品とNG品の写真を壁に貼る
これなら、「文字にするのが面倒」という言い訳も通用しません。
Step 3(標準化):ルールの共有
最後に、作ったマニュアルや動画を「いつ、誰が見ても分かる場所」に置きます(情報の定位置管理)。
自分だけが持っているのではなく、共有サーバーやクラウドに保存し、チーム全員がアクセスできるようにします。
👉 ルールを守らない社員の対処法|叱責より仕組み!5Sで「守れる風土」づくり
事例:5Sで「職人技」を継承し、組織が変わった
実際に、5S活動を通じて業務の属人化を解消した企業の事例をご紹介します。
【事例1】毎日残業→定時帰宅へ(製造業)
見積書作成業務がある1人の社員に集中し、その人だけが毎日残業している状態でした。
そこで、見積もりの手順をマニュアル化(標準化)し、他の社員でも対応できるようにしたところ、業務が分散され、全員が定時で帰れるようになりました。
【事例2】新しい診療科の開設がスムーズに(病院)
ある病院では、日々の事務作業をマニュアル化したことで、「大変だ」と思っていた業務への心理的ハードルが下がりました。
「マニュアルがあれば私にもできる」という自信が生まれ、新しい診療科を開設する際も、スタッフが尻込みせずスムーズに対応できる組織風土に変わりました。
👉 病院での5S活動とは?意味・目的、継続の仕組みと実践5ステップ
「マニュアル嫌い」な職人をどう動かすか?
それでも「俺の仕事はマニュアルにはできない」と反発するベテラン社員もいるでしょう。
そんな時は、「人を責めずに、仕組みを責める」のが鉄則です。
「あなたが教えてくれないから困る」と人を責めるのではなく、「マニュアルがないから新人が育たない(仕組みが悪い)」と考えるのです。
また、5S活動は「失敗してもリスクが少ない活動」です。
「まずはこの簡単な作業の動画を撮ることから始めませんか?」と、小さな一歩から巻き込んでいくことが成功の鍵です。
👉 5S活動反対派の効果的な対処法|抵抗勢力を力に変える5つのステップ
まとめ:仕組み化とは、社員を「楽」にすること
業務の属人化解消(マニュアル化)は、社員を縛るためのものではありません。
むしろ、「社員を楽にする」ためのものです。
いちいち人に聞かなくても仕事が進められる。
新人に同じことを何度も教えなくて済む。
安心して有給休暇が取れる。
仕組み化が進めば、社員は「記憶する作業」から解放され、「考える仕事(付加価値の高い仕事)」に集中できるようになります。
これが、中小企業が生き残るための「生産性向上」の正体です。
「どこから手をつけていいか分からない」「社員の意識を変えたい」とお考えの経営者様は、ぜひ弊社の5Sセミナーをご利用ください。

