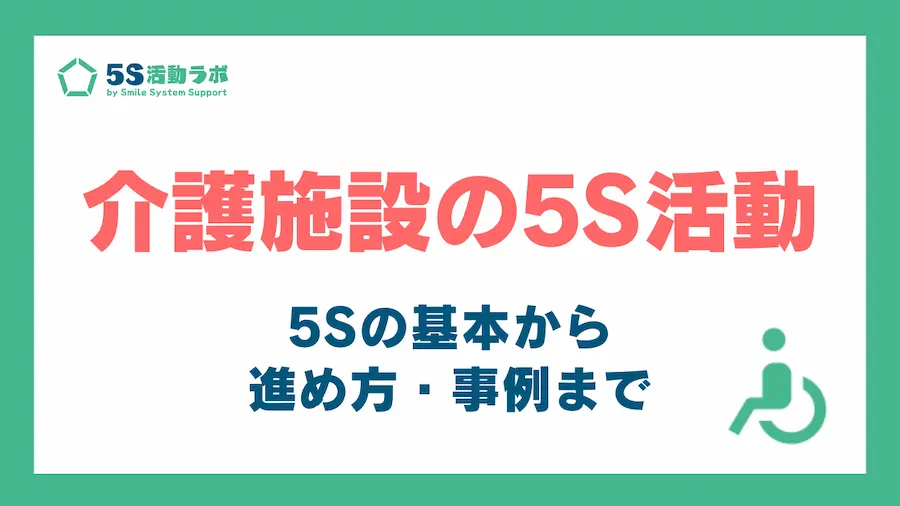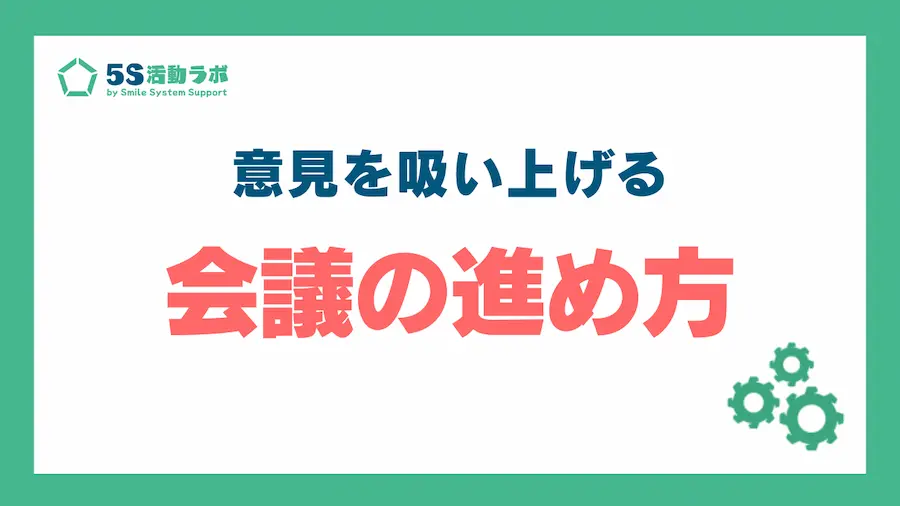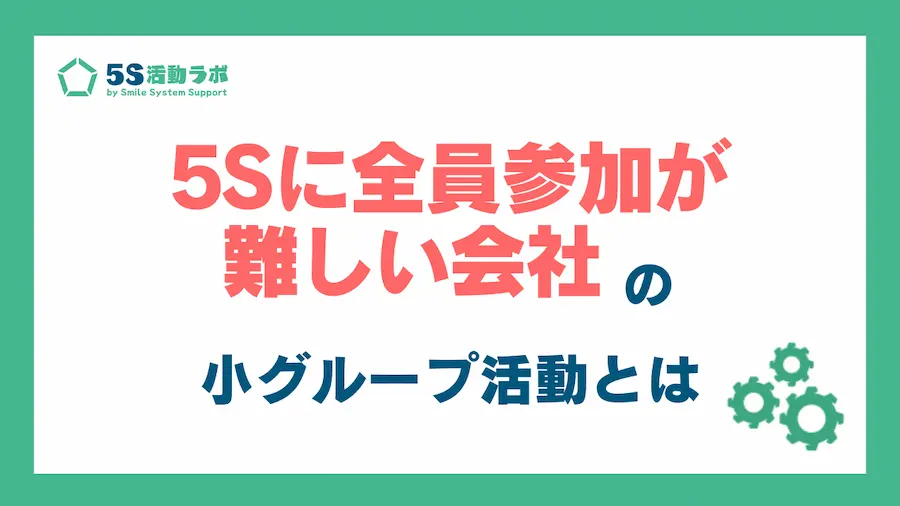
5S活動は「全員で取り組む」のが理想ですが、夜勤や交代制で人が集まれない、ラインを止められないなどの事情から、思うように進まない職場も多くあります。「全員参加が難しい」と感じている現場にこそ有効なのが、小グループ活動とリーダー会議です。
本記事では、夜勤・交代制でも続けられる5Sの進め方として、グループの作り方、短時間ミーティングの進行、記録・共有の工夫、リーダー会議での横展開、さらにPDCAと見える化のポイントまで解説します。小さな改善は日常業務を止めずに取り入れ、大掛かりな改善は計画的に時間を確保することで、現場に合わせた継続的な仕組みづくりが可能になります。
なぜ「全員参加」が難しいのか
5S活動は本来、会社全体で取り組み、全員が同じ目線で改善に参加するのが理想です。ところが実際には、次のような理由で「全員が同じ場に集まる」ことは難しいケースが多くあります。
- シフト制で同じ時間にメンバーが揃わない
- 夜勤者が会議や活動に参加できず、情報が偏ってしまう
- 製造ラインを止められないため、一斉に集まる時間を確保できない
こうした状況が続くと、活動に参加できる人とできない人の差が生まれ、5Sが「一部の人だけの取り組み」になってしまいます。これでは本来の目的である「全員参加による職場改善」から遠ざかってしまいます。
だからこそ必要なのが、小グループに分けて進める方法なのです。
小グループ活動の進め方
全員が同じ時間に集まれない職場でも、5Sを定着させる仕組みは作れます。その基本が「小グループ活動」です。ここでは、実際の進め方を4つのステップで紹介します。
① 5Sの意味や目的を共有する
小グループ活動を始める前に、まず全員に5Sの意味と目的を共有することが欠かせません。ここが曖昧なまま進むと、「ただの片付け」と誤解され、やらされ感や温度差を生みやすくなります。
5Sがどういう活動なのか、なぜ必要なのか、社員一人ひとりにどんなメリットがあるのかを伝えることで、「自分ごと」として受け止めてもらえます。
一斉説明だけでなく、できれば個人面談形式で伝えるのが理想です。個別の対話が不安や疑問を解消し、足並みを揃える出発点になります。
② グループ分けとリーダー選出
社員を 4〜6人の小グループ に分けます。必ず全員がどこかのグループに所属するようにし、それぞれのグループには とりまとめ役のリーダー を1名決めます。
リーダーは必ずしも管理職でなくても構いません。「声をかけやすい」「周囲から信頼されている」人を選ぶのがポイントです。
👉 5Sリーダーとは?役割・選び方・会議運営と育成のポイント
③ 月1回のグループミーティング
各グループでは 月1回・30〜45分程度 の短い会議を行います。ここで重要なのは、必ず全員が意見を出す時間をつくることです。
議題例:
- 日々の業務で困っていること
- 改善できそうなアイデア
- 次回までに試してみたい取り組み
リーダーは一人ひとりに意見を聞き、否定せずに受け止めながらまとめていきます。
④ リーダー会議で全体をつなぐ
各グループで出た意見や改善案は、リーダー会議で持ち寄ります。ここで共通課題や全社的に展開すべきテーマを決定し、活動の方向性を揃えます。リーダー会議を軸にすることで、夜勤や交代制の現場でも「全社で取り組んでいる」という一体感を保つことができます。
さらに、この場では 「計画(Plan)→実行(Do)→振り返り(Check)→改善(Act)」というPDCAサイクル を意識して確認することが大切です。毎月の小さな改善を確実に振り返り、次の行動に結びつけることで、活動が続き、着実に成果が積み重なっていきます。
👉 5S計画表の作り方
👉 5S活動の振り返りと報告書の作り方
夜勤・交代制・ライン稼働中でも続けられる工夫
小グループ活動の仕組みを取り入れても、「夜勤や交代制ではうまく回らないのでは?」と不安に感じる方も多いでしょう。そこで、シフト制やラインを止められない現場でも続けられる工夫をまとめます。
記録と写真で情報を引き継ぐ
- ミーティングで出た意見や改善案は、簡単な記録シートや写真で残します。
- 次の班や夜勤のメンバーが読める形にしておくことで、活動の連続性が保たれます。
- 「現場の見える化」を進める効果もあります。
会議は短時間で回す
- グループミーティングは 30〜45分以内 を目安にします。
- 議題を事前に絞っておくと、ラインを止めずに効率よく進行できます。
- 「短くても続けられる」ことが定着への第一歩です。
欠席者にはリーダーが共有する
- どうしても参加できないメンバーには、リーダーが 記録や写真をもとに共有 します。
- 「自分だけ置き去りにされた」と感じさせないことが大切です。
- 共有の仕組みがあることで、参加できない人も自然と関心を持てるようになります。
こちらもCHECK
-

介護施設の5S活動とは|目標や進め方から事例・チェックシートまで
介護施設では、転倒やヒヤリハット、探し物による時間ロス、在庫切れや残業など、日常的に多くの課題が発生します。 こうした現場の問題を根本から改善する手法として注目されているのが 5S活動(整理・整頓・清 ...
続きを見る
意見を引き出すファシリテーションのコツ
小グループ活動を続けていても、会議の場で「誰も発言しない」「一部の人だけが話す」といった状況はよくあります。そんな時に大切なのが、コーチングの考え方をベースにした関わり方です。
さえぎらずに最後まで聞く
発言の途中で口をはさんでしまうと、「どうせ最後まで聞いてもらえない」と感じさせてしまいます。まずは相手の話を最後まで聞き切ること。その上で確認や質問をすると、本人の考えが整理され、主体的な改善意欲につながります。
否定しないで受け止める
誰かが意見を出したときに、すぐに「それは違う」と否定してしまうと、他の人も発言しにくくなります。「なるほど、他には?」と受け止めることで、安心して発言できる雰囲気が生まれます。
小さな意見でも承認する
「やらされ感」が強い現場では、自分の声が無視されていると感じることで意欲が下がりがちです。小さな改善提案でも取り上げて承認し、「自分の意見が反映されている」と実感できる環境をつくることが重要です。これが、やらされ感を減らし、自分事として活動に関わるきっかけになります。
問いかけを工夫する
「何か意見ありますか?」ではなく、具体的で答えやすい問いを投げかけるのが効果的です。
例:「作業で不便に感じることを一つ教えてください」「次回までに試せそうな工夫はありますか?」。小さな問いを積み重ねることで、会議全体が前向きな雰囲気になります。
意見を吸い上げる会議の進め
-

意見を吸い上げる会議の進め方|ボトムアップで社員の主体性を育む方法
会議を効果的に続けるために欠かせないのが、参加者からの意見を吸い上げる仕組みです。 しかし、現場でよく耳にするのは「意見が出ない」「形骸化して続かない」といった悩みです。 本来の会議は単なる報告の場で ...
続きを見る
FAQ:よくある質問
Q. 夜勤や交代制の職場でも5S活動は本当に続けられますか?
はい。全員で集まれなくても、小グループ活動+リーダー会議を仕組みにすれば継続できます。記録や写真を活用して交代制でも情報を引き継げば、活動の連続性が保たれます。
Q. 会議で意見が出ないとき、どう質問すればいいですか?
「何かありますか?」ではなく、具体的な問いかけに変えましょう。
例:「作業で不便に感じることは?」「次回までに試したい工夫は?」。否定せず最後まで聞くことが信頼につながります。
Q. 改善案が出ても実行されないことが多いのですが?
1か月単位の計画と振り返りを徹底しましょう。小さく決めて、翌月に検証→改善する。PDCAを回すことで実行が習慣化されます。
👉 5S計画表の作り方
👉 5S活動の振り返りと報告書の作り方
Q. 交代制の班ごとに温度差が出る場合は?
記録や写真で情報を共有し、リーダー会議で活動状況を持ち寄ります。成功事例を横展開することで、全体の温度感を揃えられます。
Q. 「やらされ感」が強い社員を巻き込むには?
目的の理解と小さな成功体験が大切です。安全・効率につながる活動だと伝え、出た意見を否定せず取り入れることで「自分ごと化」できます。
Q. 改善の成果はどう「見える化」すれば?
数値化と写真化が基本です。改善件数や不良率、安全指標を数値で、ビフォー・アフターを写真で掲示。毎月の活動報告で継続的に共有します。
例えば「不良率◯%改善」「作業時間◯分短縮」といったQCD(品質・コスト・納期)指標で表すと、効果がより明確になります。
Q. リーダーの負担を減らすには?
リーダーに全てを任せてしまうと、負担が大きくなり活動が続かなくなります。役割分担とローテーションを徹底することが大切です。
- 会議の司会進行はリーダー、記録はメンバーA、資料準備はメンバーB、といったように分担する
- 月ごとに担当をローテーションし、活動に関わらない人が出ないようにする
さらに、リーダー同士で課題を共有できるリーダー会議そのものが「支援の場」になります。他のリーダーと悩みや工夫を交換することで孤立を防ぎ、負担も軽減されます。
まとめ
5Sは全員で取り組むのが理想ですが、夜勤や交代制、ラインを止められない職場では難しいのが現実です。そこで有効なのが、小グループ活動+リーダー会議。4〜6人で月1回短時間ミーティングを行い、記録や写真で交代制にも共有する仕組みです。小さな改善をPDCAで回し、数値や写真で成果を見える化すれば、やらされ感が減り主体性が育ちます。
こうした取り組みを自社に定着させたい方は、まずは「絶対に定着させる5S活動セミナー」の体験版で実践のヒントをつかんでください。