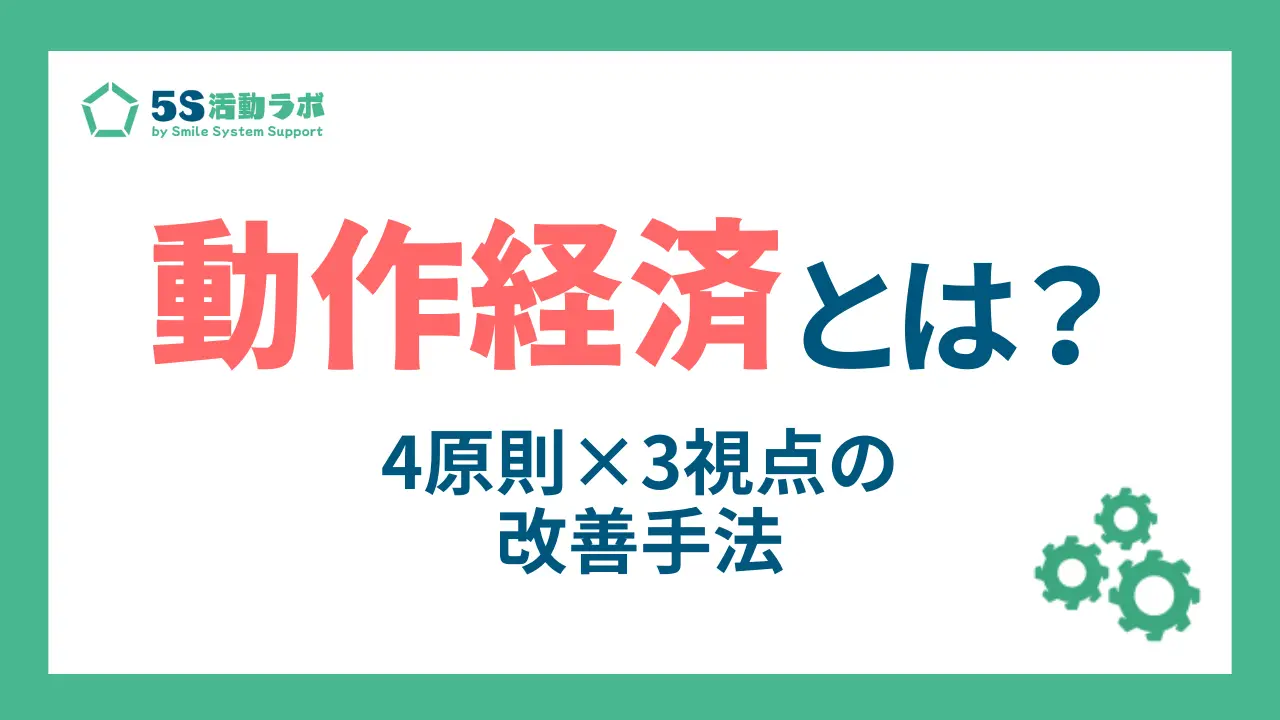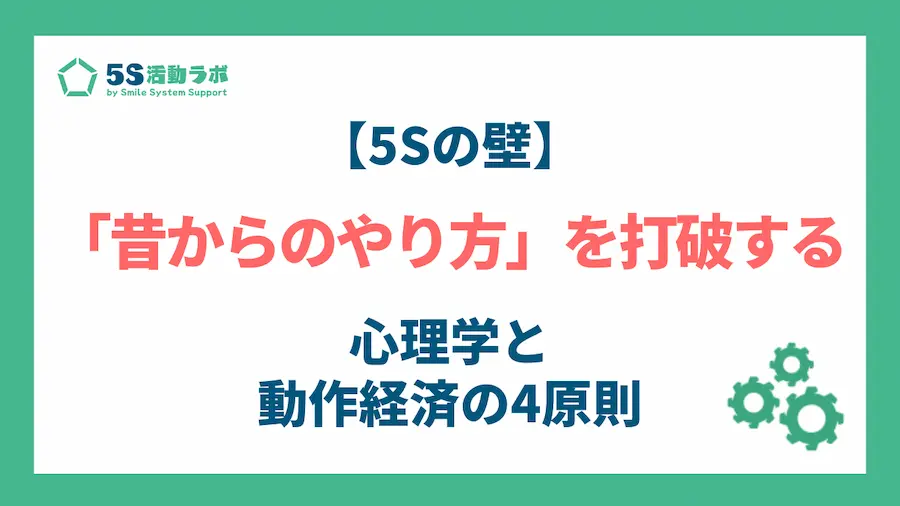
5S活動(整理・整頓・清掃・清潔・躾)の真の目的は、単に職場をきれいにすることではありません。
ムダをなくして生産性を高め、「全員で決めたルールを守れる社内風土」を作ることです。
しかし、いざ改革を進めようとすると、必ず立ちはだかる「見えない壁」があります。
それは、あなたの会社の中に深く根付いている「悪しき習慣」です。
もくじ
5S活動のNGワード「うちは昔からこれでやってきたから」
5S活動では、まず現状の業務を見直し、問題点を見つけ出すことから始めます。
しかし、改善案を出した途端、ベテラン社員や現場からこんな言葉が返ってくることはありませんか?
「うちは昔からこのやり方でやってきたから(変える必要はない)」

これは、会社に長く貢献してきた人ほど口にしてしまう、変化を拒むための言葉です。
👉 4M分析とは?5S活動の課題を洗い出す実践ステップを解説
「慣れ」=「効率的」という勘違い
同じやり方を長く続けていると、身体がその動きに慣れてしまうため、本人は「今のやり方が一番やりやすい(快適だ)」と感じています。
しかし、「慣れていること」と「効率が良いこと」は全く別物です。
その「昔ながらのやり方」の中には、実は大量のムダが潜んでいるケースが大半です。
「なぜそのやり方なのか?」と問うた時、「昔からそうだから」以外に、理論的な説明ができない作業は、改善の余地(宝の山)があります。
この心理的な壁をどう突破すればよいのでしょうか。
【心理的対策】5S活動反対派をどう動かすか?
現状を変えることに抵抗がある「反対派」への対処法。
結論から言いますと、「反対派は説得せず、放っておく」のが正解です。
冷たいように聞こえるかもしれませんが、外部からの働きかけだけで人の心を変えることは困難だからです。ここで使うべきなのが「組織の2:6:2の法則」です。
組織を動かす「2:6:2の法則」

多くの企業様で5S活動を支援してきた統計上、組織の構成は以下のようになります。
- 上位2割(推進派):モチベーションが高く、率先して変化を楽しむ人
- 中位6割(日和見派):「どちらでもいい」「やるなら従う」という層
- 下位2割(反対派):「面倒くさい」「今のままでいい」と抵抗する人
5S活動を失敗させるリーダーは、この「下位2割」を説得しようとして時間を浪費し、疲弊してしまいます。
成功のポイントは、「上位2割の推進派」に焦点を合わせることです。
彼らと共に成功事例を作り、「5Sをやると仕事が楽になる」「評価される」という実績を作るのです。
そうすると、中間の6割が「あっちの方が良さそうだ」と推進派に流れ始めます。
組織の8割が「5S推進」に傾いた時、反対派も変わらざるを得ない空気が生まれます。これが、遠回りのようで一番確実な組織改革の方法です。
👉 5S活動反対派の効果的な対処法|抵抗勢力を力に変える5つのステップ
【技術的対策】文句を言わせない「動作経済の4原則」
心理的なアプローチの次は、技術的なアプローチです。
「昔からのやり方」に固執する人を論理的に納得させるための強力な武器、それが「動作経済の4原則」です。
これは製造現場の父とも呼ばれるギルブレスが提唱した、「作業のムダを省き、疲労を減らすための経験則」です。
精神論ではなく「身体の仕組み」に基づいているため、誰も反論できません。
動作経済の4原則
- 動作の回数を減らす(Eliminate)
- 身体部位を同時に使う(Combine)
- 移動距離を短くする(Shorten)
- 動作を楽にする(Easier)
1. 動作の回数を減らす
「その作業、そもそも必要ですか?」と考えます。
仕事の目的に直結しない動きをなくします。
- 例:確認印を押す回数を減らす、カバーの開け閉めをなくす、工具の持ち替えをなくす。
2. 身体部位を同時に使う
「片手がお留守になっていませんか?」と考えます。
右手で作業している間、左手がただ品物を抑えているだけならムダです。
- 例:左右の手で同時に部品を取り出す、治具を使って両手をフリーにして組み立てる。
3. 移動距離を短くする
「探す時間、歩く時間は作業ではありません」と考えます。
必要なモノを、手を伸ばせば届く範囲(最適な作業域)に配置します。
- 例:よく使う工具を手元に置く、キャスター付きの台車でモノの方を動かす。
4. 動作を楽にする
「無理な姿勢をさせていませんか?」と考えます。
しゃがむ、背伸びをする、振り返るといった動作は疲労の原因となり、ミスを誘発します。
- 例:作業台の高さを身長に合わせる、重いものは持ち上げずにスライドさせる(重力の利用)。
このように、「楽をするための科学的なルール」だと伝えれば、反対派の人も「それならやってみようか」と受け入れやすくなります。
動作経済の4原則とは
-

動作経済とは?製造業で作業効率と生産性を上げる4原則×3視点の改善手法
毎日の作業で「無駄が多い」「疲れる」「非効率だ」と感じていませんか?そんな悩みを解決するのが、IE(Industrial Engineering)の基本手法である「動作経済」です。 これは作業を楽にし ...
続きを見る
まとめ:感情論ではなく「仕組み」で風土を変える
5S活動の壁となる「昔からのやり方」を壊すには、二つのアプローチが必要です。
- 心理面:反対派は追わず、推進派と共に8割の空気を作る(2:6:2の法則)
- 技術面:「動作経済の4原則」を用いて、論理的に楽な方法を提示する
「気合で頑張れ」「意識を変えろ」という精神論だけでは、現場は疲弊し、活動は定着しません。
正しい理論と、人間の心理に基づいた進め方こそが、5S成功のカギです。