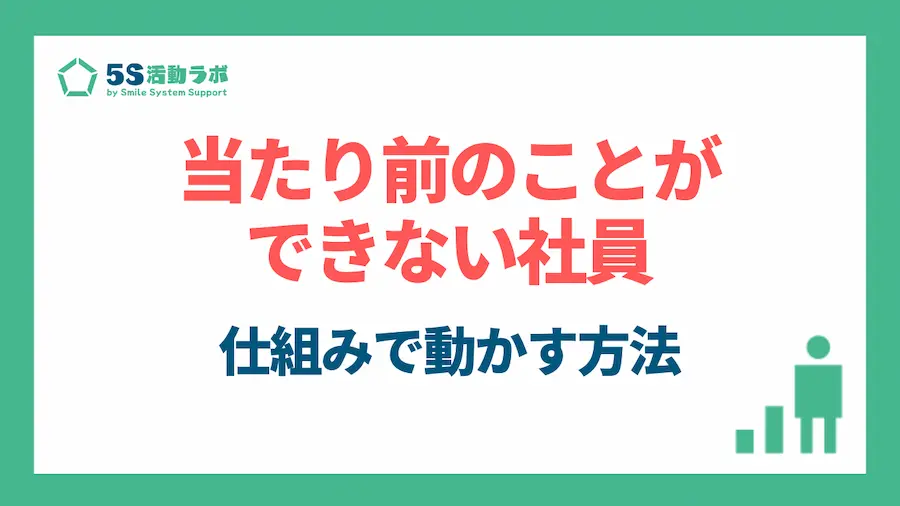
どこの会社でも尽きない「社員教育」の悩み。
特に経営者や管理職の方からよくお聞きするのが、次のような嘆きです。
「そんなこと、言わなくても当たり前だろ?」
「なんでこんな簡単なことができないんだ?」
挨拶をする、使った物を元の場所に戻す、報告をする…。
社会人として「できて当然」と思うことができない部下を見ると、どうしてもイライラしてしまいますよね。
しかし、実はこの問題を「本人のやる気や性格の問題」として片付けてしまうと、解決から遠ざかってしまいます。
今回は、この「当たり前のことができない問題」を、精神論ではなく「仕組み(5S)」で解決する方法について解説します。
もくじ
なぜ、部下は「当たり前」がわからないのか?
例えば、部下が作業台を片付けずに帰宅し、翌日そのまま作業を始めたとします。
上司からすれば「帰る前に片付けるのが常識(当たり前)」ですが、部下にとっては「明日も使うならそのままの方が効率的(という自分なりの当たり前)」かもしれません。
ここに、決定的な「認識のズレ」があります。
「常識のズレ」という落とし穴
育った環境、年代、過去の職歴によって、「常識」の定義はバラバラです。
特に現在は多様性の時代。自分にとっての「普通」が、相手にとっても「普通」であるとは限りません。
例えば「掃除」ひとつとってもそうです。
上司の思う「きれい」は「ピカピカでチリ一つない状態」かもしれませんが、部下の思う「きれい」は「大きなゴミが落ちていない程度」かもしれません。
この状態で「常識的に考えてきれいにしてくれ」と指示するのは、「私の頭の中にある基準を、テレパシーで読み取ってくれ」と言っているのと同じくらい、実は無理な要求なのです。
脳の仕組み:「正常性バイアス」と「決定疲労」
また、人間には「正常性バイアス」という心理作用があります。
明確な基準(定位置など)が決まっていないと、乱雑な状態を見ても「まあ、これくらいなら大丈夫だろう」と自分に都合よく解釈してしまいます。
さらに、モノの置き場が決まっていないと、片付けるたびに「どこに置こう?」と脳が判断しなければなりません。
これを繰り返すと脳が疲弊し(決定疲労)、最終的に「片付けるのが面倒くさい」「出しっぱなしでいいや」という行動をとるようになります。
つまり、社員がだらしないのではなく、「迷わせる環境」が社員をだらしなくさせているのです。
解決策:「暗黙知」を「形式知(ルール)」に変える
「当たり前のことができない」と嘆く前に、やるべきことがあります。
それは、社内の「暗黙の了解」を言葉にして、目に見える「基準(ルール)」にすることです。
「ちゃんとする」は禁止ワード
「きれいに片付ける」「常識の範囲で」といった曖昧な言葉(定性的な指示)は禁止しましょう。
誰が見ても〇か✕かが分かる基準(定量的な指示)に変えます。
❌ NG例(曖昧):
「デスクをきれいにして帰る」
⭕ OK例(具体的):
「退社時は、キーボードをモニターの下に入れ、卓上には何も置かない」
「床にはチリ一つ落ちていない状態にする」
ここまで具体的にして初めて、上司と部下の「当たり前」が統一されます。
これをビジネス用語では「標準化」と呼びます。
マクドナルドやスターバックスが、誰が働いても一定の品質を保てるのは、この「標準化」が徹底されているからです。
中小企業こそ、エース社員の能力に頼るのではなく、この「標準化」による仕組み作りが必要です。
5S活動とは「基準を守るトレーニング」である
弊社が指導している「5S活動(整理・整頓・清掃・清潔・躾)」は、単なるお掃除活動ではありません。
実は、この「社内の基準(ルール)をみんなで決めて、守れるようにするトレーニング」そのものなのです。
掃除ではなく「マネジメント」の練習
5S活動の本質は、職場をより働きやすくするために、「みんなでルールを決めて、それをみんなで守る」ことにあります。
「ハサミはどこに置くのが使いやすいか?」
「在庫はいくつになったら発注するか?」
こうした小さなことを一つひとつ話し合い、合意形成し、基準を作る。
このプロセスこそが、「自分たちで決めたことは守る」という自律的な社風を育てます。
小さな約束を守れない人は、大きな仕事も守れない
「ハインリッヒの法則」をご存知でしょうか。
1件の重大事故の裏には、29件の軽微な事故と、300件のヒヤリハット(小さなミス)があるという法則です。
「道具を元に戻さない」「スリッパを揃えない」といった小さなルールの無視は、やがて「納期遅れ」「品質不良」「労働災害」といった大きな問題に繋がります。
たかが片付け、されど片付け。
凡事徹底(当たり前のことを徹底してやる)こそが、最強のリスク管理であり、組織作りの基本なのです。
👉 ルールを守らない社員の対処法|叱責より仕組み!5Sで「守れる風土」づくり
「躾(しつけ)」=「無意識化」へのステップ
5Sの最後にある「躾(しつけ)」とは、決めたルールが習慣化し、「無意識にできる状態」になることを指します。
これを実現するためには、2つのポイントがあります。
1. ルールを形骸化させない「チェック機能」
人間は弱い生き物です。一度決めたルールも、放っておけば3日で元通りになります。
定着させるには、「チェックシートによる定期点検(パトロール)」が必須です。
できていない時は、人格を否定して叱る必要はありません。
「基準と違っていますよ」と事実を伝え、なぜ守れなかったのか(仕組みに無理がないか)を一緒に考えるだけで十分です。
「人を責めるな、仕組みを責めろ」が鉄則です。
2. 社長・上司が一番の「手本」になる
最も重要なのが、リーダーの振る舞いです。
「俺は社長だからいいんだ」と例外を作った瞬間、組織は崩壊します。
「言動一致」こそが信頼の証です。
上司が率先してルールを守り、楽しそうに取り組む姿を見せれば、部下は自然とついてきます。
逆に、上司が守らないルールを部下が守ることは、絶対にありません。
👉5Sの「躾」に違和感?誤解されがちな「躾」の本当の意味とは
まとめ:イライラする前に「仕組み」を作ろう
「当たり前のことができない社員」に悩んだら、まずは自社に「当たり前の基準」があるかを見直してみてください。
- 挨拶の基準はありますか?
- 整理整頓の基準はありますか?
- 報告のタイミングの基準はありますか?
もし、それが「暗黙の了解」になっているのなら、5S活動を通じて「明文化」していくことをお勧めします。
基準ができれば、人は必ず動けるようになります。
「どうやって社内の基準を作ればいいかわからない」「社員を巻き込む方法が知りたい」という方は、ぜひ弊社の5Sセミナーをご検討ください。
バラバラだった社内のベクトルを整え、自律的に動く組織作りの基礎を学んでいただけます。

