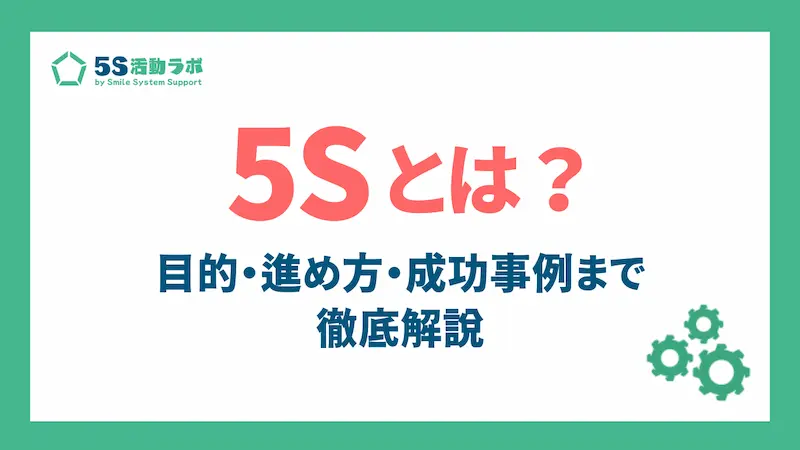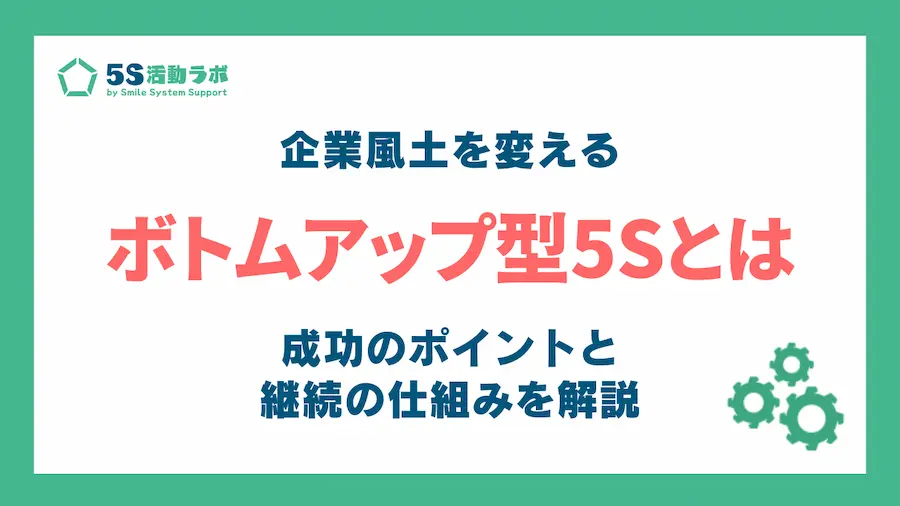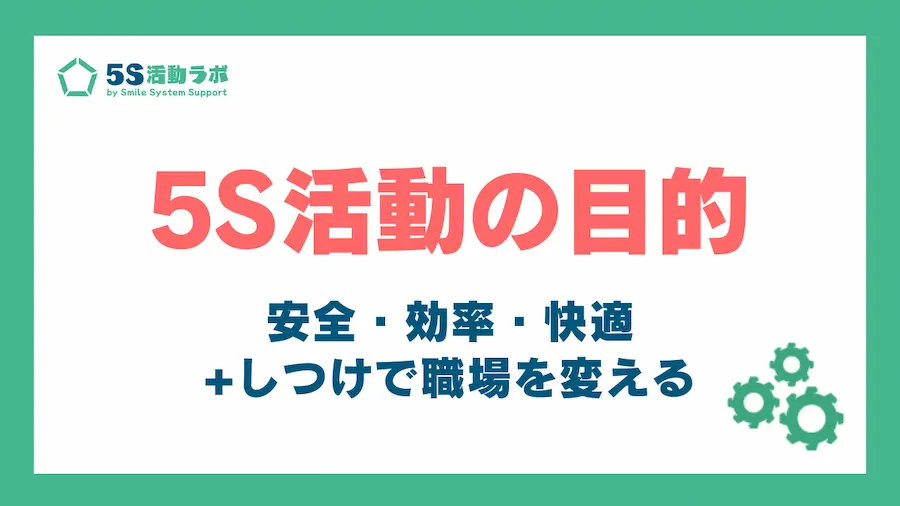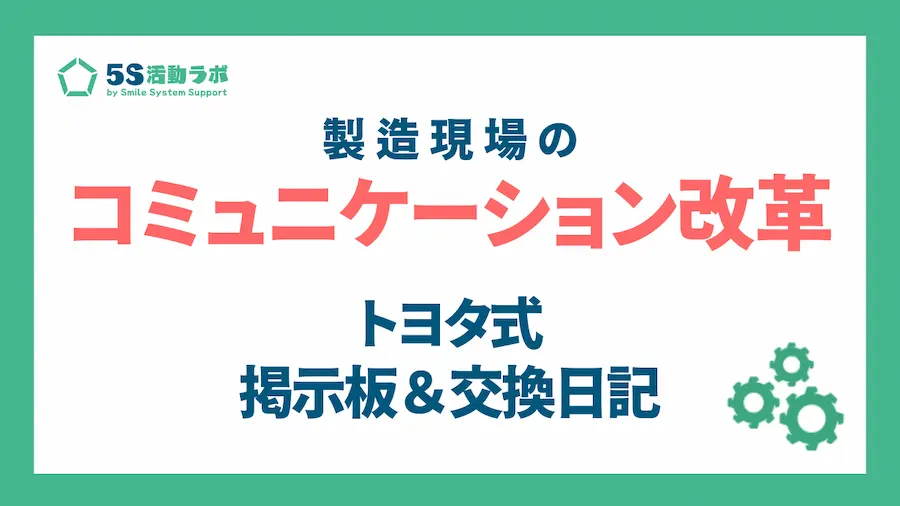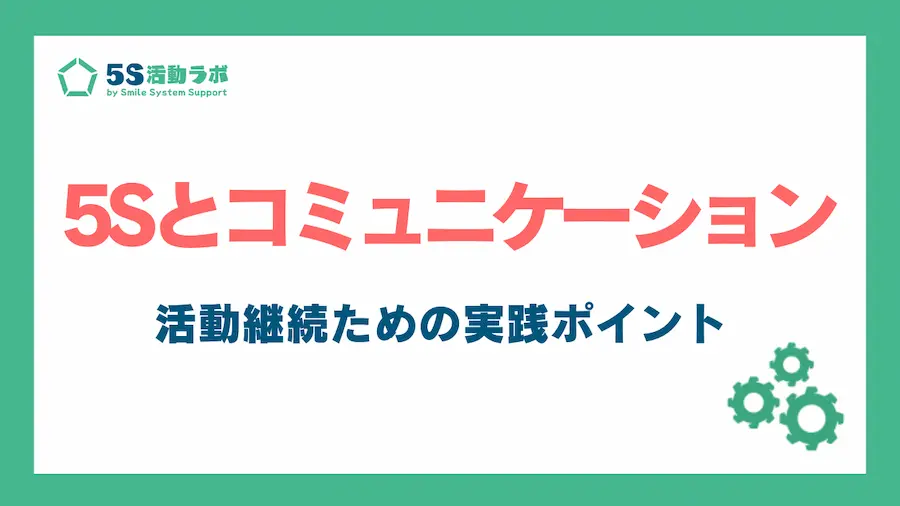
5S活動を導入しても「続かない」「定着しない」と悩む会社は少なくありません。
その原因の多くは、整理整頓や清掃そのものではなく、コミュニケーション不足にあります。
「社員はどんな点で悩んでいるのか?」という経営者の問いに対して、現場から最も多く聞かれるのは 「やらされ感」 です。上司が指示を出し、社員が黙って従う――これでは改善の文化は育ちません。
本来、5Sは「片付けさせられる活動」ではなく、社員が自分たちでルールを決め、職場をより良くしていくための活動です。そのためには、日々の声かけや話し合いを通じて意見を引き出し、共有し、相談できる仕組みが欠かせません。
この記事では、5Sとコミュニケーションの関係を整理しながら、やらされ感をなくし、主体的な改善が生まれる職場をつくるための実践ポイントを紹介します。
もくじ
なぜ5Sにコミュニケーションが必要なのか
5S活動を社内に定着させ、継続的に成果を出すために欠かせないもの――それがコミュニケーションです。
多くの経営者が口にされる疑問に「社員は5S活動のどんな点で悩んでいるのか?」というものがあります。
実際に現場で聞かれる声の中で最も多いのは、「やらされ感で取り組んでいる」という悩みです。
本来、5Sは「片付け」や「掃除」を強制される活動ではありません。
職場を安全にし、効率を高め、より快適に働けるようにするために、社員自身が考え、意見を出し合い、ルールを決めていく取り組みです。
しかし、コミュニケーションが不足すると、その意義が正しく共有されず、ただの作業に感じられてしまいます。
だからこそ、5Sを「文化」として根付かせるには、社員一人ひとりの声を引き出す仕組みと、意見を尊重し合うコミュニケーションが欠かせないのです。
こちらもCHECK
-

5Sとは?職場改善の基本を徹底解説!目的・進め方・成功事例をわかりやすく紹介
はじめに:トヨタ発祥の「5S活動」で職場を変える 現代の企業や組織が抱える課題には、業務効率の低下や安全性の欠如、社員育成や社内コミュニケーションの問題など様々です。これらを解決するための強力なアプロ ...
続きを見る
トップダウンの取り組みが招くコミュニケーションのすれ違い
5S活動の現場では、「上司が勝手に進めてしまう」ことによるすれ違いが少なくありません。
ある企業のセミナーに参加した社員さんがこう言われました。「僕が一番5S活動に協力しないから、このセミナーに参加させられたんですよ」
一見すると冗談のように聞こえますが、この言葉には“やらされ感”がにじんでいます。その背景にあるのは、トップダウンで進められる5S活動です。
例えば、現場を使っていない上司が独断で工具の定位置を決めてしまう。形跡管理を良かれと思って導入したものの、実際に使う社員にとっては効率が悪く、かえって使いづらくなる…。
社員にとっては「相談もなく勝手に変えられた」という不満が残り、改善への意欲が削がれてしまいます。
一方、上司からすると「もっと意見を言ってほしい」「なぜ自主的にやらないのか」と思うのですが、社員側は“相談してもどうせ変えてもらえない”と感じてしまう。こうしたすれ違いが続くと、せっかくの5S活動も「指示されたことをやるだけ」の活動に変わってしまいます。
この悪循環を断ち切るには、まず現場の声を聞き、共に考えるコミュニケーションが欠かせません。上司の思い込みだけで進めるのではなく、社員と一緒に仕組みを作る姿勢が、5Sを定着させる第一歩なのです。
こちらもCHECK
-

なぜボトムアップ式5Sが組織を変える?成功のポイントと継続の仕組みを解説
「すばらしい経営戦略があるのに社員が自分で動いてくれない」。これは多くの経営者が抱える根深い悩みです。この問題の本質は社員の能力ではなく、戦略の実行を阻害する「企業風土」にあります。 この企業風土を根 ...
続きを見る
5S活動とコミュニケーションの関係
5S活動は「整理・整頓・清掃・清潔・しつけ」という5つの行動を積み重ねていく取り組みですが、その根底には「人と人との関わり」があります。安全で効率的、快適な職場づくりは、ルールや仕組みだけでは成り立ちません。日常の声かけや意見交換といったコミュニケーションによって、初めて定着していくのです。
もしコミュニケーションが不足すれば、5Sは単なる「掃除」や「片付け」の活動に矮小化されます。社員にとっては「指示されたからやる」だけの仕事となり、やがて形骸化してしまうでしょう。反対に、話し合いながら進めることで「自分たちでルールを決めている」という実感が生まれます。その実感こそが、活動を継続させる原動力になります。
つまり、5S活動におけるコミュニケーションとは、「指示待ち」から「自分たちで改善する文化」へ転換させるための土台です。社員が主体的に関わるからこそ、小さな改善が積み重なり、やがて会社全体の風土を変える力に育っていきます。
こちらもCHECK
-

5S活動の目的とは|安全・効率・快適、そして躾で職場を変える
5Sとは、整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字を取った、職場改善の基本活動です。5Sとは何か?はこちらの記事で解説しています。 本記事では、その中でも多くの企業が最初に直面する疑問である「5S活動の目的 ...
続きを見る
コミュニケーションの基本3要素
5S活動を円滑に進めるには、ただ「話し合う」だけでは不十分です。情報を正しく伝え、共有し、相談し合うという流れを仕組みに落とし込むことが大切です。その基本となるのが、「連絡・共有・相談」の3要素です。
連絡:事実を正しく、漏れなく伝えること。
例えば「今日からこの道具の置き場所が変わります」といった情報は、タイミングを逃すと混乱を招きます。連絡の精度が低いと、作業のミスや無駄が生じやすくなります。
共有:情報を全員で持ち合うこと。
一部の人だけが知っている状態では、チームとしての改善が進みません。掲示板やチャットツールを使って「誰でも見られる形」で共有することが重要です。
相談:改善や意思決定につなげること。
「こうしたらもっと効率的になるのでは?」という現場の声を吸い上げる場をつくることで、社員の主体性が育ちます。相談が機能すると、現場から自然に改善提案が生まれるようになります。
この3要素はどれも欠けてはいけません。連絡だけに偏ると「一方通行」になり、共有が弱ければ情報格差が生まれ、相談がなければ改善が止まってしまいます。5Sを単なる作業で終わらせず、組織を前進させる活動にするためには、この3要素を意識したコミュニケーション設計が不可欠なのです。
5Sを支える具体的なコミュニケーションの場と仕組み
5S活動を定着させるには、自然にコミュニケーションが生まれる「場」と、誰でも理解できる「仕組み」が欠かせません。日常の中で対話や情報共有を仕組み化することで、“やらされ感”のない自発的な5Sが実現できます。
朝礼や短時間ミーティング
1日の始まりに数分の朝礼を設けるだけで、全員が共通の情報を持ち、作業のズレを防げます。特に「今日どこを重点的に整理するか」「今月の改善点を確認する」といった内容を扱うと、5Sが業務と直結した実感を持てます。大掛かりな会議でなく、短く・具体的に・全員が話せる場を意識するのがコツです。
掲示板や見える化ツール
5S専用の掲示板やホワイトボードを使えば、活動のルールや進捗が一目でわかります。「今月の改善報告」「新しいルール」「改善提案一覧」などを見える化することで、口頭だけでは伝わらない情報が共有され、周知徹底がスムーズになります。
報連相の仕組み化
「報告・連絡・相談」を仕組みに落とし込むことも重要です。口頭だけでは抜け漏れが起こりやすいため、簡単な記録やチャットツールで補完します。特に報告内容を共有化し、相談したことが残る仕組みを整えると、同じ問題が繰り返されず、改善スピードが上がります。
こうした「場」と「仕組み」があって初めて、社員一人ひとりの声が自然と集まり、5Sの活動が広がっていきます。
こちらもCHECK
-

製造現場コミュニケーション改革!トヨタ式掲示板・交換日記で現場が動く
「社内SNSやチャットツールを導入したのに、現場の空気は変わらない――。」 多くの製造業や現場部門では、そんな“デジタルコミュニケーションの限界”を感じています。 職場コミュニケーション ...
続きを見る
社員主体を育むディスカッション
5S活動を「やらされるもの」から「自分たちでつくるもの」に変えるために効果的なのが、ディスカッションの場を設けることです。
私たちの研修でも、実際の作業よりも“話し合い”に多くの時間を割いています。社員全員が集まり、小グループに分かれて「今の職場の問題は何か」「どんな改善ができるか」を出し合う。さらに、そこで出た意見をもとにルールを決め、全員で納得したうえで進める。こうしたプロセスを踏むと、誤解やすれ違いがなくなり、自然と前向きに活動できるようになります。
特にこれまでディスカッションの習慣がなかった職場では、その効果は大きく現れます。最初は口数の少なかった社員も、対話を重ねることで意見を言えるようになり、普段のコミュニケーションも活発になります。さらに、「自分の意見が職場を変える」という実感が、次の改善意欲につながっていきます。
つまり、ディスカッションは単なる話し合いではなく、主体性を育み、社内の風土を変える仕掛けです。5Sを通じて社員が自ら考え、話し、決めていく習慣がつけば、活動は長く続き、会社全体に前向きな文化が広がります。
コミュニケーションを活性化させるポイント
ディスカッションや会議を設けても、「結局、意見が出ない」「上司だけが話して終わる」という状態では、5Sの成果にはつながりません。社員が安心して意見を出せる雰囲気をつくることが大切です。
否定しない姿勢
せっかく出た意見を頭ごなしに否定すると、次から誰も発言しなくなってしまいます。まずは「そういう考え方もあるね」と受け止め、事実として認めることから始めましょう。否定せずに受け止めるだけで、社員は「ここでは話しても大丈夫だ」と感じられるようになります。
オープンクエスチョンで引き出す
「意見はありませんか?」ではなく、「このやり方だとどこがやりにくいですか?」「もっと良くするには何が必要でしょうか?」と問いかけると、社員は考えざるを得なくなります。具体的なオープンクエスチョンは、意見を引き出し、考える力を育てます。
コーチングスキルの活用
承認・傾聴・質問。この3つのコーチングスキルを意識するだけで、場の雰囲気は大きく変わります。
- 承認:小さな改善でも「いいね」と認める。
- 傾聴:相手の話を遮らず、最後までしっかり聴く。
- 質問:さらに考えを深めるための問いを投げる。
この積み重ねが、社員の自信と主体性を育て、前向きなコミュニケーションを定着させていきます。
FAQ:5Sのコミュニケーションに関するよくある質問
Q. 5S活動を浸透させるには、なぜコミュニケーションが重要なのですか?
5Sは「指示されたことをやる活動」ではなく、「自分たちでルールを決めて守る活動」です。社員同士が意見を出し合い、改善策を共有することで、やらされ感がなくなり主体性が育ちます。その土台になるのが日常的なコミュニケーションです。
Q. 5S専用の掲示板やホワイトボードには何を掲示すべきですか?
A. 「今月の重点エリア」「改善提案一覧」「新しいルール」など、全員が一目で理解できる情報を掲示すると効果的です。進捗状況や成功事例を見える化することで、社員のモチベーションも高まります。
Q. 会議で意見が出ないとき、どう質問すればよいですか?
「意見はありますか?」ではなく、「どこがやりにくいですか?」「もっと効率を上げるには何が必要ですか?」など具体的なオープンクエスチョンを投げかけると発言が生まれやすくなります。
Q. コーチングスキルは5S活動にどう役立ちますか?
コーチングの基本である「承認・傾聴・質問」は、社員の意欲を高める力があります。小さな改善でも認め、相手の話を最後まで聴き、さらに考えを深める質問をすることで、前向きなコミュニケーションが定着します。
Q. 5Sのディスカッションはどのくらいの頻度で行うべきですか?
月に1回程度の定例ディスカッションが理想です。短時間でも定期的に振り返ることで、改善の習慣が身につき、活動が途切れなく続きます。
Q. 小集団活動(グループ討議)は何人くらいでやるのが効果的ですか?
A. 4〜6人程度が最適です。大人数では発言が少なくなりがちですが、小集団なら一人ひとりの意見を引き出しやすく、責任分担もしやすくなります。
まとめ:5Sを通じて生まれる「見て見ぬふりをしない風土」
5S活動を本当に社内に根づかせるには、道具や書類を整理整頓するだけでは足りません。社員同士が声をかけ合い、相談し合い、改善を共有する――その積み重ねが職場を変えていきます。
トップダウンで進めるだけでは「やらされ感」が強まり、せっかくの活動も形骸化してしまいます。反対に、社員の声を聞き、ディスカッションを通じてルールを一緒に作っていけば、活動は自然と自発的になります。コミュニケーションは、やらされ感をなくし、社員の主体性を引き出す最大の鍵なのです。
5Sを通して社員が日常的に「気づく」「声をかける」「改善する」ことを繰り返せば、職場には「見て見ぬふりをしない風土」が育ちます。その風土こそが、安全で効率的、そして快適な会社を支える土台になります。