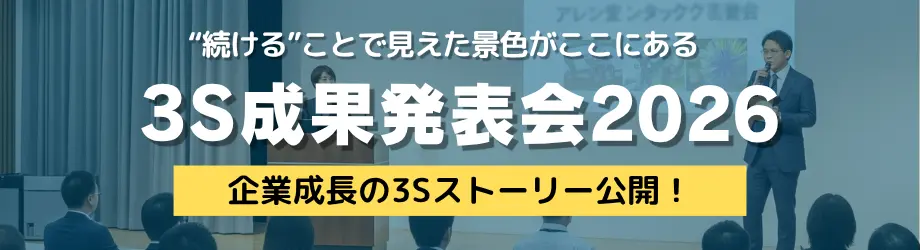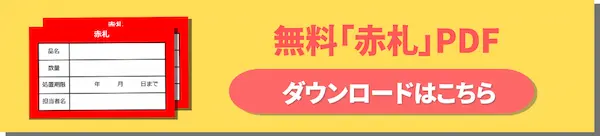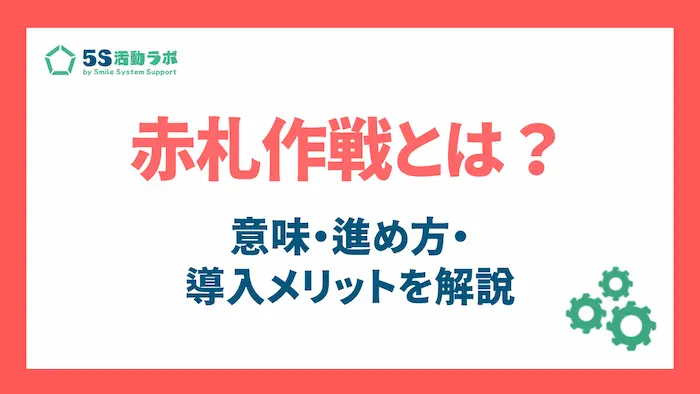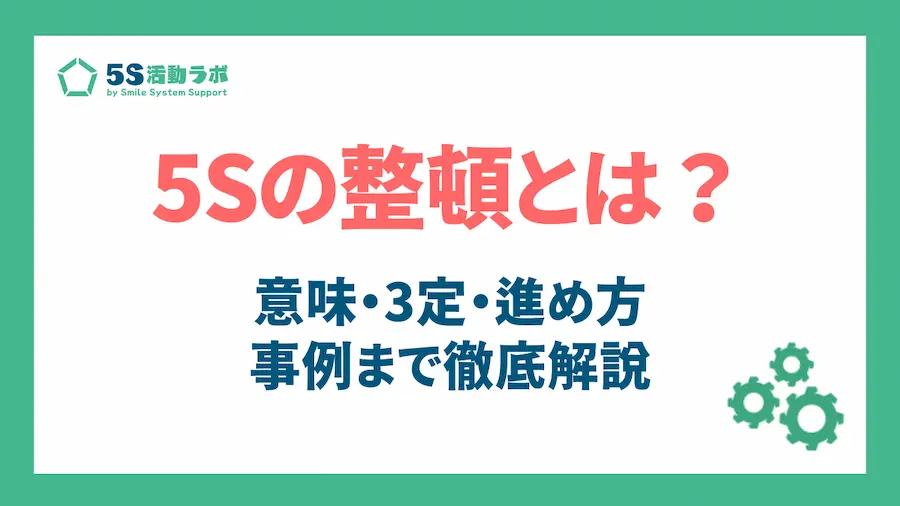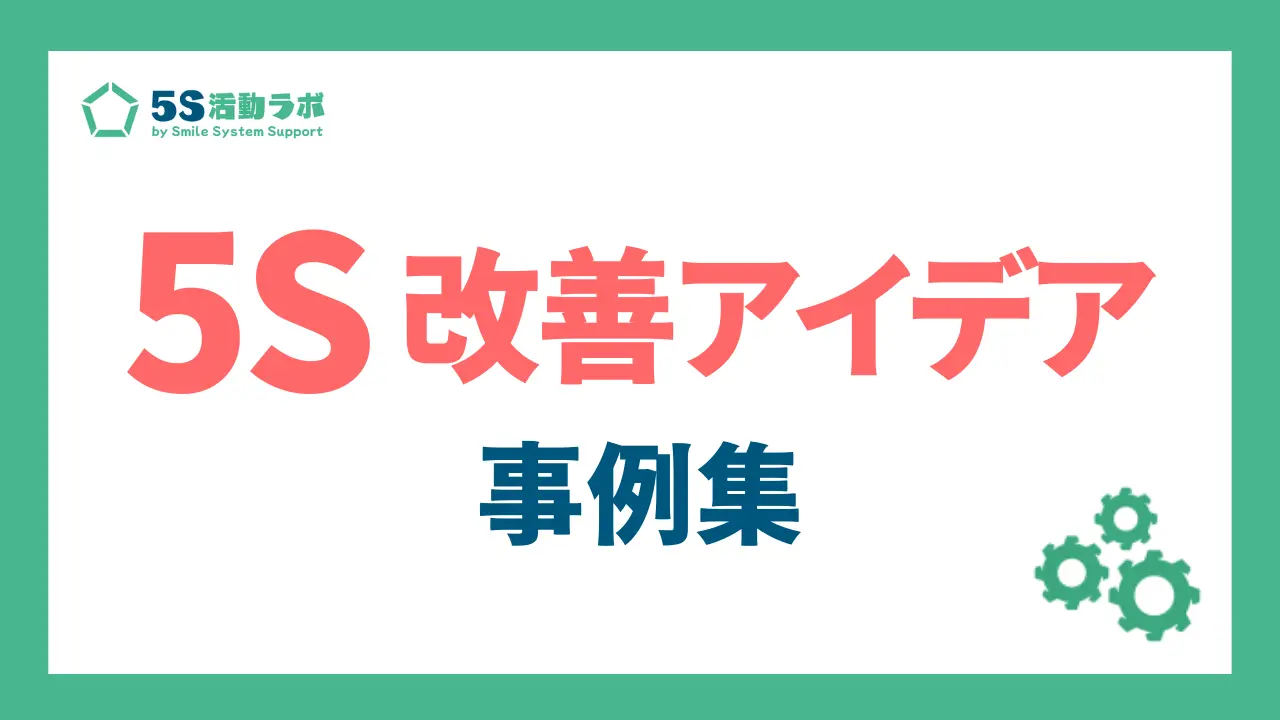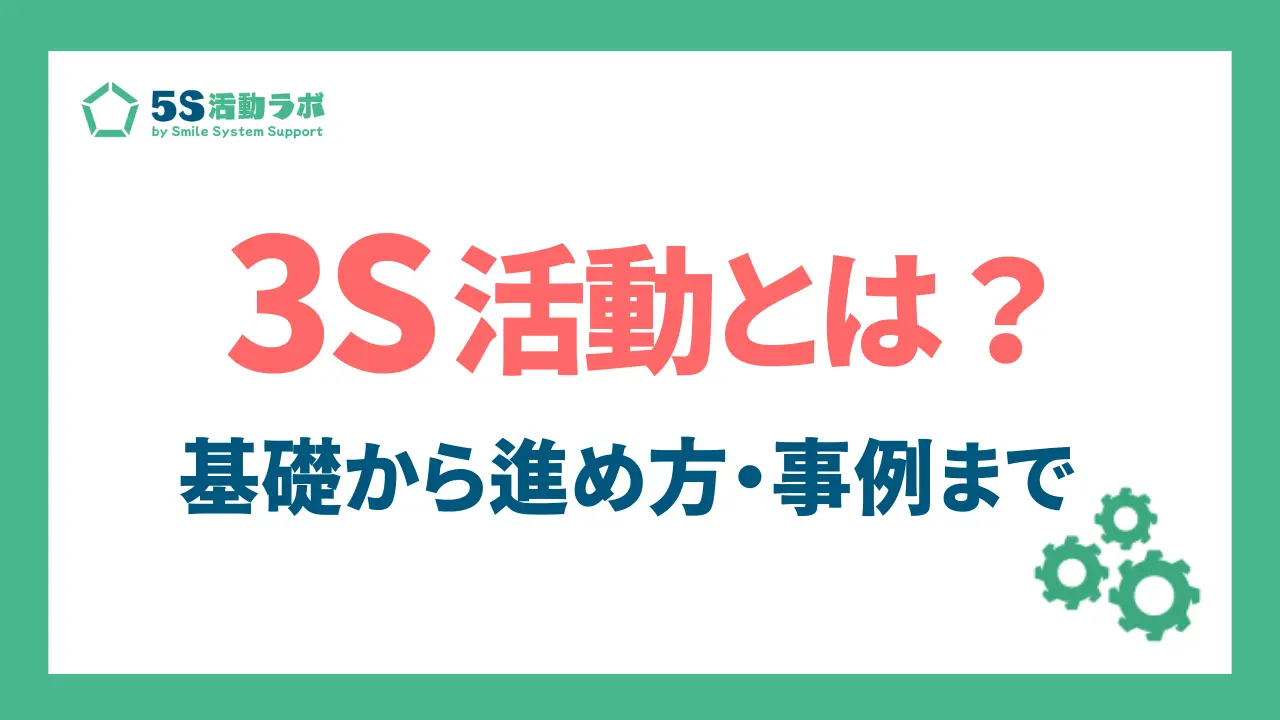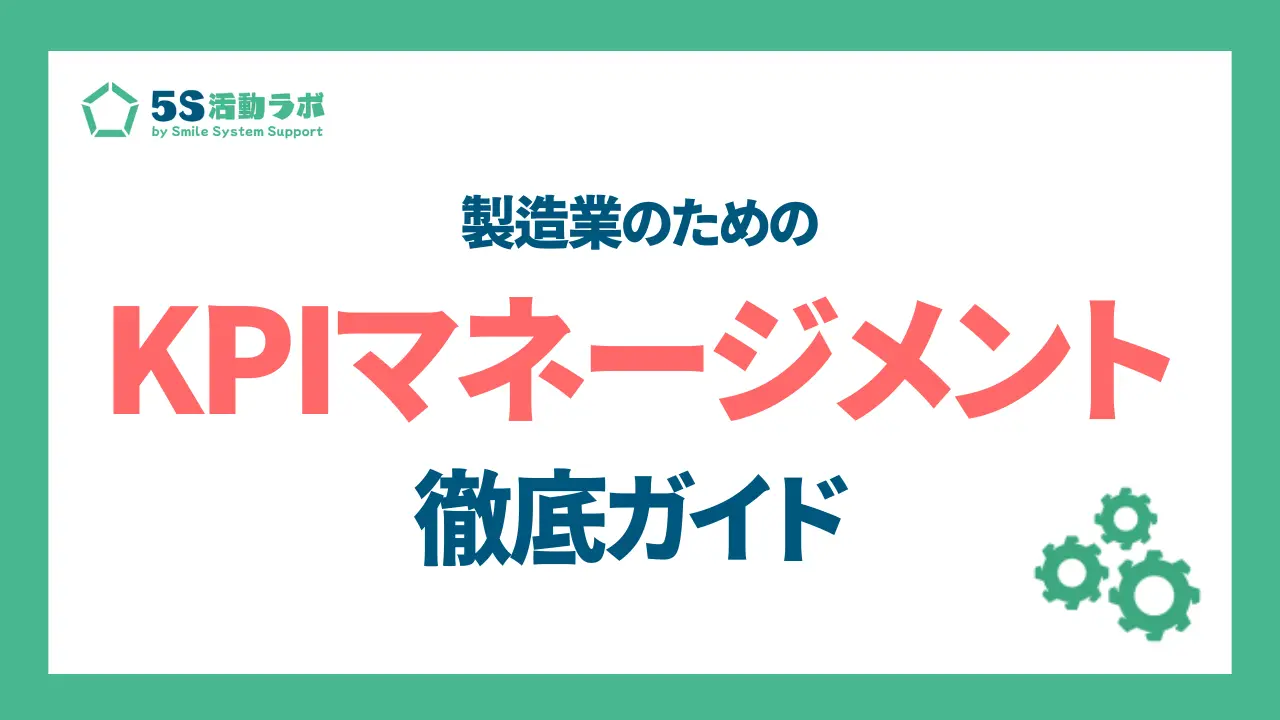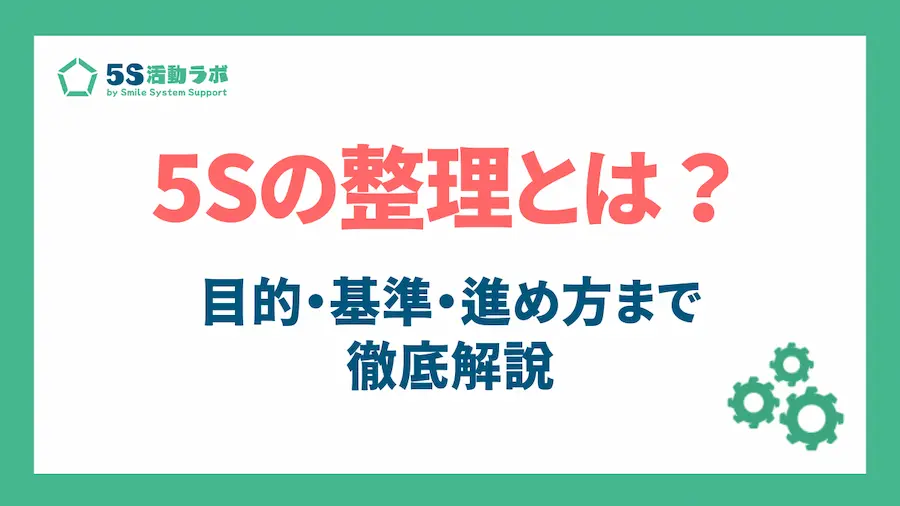
5S活動(整理・整頓・清掃・清潔・しつけ)の中で、最初のステップにあたるのが「整理」。
本記事では、5Sの中でも「整理」に特化し、その目的・基準・進め方・よくある失敗と対策までをわかりやすく解説します。
- 「何から始めればいいかわからない」
- 「捨てる・残すの基準がバラバラ」
- 「整理してもすぐに元に戻ってしまう」
そんな悩みを持つ職場に向けて、5S活動の最初の一歩である“整理の正しい進め方”を実践的に紹介していきます。
整理は単なる片づけではありません。
不要なモノを見極めて捨てることで、価値ある業務に集中できる環境をつくる――それが5Sにおける整理の本質です。
この記事を通じて、整理の考え方とステップを正しく理解し、ムダを削ぎ落とした「使いやすい職場づくり」を一緒に目指しましょう。
5S活動全体について知りたい方はこちら
もくじ
5S活動の整理とは?意味と目的
5S活動の第一ステップが「整理」です。
しかし「整理」という言葉は、日常的には「片づける」「整える」といった意味合いで使われることが多く、5Sにおける本来の意味とは少しズレがあります。
5S活動における「整理(Sort)」の意味は、「要るもの、要らないもの、急がないものを分けて、不要なものを徹底的に捨てること」を指します。
つまり整理の目的は、ただ整えるのではなく、企業にとって価値を生まないものを見極め、排除することによって、本当に必要なものだけが残る状態をつくることです。
これは単なる美化や片づけではなく、業務効率・安全性・生産性に直結する、本質的な取り組みといえます。
また、単に捨てるだけでは整理は完了しません。
「捨てる・捨てない」のルールを明確にし、それを維持する仕組みを整えることが、整理を“持続可能な仕組み”にしていく鍵となります。
整理の区分:モノを3つに分けて見極める
整理の第一歩は、モノを見極めること。
「要るモノ」「要らないモノ」「急がないモノ」の3つに区分して、それぞれの意味を明確にすることで、捨てる・残すの判断がしやすくなります。
この区分けは、整理を“感覚”で進めず、“基準”で判断するための重要な考え方です。
要るモノ(=生品)
「要るモノ」とは、日々の業務の中で頻繁に使っているモノのことを指します。
たとえば、毎日使う道具や、1週間に何度も出番のある備品などが該当します。
このように、使用頻度が高く、手元や作業エリアにあるべきモノは「生きているモノ」として「生品」と呼ばれます。
例:毎日使う工具、定期的に使う帳票、日報記入用の文具など
急がないモノ(=休品)
「急がないモノ」は、必要ではあるが、使用頻度が低いモノです。
たとえば、「半年に一度」「年に一度」しか使わないが、法的・業務的には保管が必要な資料や部品などです。
これらは「休んでいるモノ」として「休品」と呼ばれ、捨てるのではなく、保管ルールを明確にして整理することが大切です。
例:年1回使う検査機器、稀に使う予備部品、保管義務のある書類
要らないモノ(=死品)
「要らないモノ」は、壊れて使えないもの、誰も使っていないもの、用途が不明なものなど、今後使う見込みがないものを指します。
このようなモノは、「死んでいるモノ」として「死品」と呼ばれます。
死品は見えないコストを生み出します。
「探す時間」「スペースの圧迫」「判断の遅れ」など、業務のムダを生む原因になるため、徹底的に排除することが整理の本質です。
例:壊れた機器、古い型式の部品、用途不明の備品、誰も使わない道具
整理の基準:モノの価値を見極める共通ルールを持つ
整理を進めるうえで最も重要なのは、「捨てる・残す」の基準を明確にすることです。
「要るモノ」は、日常業務で使っているモノなので、判断に迷うことはあまりありません。
問題になるのは、「今すぐは使わないが、将来的には必要かもしれないモノ」。
こうした「急がないモノ」と「要らないモノ」の線引きが曖昧だと、「とりあえず残す」「そのうち使うかも」といった判断が積み重なり、いつの間にか職場がモノであふれてしまいます。
なぜ基準が必要なのか?
多くの現場で整理が進まない最大の理由は、「判断が人によってバラバラだから」です。
ある人にとっては必要でも、別の人にとっては不要。
こうした食い違いが起こる背景には、「残す・捨てる」の基準があいまいであるという問題があります。
そこで必要になるのが、「何をどの状態で残すか」という共通ルールです。
ルール化して初めて整理は機能する
大切なのは、これらの判断基準を個人の感覚に任せず、職場全体の共通ルールとして定めることです。
そして、それを“使う人全員”が理解し、守れるようにすることが整理の前提になります。
ルールがなければ、時間が経つにつれて判断がぶれ、モノは再び増えていきます。
「整理は一度やれば終わりではなく、ルールを通じて維持するもの」だという意識が欠かせません。
●基準は“現場で話し合って決める”もの
捨てるか残すかの判断は、単にモノの状態や使用頻度だけで決まるものではありません。
どの基準が適切かは、現場の業務内容や職場の事情によって大きく異なります。
だからこそ大切なのは、「使っている人たちが、自分たちの言葉でルールを決めること」です。
誰かが一方的に決めた基準ではなく、現場のメンバーが話し合いながら、「これは残そう」「これはもう使っていないよね」と意見を交わすこと。
その対話のプロセスこそが、職場にとって本当に納得感のあるルールを生み出します。
整理とは、モノを減らす作業ではなく、「何を大切に残すか」をみんなで決める行為です。
基準・ルールづくりの中にこそ、5Sの本質があります。
整理の進め方:小さく始めて、ムダを見える化する
◆なぜ整理から始めるのか?
5S活動を始めるとき、多くの人が最初に迷うのは「何から手をつけるか」です。
その答えは――まずは整理、つまり“要らないモノを捨てること”から始めることです。
「要るモノ」と「要らないモノ」が混ざった状態でいくら整えても、使いやすい職場にはなりません。
例えば、工具や備品の中に不要なモノが混在していると、必要なモノを探す時間や労力が増え、作業効率を大きく下げてしまいます。
一方で、不要なモノを徹底的に取り除けば、残るのは本当に使うモノだけ。
それだけで、使いやすさ・探しやすさ・整えやすさが一気に高まります。
また、整理ができていないと、その後の整頓(定位置・定量管理)や清掃もうまく機能しません。
だからこそ、5Sは「整理」から始めるべきなのです。
小さなエリアから始めよう
整理を進めるとき、いきなり大がかりに始める必要はありません。
むしろ、最初は「引き出し1段」「棚の一区画」など、小さなエリアから始めることが成功のポイントです。
特にモノが多い職場では、一気に全体を整理しようとすると手が止まってしまいがちです。
まずは、今いる現場で「すぐに取り組める範囲」から手をつけて、整理の感覚と基準を体感するところから始めましょう。
1つひとつのモノと向き合う
エリアを決めたら、そこにあるモノを一つずつ手に取り、「要るモノ」「急がないモノ」「要らないモノ」に分類していきます。
ここで重要なのは、一つひとつのモノに対して、「本当に必要かどうか?」を問い直す姿勢です。
最初は迷うかもしれませんが、分類を続けるうちに、意外なほど多くの“要らないモノ”が職場にあることに気づくはずです。
赤札作戦で“不要かもしれないモノ”を可視化する
整理を実施するうえで役立つのが、5Sの定番ツールである「赤札」です。
これは「不要かもしれない」と感じたモノに対して、処置期限などを記入した赤い札(ラベル)を貼り付けるものです。

- 「勝手に捨てることはできない」
- 「本当に不要かどうかの判断に迷う」
こうした状況でも、赤札を使えば“判断保留”の状態を一旦棚上げして、職場全体で共有・見える化することができます。
これを「赤札作戦」と呼び、不要品の整理を円滑に進めるための強力な仕組みとして、多くの現場で活用されています。
赤札には“期限”と“判断者”をセットで
赤札を使う際は、次の2点を必ずセットで運用しましょう。
- 処置期限を書く:いつまでに処分判断を行うのか明確にする
- 判断者を決める:上長や管理者が責任を持って捨てる・残すを判断する
これにより、曖昧な状態が長引くことを防ぎ、整理が確実に進みます。
ルールを決めて、現場で判断できる仕組みに
赤札を貼ったモノについて、今後も継続的に整理を行うためには、「処分のルール化」が欠かせません。
たとえば、
「1年間赤札が貼られたまま使用されなければ、自動的に処分対象とする」
といったルールを定めれば、いちいち上司の判断を仰がなくても、現場で自律的に判断できる整理体制が整います。
逆に、赤札を貼った後に使用されたモノは「急がないモノ」として整理し、必要なときにすぐ取り出せるように保管場所を明確にしておきます。
繰り返すことで、「必要なモノだけ」の職場に近づく
このようにして、整理→判断→ルール化→再整理を繰り返していくことで、職場からムダが減り、「必要なモノしか存在しない」快適で効率的な空間へと近づいていきます。
整理は1回で終わる作業ではありません。
判断と見直しを繰り返すことで、職場の価値基準そのものが洗練されていきます。
整理のよくある失敗とその対策
Q. どうしても捨てられないときは、どうすればいい?
A.「捨てる」ではなく「判断を保留する仕組み」を使いましょう。
迷うモノには赤札を貼り、処置期限を決めて一時保留にします。
さらに、「赤札が1年使われなければ処分」といったルールを決めれば、感情に頼らず整理が進みます。
捨てる勇気よりも、判断を先送りしない仕組みが大切です。
Q. 整理しても、しばらくするとまたモノが増えてしまいます…
A. 整理は“やりっぱなし”では維持できません。
「使っていないモノは処分」「赤札が1年貼られていれば自動処分」といったルールを決めて、定期的に見直す習慣を持ちましょう。
“維持の仕組み”を作ることが、整理のゴールです。
Q. 他の人のモノに勝手に手を出せないので、進みません…
A. 赤札で“判断の保留”と“共有”をしましょう。
勝手に捨てず、赤札を貼って「不要かも?」を見える化します。
処置期限を設け、上司や持ち主が判断する仕組みにすれば、協力して整理が進められます。
Q. 整理の判断が人によってバラバラです…
A. 判断基準を“職場で話し合って”決めましょう。
「半年使っていなければ処分候補」など、頻度や使用目的を軸に明確なルールを作ることで、感覚に頼らず判断できるようになります。
次は「整頓」へ――使いやすさをつくる次のステップ
「整理」は、職場から不要なモノを取り除くステップでした。
それに対して「整頓」は、必要なモノを“使いやすく配置する”ためのステップです。
いくら不要なモノを捨てても、必要なモノの場所や量がバラバラでは、ムダな探し物や手間は減りません。
次の記事では、5S活動における「整頓」の目的と進め方を、具体例とともに解説していきます。
整頓はこちら
-

5Sの整頓とは?意味・3定から進め方・事例・失敗対策まで徹底解説
5S活動の中で「整頓」は、整理の次に取り組むステップです。 単にモノを見た目よく並べるのではなく、「必要なモノを、誰でもすぐに取り出せる状態」にすることが整頓の目的です。 現場では「どこ ...
続きを見る
まとめ:整理とは、職場の価値観を見える化する行動
5S活動の第一ステップである「整理」は、ただの片づけやモノの削減ではありません。
「捨てる・残す」を通じて、職場が何を大切にしているのかを明らかにする、非常に本質的な取り組みです。
整理の過程では、「なぜこれを残すのか?」「これは本当に必要か?」という問いが自然と生まれます。
その問いこそが、職場にある曖昧さや思考のクセを“見える化”する機会なのです。
- 判断基準を言語化する
- 不要なモノを手放すルールを決める
- 維持する仕組みをつくる
こうした行動を積み重ねることで、整理は「考える職場づくり」そのものになります。
まずは小さく始めて、現場で“考える力”を育てていきましょう。