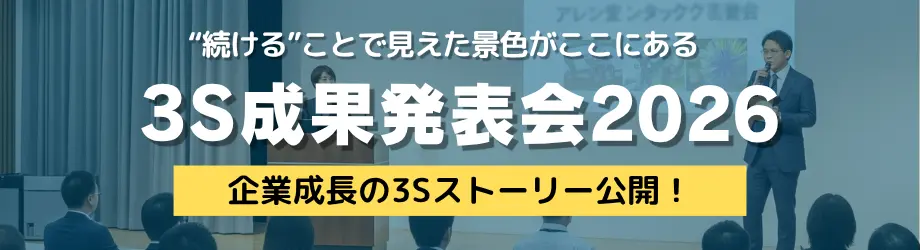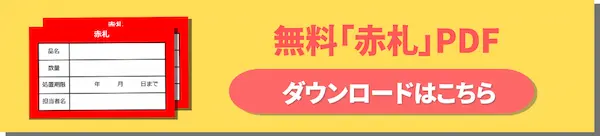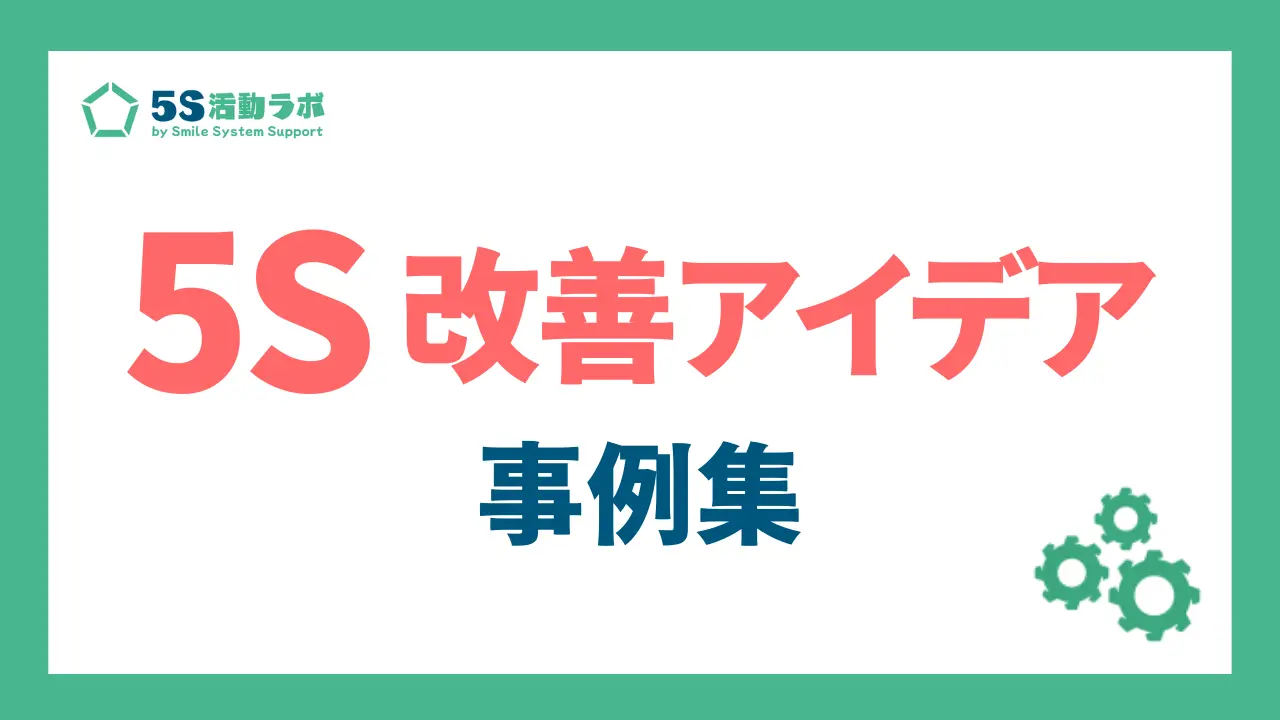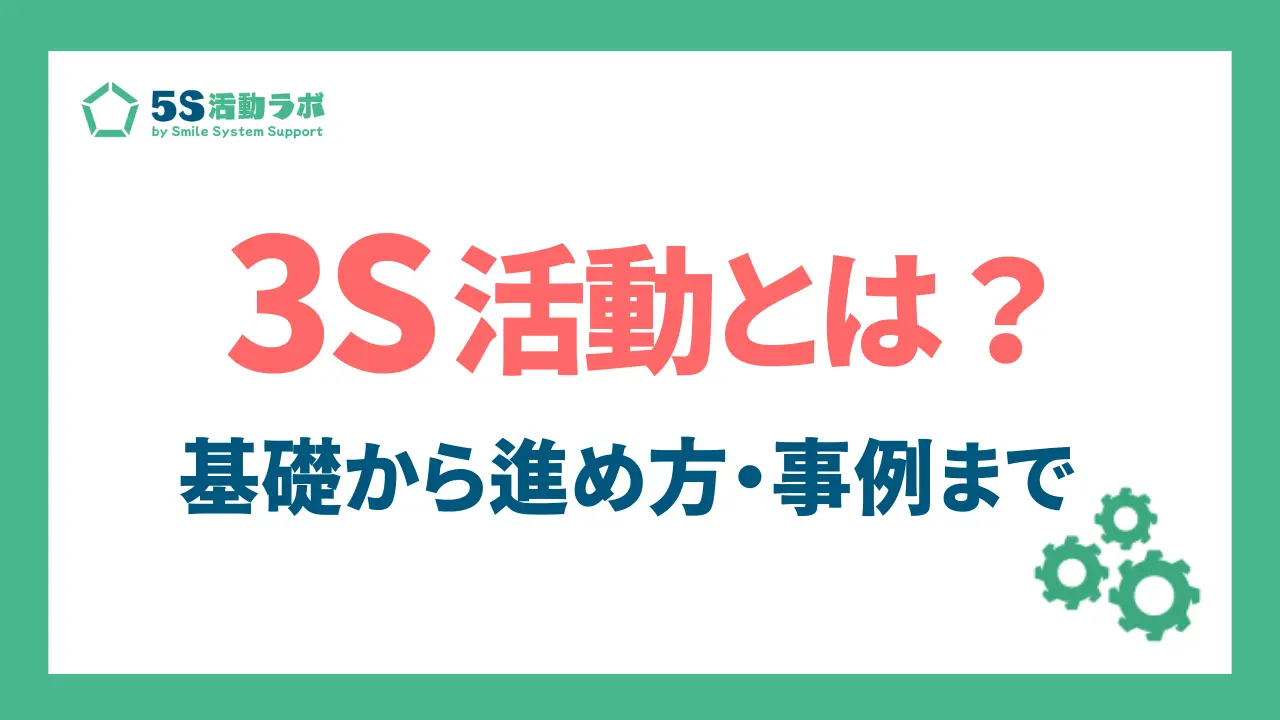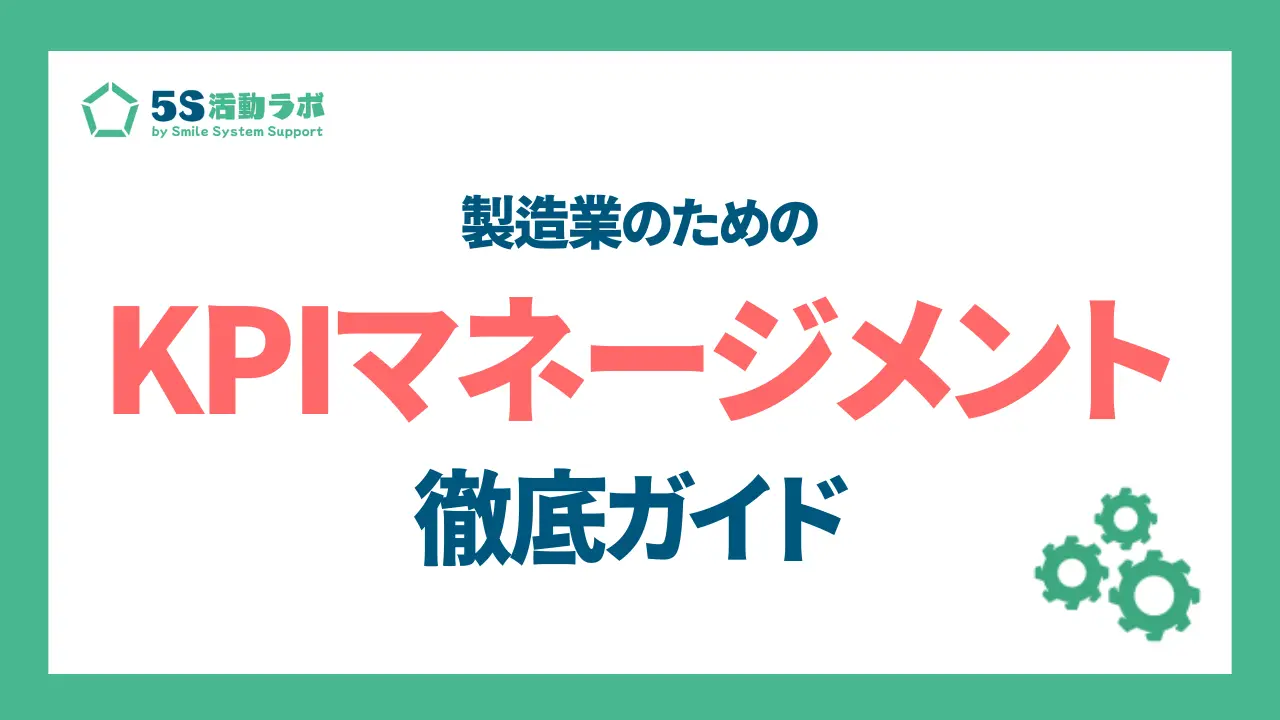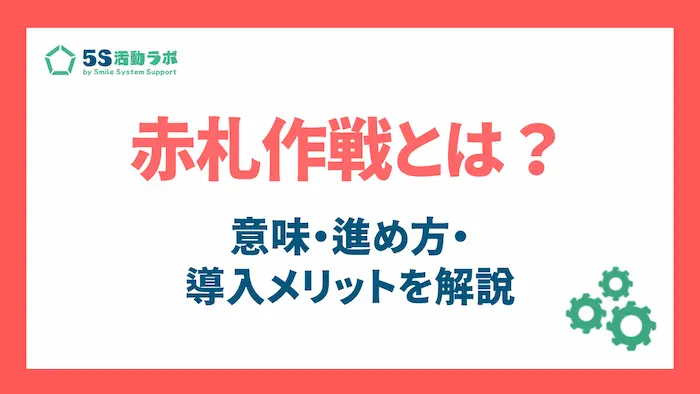
「赤札作戦」は、トヨタ生産方式(TPS)でも活用されている、5S活動の「整理」を徹底するための手法です。
不用品に赤い札を貼ることで、“必要・不要”を見える化し、職場のムダを明確にできます。
この記事では、赤札作戦の、初めての方にも分かりやすく解説します。
もくじ
赤札作戦とは?5S活動の第一歩を支える“見える化”の切り札
「整理」とは何か?整頓や清掃とは違う“捨てる勇気”
5S活動の第一歩である「整理」とは、「要るもの」と「要らないもの」を分け、要らないものを処分することを指します。
しかし実際の職場では、どれが必要でどれが不要なのか、判断に迷うことが多く、結果として“なんとなく残っているモノ”が溜まりがちです。
そこで導入されるのが「赤札作戦」です。
赤札とは?判断に迷うモノを“保留”しながら見える化する仕組み

赤札とは、「これは不要かもしれない」と感じたモノに一時的に貼る“判別札”です。
通常は赤い紙やラベルに以下のような情報を記入して対象物に貼り付けます。
- 品名・内容
- 担当者名
- 赤札を貼った日付
- 処分判断の期限
ポイントは、「迷ったら貼る」こと。
一人の判断だけではなく、後から上長やチーム全体で相談して判断できるようにするための保留の仕組みでもあります。
これにより、曖昧だった「要・不要の判断」が職場全体で共有され、意思決定が進みやすくなります。

なぜ「赤札」?名称に込められた意味と意図
赤札作戦で使われる「赤札」は、不用品などの判断に迷う物品を区別し可視化するために使われる赤い札から名づけられています。
不用品に赤い札、移動保管品に黄色の札を貼って分類する手法から、「赤札作戦」と呼ばれるようになりました。
赤は「危険」「注意」「停止」を示す色であり、不用品をこの色で目立たせることで「これは放置してはいけないものだ」と直感的に伝えます。
赤札作戦がもたらす、本質的な4つの効果
① 判断を保留する仕組みができる
「要るか、要らないか」――整理を進める中で、即座に判断できないモノは意外と多いものです。
赤札は、そういった判断に迷うモノを「いったん保留」にするための札です。
「迷ったら貼る」をルールにすれば、曖昧な判断を無理に迫ることなく、一時的に棚上げしながらも「放置しない状態」をつくることができます。
この仕組みがあることで、整理が止まらずに前へ進みます。
② 判断を共有できるようになる
赤札には、貼った日付・担当者・用途・処分期限などの情報を記入します。
これにより、「このモノは誰が貼ったのか?」「いつまでにどう判断するのか?」が誰の目にも明らかになります。
整理の判断を個人に閉じず、チームや上司も含めて共有・協議できるようになることで、属人的な整理判断から脱却し、納得感のある処分判断が可能になります。
③ モノの問題を“職場全体の課題”として可視化できる
赤札が貼られたモノは、どこに置いてあっても一目で「これは要注意だ」と分かります。
これにより、これまで「なんとなくそこにあるだけだったモノ」が、「考えるべき対象」として職場の中で共有されます。
「これはまだ必要?」「そもそも誰の持ち物?」といった対話と判断のきっかけが生まれるため、赤札は単なるラベルではなく、「問題提起のトリガー」として機能します。
④ 整理の継続と仕組み化を助ける
赤札を活用した整理手順をルール化すれば、「赤札 → 判断 → 処分 or 保管」というフローが職場に定着します。
この仕組みがあることで、整理が“その場かぎりの片付け”ではなく、定期的に見直し・処分を進めていく習慣として根づいていきます。
赤札は、単発イベントとしての整理ではなく、仕組みとして続く整理を実現するサポートツールなのです。
【実践編】赤札作戦の進め方|5ステップで簡単スタート
STEP1|基準を決める:「何を貼るか」のルールを明確に
まず最初に、「どんなモノに赤札を貼るか」という基準を職場で共有することが重要です。
たとえば:
- ◯ヶ月間使っていないモノ
- 複数あって明らかに過剰なモノ
- 誰の持ち物かわからないモノ
- 壊れている、または使いにくいモノ
など、明確な判断基準をあらかじめ設定することで、迷いなく赤札を貼ることができます。
STEP2|赤札を貼る:「迷ったら貼る」を徹底する
基準が決まったら、いよいよ現場での赤札貼りを一斉に実施します。
このときのコツは、「迷ったら貼る」「貼るかどうかを悩まない」こと。
目的は「処分」ではなく「見える化」なので、判断がつかないモノほど積極的に赤札を貼っていくのが正解です。
全員参加で取り組むことで、現場全体の意識が揃い、赤札作戦が単なるイベントではなく、職場改善のスタートラインになります。
STEP3|赤札リストを作る:貼ったモノの情報を記録する
貼った赤札の情報は、リスト化(一覧表)して管理します。
赤札には、以下の内容を記載しておくことで、後の判断がスムーズになり、記憶から抜け落ちるのを防ぐことができます。
- 品名(または写真)
- 貼付日
- 担当者名
- 理由(使用頻度・状態など)
- 処分期限または判断期限
このリストは、判断会議や報告の際に非常に役立ちます。
STEP4|判断・処分を実行する:ルールに従って動かす
赤札を貼ったモノは、作業の邪魔にならないように、最終的に一箇所にまとめて集約保管します。

この「赤札置き場」に集めることで、判断が漏れたり放置されるのを防ぎ、誰が見ても“今、処分対象のモノがここにある”と分かる状態を作れます。
その後、リストと照らし合わせながら、以下のように対応を決めます:
- 明確に不要と判断 → 処分
- まだ判断がつかない → 一時保管(期限つき)
- 使用が再確認された → 赤札を外して定位置へ戻す
このような判断とアクションをルール化しておくことで、赤札作戦は単なる“貼るだけ”で終わらず、整理の結果を確実に現場に反映させるステップになります。
STEP5|ルール化とPDCA:仕組みにして習慣化する
赤札作戦は、一度だけやっても効果は長続きしません。
毎月の5Sパトロール時に赤札を持参し活用するなど、職場の中で「赤札を貼る・判断する・処分する」流れをルールとして定着させることで、整理の習慣が根づいていきます。
また、赤札のテンプレートや運用ルールを文書化しておくことで、新しいメンバーにも浸透しやすくなります。
まとめ:赤札作戦は、職場を“動かす”仕組みづくり
赤札作戦は、モノに札を貼ることが目的ではありません。
本質は、要・不要の判断を見える化し、チームで共有し、行動につなげる“整理の仕組み”をつくることにあります。
これまで誰も触れなかった不要品に赤札を貼る。
それを見た誰かが、「これって本当に必要?」と問いを投げる。
そして現場全体で判断し、不要なモノが減っていく。
このサイクルが動き出したとき、職場は確実に変わり始めます。
赤札作戦は、特別なスキルや設備がなくてもすぐに始められる改善手法です。
まずは一つの棚、一つの引き出しからでも構いません。
小さな“赤札”の一手が、職場を動かす大きな一歩になります。
赤札テンプレート|すぐに使えるフォーマット無料配布中
赤札作戦を実施する際に、「赤札ってどんなフォーマットで作ればいいの?」「項目に何を書けばいいのか分からない」という声をよくいただきます。
当サイトでは、現場ですぐに使える赤札のテンプレート(フォーマット付き)を無料で提供しています。
A4サイズで印刷できるPDF版テンプレートをご用意していますので、下記リンク先よりダウンロードしてご活用ください。