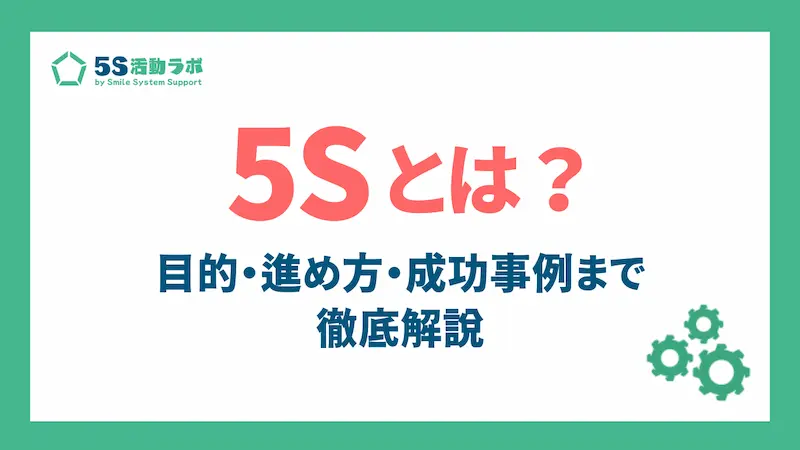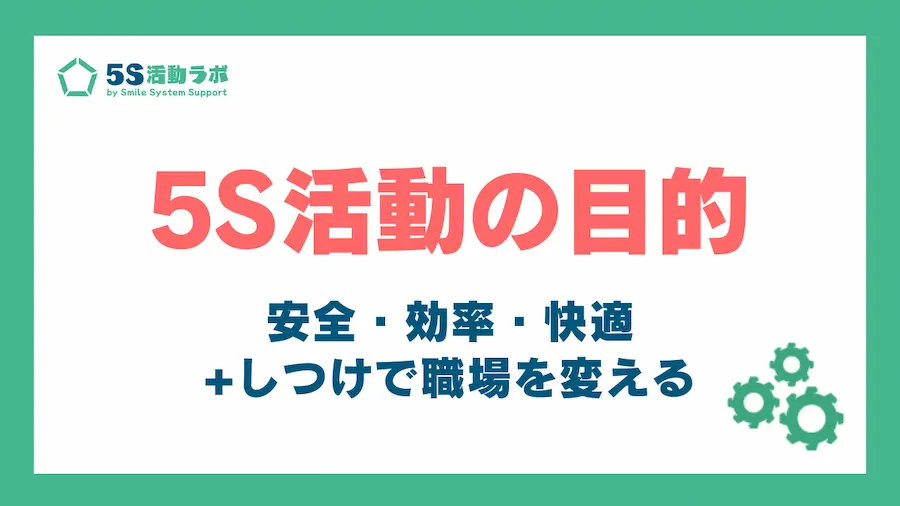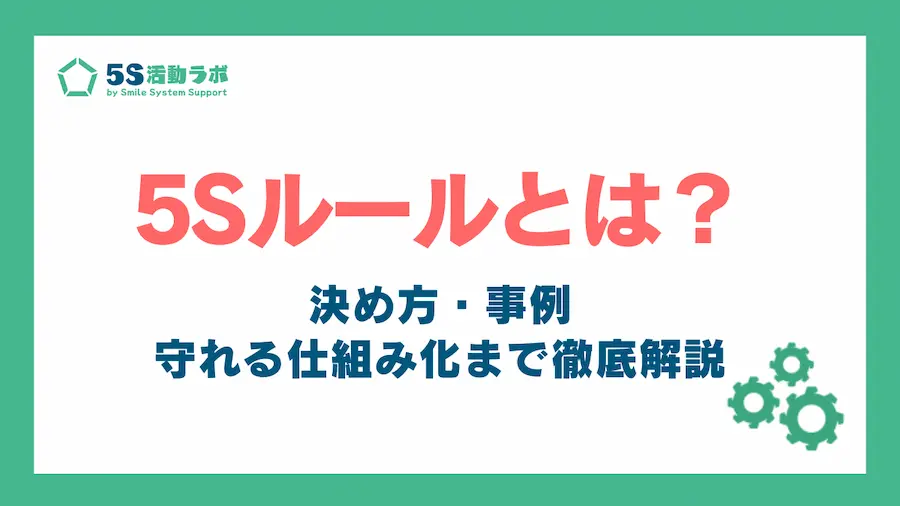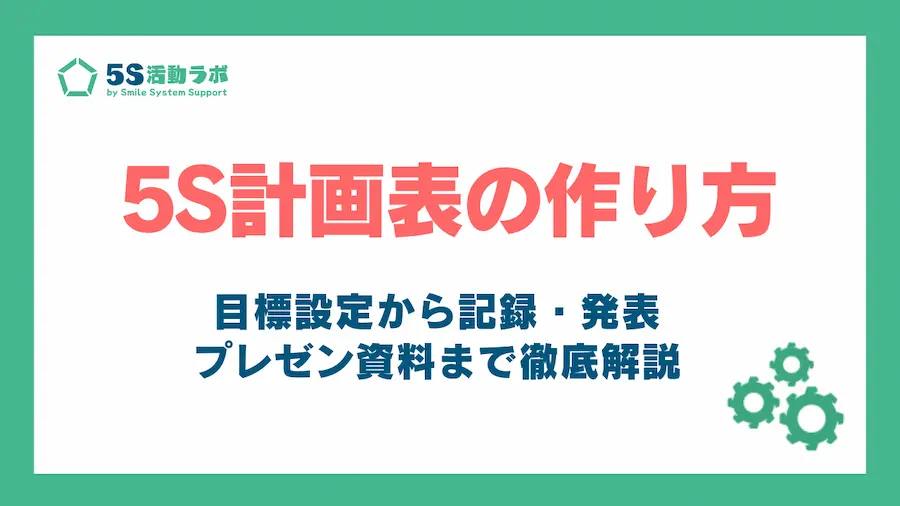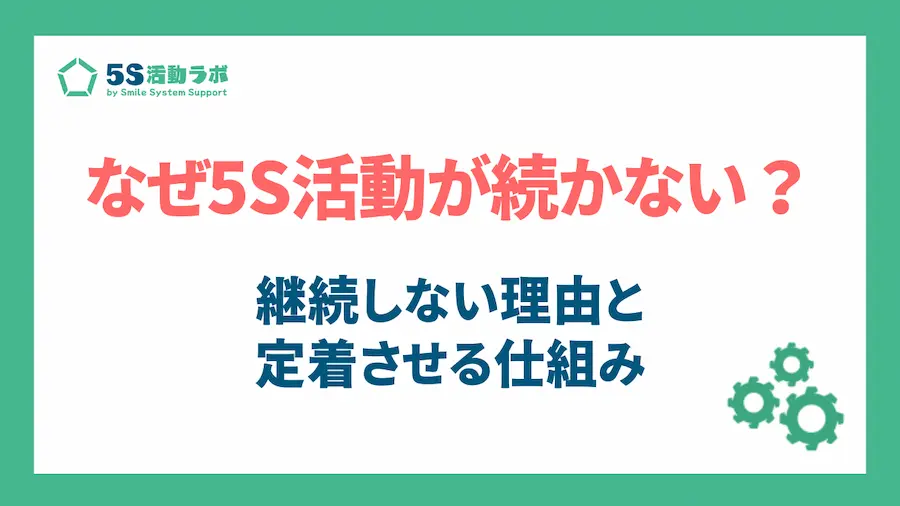
もくじ
5S活動が続かない企業が、つまずいている本当の理由とは?
「5Sを導入したけれど、結局長続きしなかった」
「最初は取り組んでいたけど、気づけばフェードアウトしていた」
そんな声を、私たちはこれまで数多くの企業から伺ってきました。
実際、弊社に5S研修を依頼される企業の多くが、一度は自力で5S活動にチャレンジした経験があります。しかし、正しいやり方が分からない、思うように続けられないという理由から、外部の支援を求めて来られます。
本来の業務に加えて新たな改善活動を継続するのは、確かに簡単なことではありません。だからこそ、「なぜうまくいかないのか」を明らかにし、無理なく続けられる仕組みが必要です。
この記事では、5S活動が定着しない理由と、その解決策としての継続のコツを具体的にお伝えします。これから5Sに取り組もうとしている方も、過去に失敗経験のある方も、ぜひ参考にしてみてください。
5S活動とは?5Sの意味とそれぞれの内容を整理
5S活動とは、「整理・整頓・清掃・清潔・躾(しつけ)」の頭文字を取った、日本発の職場改善手法です。
製造業や病院、オフィスなど、さまざまな業種で導入されており、環境整備や業務効率化、安全性の向上を目的とした取り組みです。
それぞれのSには、以下のような意味があります:
- 整理
要るモノと、要らないモノを分類し、要らないものを捨てること - 整頓
要るモノを、誰にでも、すぐに取り出せるようにすること - 清掃
ゴミや汚れがない綺麗な状態を維持すること - 清潔
3S(整理・整頓・整頓)が維持されている状態 - 躾(しつけ)
3Sが定着し、決められたことを守れる風土になっている状態
このように、5Sは単なる片付けではなく、職場全体の「考え方」「習慣」を変える活動です。
こちらもCHECK
-

5Sとは?職場改善の基本を徹底解説!目的・進め方・成功事例をわかりやすく紹介
はじめに:トヨタ発祥の「5S活動」で職場を変える 現代の企業や組織が抱える課題には、業務効率の低下や安全性の欠如、社員育成や社内コミュニケーションの問題など様々です。これらを解決するための強力なアプロ ...
続きを見る
5S活動の本当の目的とは?ただの掃除ではない理由
5S活動というと、「職場をきれいにする取り組み」と捉えられがちですが、それは表面的な一部にすぎません。
5Sの本質は、安全・快適・効率的な職場をつくることにあります。
安全:事故やケガのリスクを減らし、安心して働ける職場をつくる
快適:働く人の心と体にストレスの少ない、居心地のよい環境を整える
効率的:ムダな動作や探し物を減らし、本来の業務に集中できる仕組みをつくる
この3つの目的に沿って5Sを続けることで、職場の雰囲気や社員の意識が変わり、企業風土そのものが前向きに変化していきます。
こちらもCHECK
-

5S活動の目的とは|安全・効率・快適、そして躾で職場を変える
5Sとは、整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字を取った、職場改善の基本活動です。5Sとは何か?はこちらの記事で解説しています。 本記事では、その中でも多くの企業が最初に直面する疑問である「5S活動の目的 ...
続きを見る
なぜ5S活動は続かないのか?よくある5つの原因
「5S活動に取り組んでみたものの、気づけばやらなくなっていた」
そんな悩みを抱える企業には、いくつかの共通した原因があります。
多くの場合、次のような要素が5S継続の壁となっています:
- 社員がそもそも5Sをやりたくない
- 活動の目的が明確に共有されていない
- 忙しさを理由に、いつの間にか後回しにされる
- 上司が部下に任せきりで当事者意識がない
- ルールが存在しない、または守られていない
ここからは、それぞれの原因について詳しく解説していきます。
1. 社員が「やりたくない」と感じている
5S活動が続かない最大の原因のひとつが、社員自身が最初から前向きではないという点です。
5Sは通常業務とは別の取り組みであり、「面倒くさい」「余計な仕事を増やされたくない」と感じるのは自然なことです。
さらに、「今のやり方を変えたくない」「現状維持で十分」という心理的な抵抗もよく見られます。
こうした社員の本音を無視して5Sを進めると、表面的には始まっても長続きしません。
まずは社員が抱く不安や抵抗感を受け止め、それを超える意味や価値を共有することが、継続への第一歩です。
2. 活動の目的が不明確で共有されていない
5S活動を継続させる上で最も重要なのが、「なぜやるのか?」という目的の明確化です。
そもそもやりたくないと感じている社員に対して、「何のために取り組むのか」が伝わっていなければ、行動する理由も意義も見いだせません。
5S活動は単なる美化運動ではなく、
- 作業の効率を上げる
- ケガや事故を防ぐ
- 快適で働きやすい環境をつくる
といった明確なゴールがあります。
「この活動を通して、何が良くなるのか?」「自分たちにどんなメリットがあるのか?」
これらの問いにしっかり答え、目的を社員と共有できていれば、取り組みの姿勢や継続性は大きく変わります。
👉 5S活動のスローガン・目標の作り方
👉 5S活動定着に効果的「個人面談」の進め方
3. 「忙しいから後回し」になり、自然消滅してしまう
5S活動を始めても、業務が忙しくなると「今はそれどころじゃない」と後回しにされがちです。
この状態が続くと、気づけば活動そのものが忘れられ、フェードアウトしてしまうというパターンは非常に多くの現場で見られます。
本業が優先されるのは当然ですが、少しの時間でも継続する工夫がなければ、5Sはいつまで経っても形になりません。
- 毎日5分だけでも時間を確保する
- 月1回の定例会議で振り返る時間を入れる
- 担当者を固定しないなど、負担を分散する
こうした工夫によって、忙しくても少しずつ前進できる環境を整えることが、継続のカギとなります。
👉 5S活動に全員参加が難しい会社のための小グループ活動の進め方
4. 上司が5S活動を“部下任せ”にしている
5S活動が定着しない職場でよく見られるのが、上司が現場任せ・部下任せにしているパターンです。
「整理整頓や掃除は若手の仕事」「現場がやるべきもの」といった認識があると、上司は当事者意識を持てず、活動を支える側に回りません。
しかし、5Sは一部の人だけが頑張っても成果は出ません。
- 上司がルールを守らない
- 指示だけ出して自分は関わらない
- 活動の意義を理解せず、単なる“清掃作業”と捉えている
こうした状況では、現場の士気が下がり、やがて活動自体が形骸化していきます。
5Sを会社全体で続けるには、上司こそが率先して動き、模範を示すことが不可欠です。
5. ルールがない、または守られていない
5S活動が定着しない大きな原因のひとつが、ルールが存在しない、あるいはあっても守られていないという状態です。
5Sの基本は「ルールを決め、それを全員が守ること」。この積み重ねが「躾(しつけ)」につながります。
たとえば、ルールがなければこんな問題が起こります:
- 「捨てる・捨てない」の判断基準が人によってバラバラ
- モノの定位置が決まっておらず、探し物が絶えない
- 清掃当番が曖昧で、人任せになる
- 上司がルールを無視して、現場が混乱する
こうした状態が続けば、「自分だけが頑張っている」「やってない人がいるからやらない」といった空気が生まれ、5Sは徐々に崩れていきます。
まずは「捨てる基準」「モノの置き場所」「清掃ルール」など、具体的なルールを話し合って決めましょう。
そして、ルールが守られていないと感じたら、人を責める前に「そのルール自体に無理がないか?」を見直す視点も必要です。
守れるルールを作り、全員で守る仕組みを整えることが、5Sの継続には不可欠です。
こちらもCHECK
-

5Sルールとは?決め方・事例・守れる仕組み化まで徹底解説
5Sルールとは、整理・整頓・清掃・清潔・しつけを職場に定着させるための行動基準です。 多くの会社で5Sが続かない原因は「ルールがあいまいなまま」になっていることにあります。 本記事では、5Sルールの意 ...
続きを見る
5S活動を継続・定着させるには?仕組み化が成功のカギ
5S活動は、日々の業務とは異なる“プラスアルファの取り組み”であるため、忙しい職場ほど後回しにされやすいものです。
「今日は忙しいから後にしよう」
「会議は決まっていたけど、今回は見送ろう」
そんな状態が続くと、気づけば5Sは忘れられ、自然消滅してしまいます。
しかし、継続しなければ5Sの効果は現れません。
現場が変わらなければ、快適さも効率も安全性も向上しないままです。
そこで必要なのが、「仕組み化」です。
たとえ少しずつでも、続けられる設計にしておくことで、無理なく定着へとつながっていきます。
5S継続の仕組みづくりは「1ヶ月スパンのPDCAサイクル」から
5S活動を継続的に行うためには、「1ヶ月ごとのPDCAサイクル」で進めていくのが効果的です。
Plan(計画):活動の方針と目標を立てる
Do(実行):実際に活動を行い、記録を残す
Check(振り返り):活動の進捗や成果を確認する
Act(改善):次回に向けた改善策を話し合う
1. 計画を立てる(Plan)
まずは、可能な限り全社員参加で5S会議を開催しましょう。
弊社の5Sコンサルティングでは、経営者ご本人にも必ずご参加いただいています。
会議では、以下のような内容を共有・決定します:
- 今回の5S活動を通じて「何を改善したいか」
- 各部署ごとに、1ヶ月間で取り組む具体的な内容
- 次回の5S会議の日程
活動は「整理 → 整頓 → 清掃」の順で進めていくのが基本です。
5S計画表の作り方
-

5S計画表の作り方|目標設定から記録・発表・プレゼン資料まで徹底解説
5S活動を始めても、「やりっぱなしで続かない」「計画が形だけで終わっている」という声をよく耳にします。現場任せのままでは改善が属人的になり、せっかくの取り組みが定着しません。 計画が曖昧なままでは、成 ...
続きを見る
最初のステップである「整理」では、赤札作戦から始めることをおすすめします。
2. 実行し、活動を「見える化」する(Do)
計画した内容に沿って、各部署で5S活動を実行していきます。
実行にあたって重要なのは、活動の記録を残すことです。
- 実施前と実施後の写真を撮る(ビフォーアフター)
- 使用した時間や取り組んだ内容をメモする
- 予想と違った点や、計画通りにいかなかった点も記録する
こうした記録があることで、次の振り返り(Check)に活かすことができ、5Sの“成果”を見える形で社内に伝える材料になります。
特にビフォーアフターの写真は、成果を実感しやすく、社員のモチベーション維持にも効果的です。
3. 活動を振り返り、チームで共有する(Check)
活動開始から1ヶ月後には、再び全体会議を開き、各部署の進捗と成果を報告し合いましょう。
- 予定通り進んだこと
- 実際に出た成果(写真や数値)
- 計画通りにいかなかった理由と現場の声
こうした情報をオープンに共有することで、お互いの取り組み状況が可視化され、良い意味での“刺激”が生まれます。
活動が進んでいるチームの成果は、他チームにとって大きな参考になりますし、
「うちはまだ何もできていない…」という焦りが、次への行動意欲につながることもあります。
報告会と振り返りの時間こそが、5S活動を“他人ごと”から“自分ごと”に変える重要なステップです。
こちらもCHECK
-

5S振り返りのやり方|毎月の報告書とKPTで改善を定着させる方法
5S活動を続けていると、最初のうちは成果が見えても、しばらくすると「やりっぱなし」で元に戻ってしまう…そんな悩みはよく聞かれます。 そこで大切なのが 定期的な振り返り。 毎月の振り返りでは報告書フォー ...
続きを見る
4. 改善点を見つけ、次のアクションを決める(Act)
活動報告の後は、社内を実際に点検しながら、新たな課題や改善したいポイントをチームで洗い出します。
このとき、前回の反省点や「うまくいかなかった原因」も丁寧に振り返りましょう。
たとえば:
- なぜ実行できなかったのか?
- 誰が、どこで、どんな点につまずいたのか?
- その課題をどうすれば乗り越えられるのか?
改善策がまとまったら、再び次の1ヶ月間の活動計画(Plan)へとつなげていきます。
この一連の流れを毎月のサイクルとして繰り返すことで、5S活動は自然と職場に根づいていきます。
PDCAサイクルを繰り返すことで、5Sは自然と職場に根づく
毎月のPDCAサイクルを地道に繰り返すことで、5S活動は徐々に社内に浸透していきます。
ときには思うように進まないことがあっても、“定例会議だけは必ず続ける”というルールを守るだけでも、活動は止まりません。
少しでも成果が見えてくると、5Sの意味が実感でき、社員の意識や行動にも変化が生まれます。
重要なのは、「止めないこと」。小さな一歩でも積み重ねが大きな変化を生みます。
まとめ:5S活動を社内に定着させるために必要なこと
5S活動がうまくいかない理由は企業によってさまざまです。
「社員の反発」「目的の曖昧さ」「時間の確保」「上司の関与不足」「ルール不在」── どこに原因があるかをまず見極めることが、改善の第一歩です。
そして、どんなに忙しくても、1日3分でも良いので“継続する仕組み”を作ることが、定着のカギとなります。
まずは全員で目標を共有し、小さくても行動を始めてみてください。
その一歩が、職場の空気を変え、会社全体の成長へとつながっていきます。